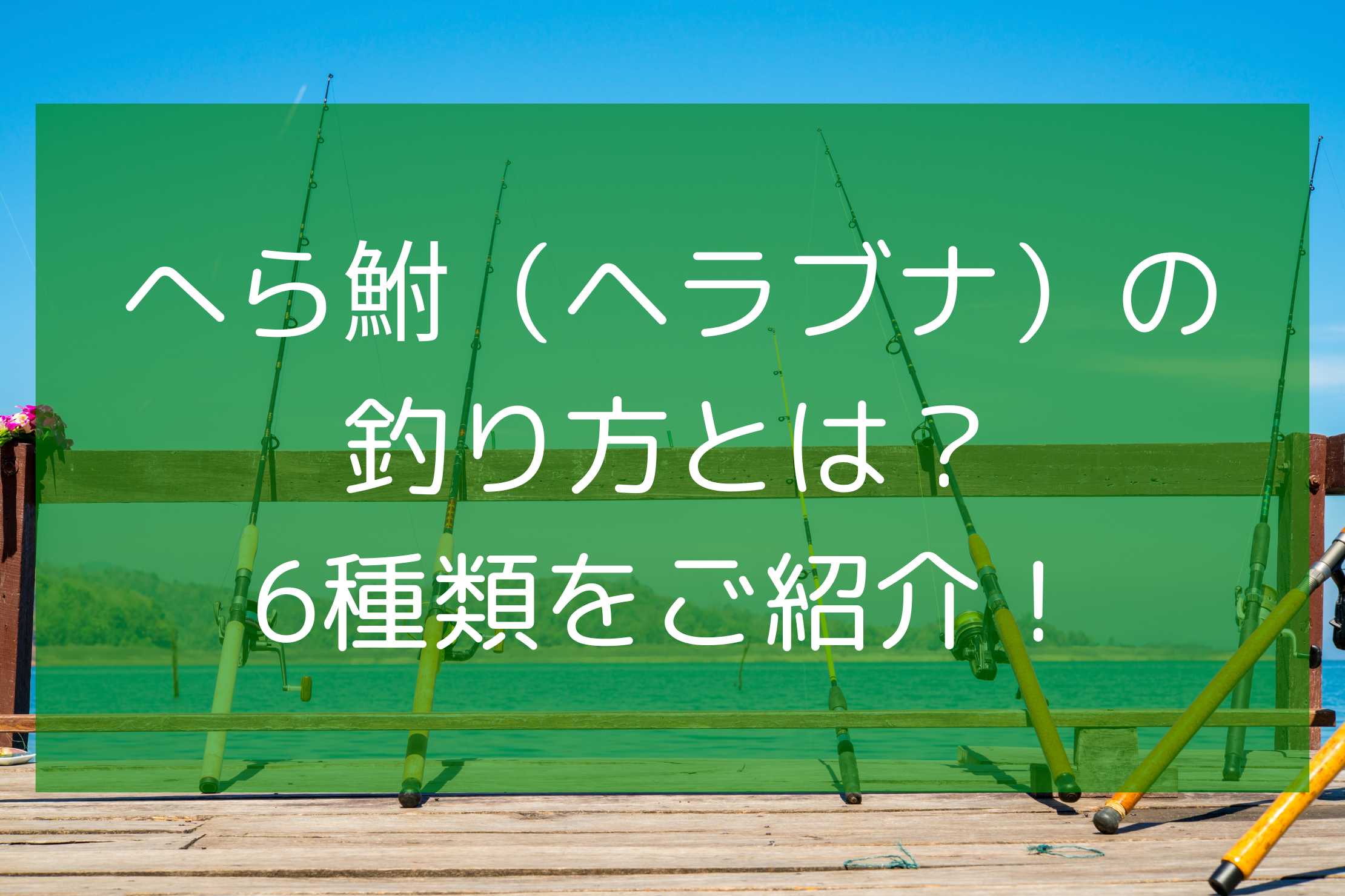Contents
- 1 ヘラブナ釣り概要|まずは「ヘラブナ」「マブナ」についてご紹介
- 2 へらブナ(鮒)釣りに使用する「タックル」「仕掛け」「必要な道具」まとめ
- 3 ヘラブナ釣りの「準備作業」「仕掛けの作り方」を解説!
- 4 へら鮒(ヘラブナ)の釣り方|6種類を解説
- 4.1 へら鮒(ヘラブナ)の釣り方:「メーター釣りの両ダンゴ釣り(メーター両ダンゴ釣り)とは?
- 4.2 へら鮒(ヘラブナ)の釣り方:メーター釣りのセット釣りとは?
- 4.3 へら鮒(ヘラブナ)の釣り方:深宙釣り(チョウチン釣り)とは?
- 4.4 へら鮒(ヘラブナ)の釣り方:段差の底釣りとは?
- 4.5 段差の底釣りの仕掛けについて
- 4.6 へら鮒(ヘラブナ)の釣り方:底釣りとは?
- 4.7 底測りとは?
- 4.8 底釣りの浮子について解説
- 4.9 底釣りの仕掛けのひとつ「共ずらし」とは?
- 4.10 「仕掛け(共ずらし)」のポイントは?
- 4.11 ヘラブナ釣り編:これからエントリーする人は水層(タナ)を見極めやすい「底釣り」から覚えよう!
- 4.12 マブナ編:「シモリウキ」を使って細かいアタリを感じ取ろう!アクティブに誘い攻めることが大切!
ヘラブナ釣り概要|まずは「ヘラブナ」「マブナ」についてご紹介
まずはヘラブナ釣りの概要として「ヘラブナ」「マブナ」についてご紹介です。
「ヘラブナ釣りを始めたいけどヘラブナについて知らない!」「そもそもヘラブナってどんな魚?」といった疑問を解決できると思います。
さっそく「ヘラブナ」「マブナ」がどんな魚なのか見ていきましょう!
「ヘラブナ」「マブナ」ってどんな魚?
ヘラブナとは、ゲンゴロウブナという琵琶湖や淀川水系に生息していた魚を品種改良して誕生しました。
体高が高くなるよう人工的に作られたヘラブナは、なんと最大で魚体が50cm以上に育つそうです。
成長もはやく、約3年で30cmほどまで大きくなりますよ!
マブナとは、野生のフナの総称ことで、ヘラブナと区別するために名付けられました。
主に金ぶな(キンブナ)や銀ブナ(ギンブナ)のことを指します。
マブナは河川の下流域、湖沼などに生息していて、簡単に釣れることもあり初心者さんに人気の高い魚です。
「ヘラブナ」「マブナ」を狙うポイントはどこ?
ヘラブナとマブナ共に、水の流れが穏やかな場所を好む傾向があります。
具体的に、水草の周辺、障害物周りの中層〜低層に生息している可能性が高いです。
上記のポイントを入念に探ることで、釣果を伸ばすことができると思います。
ヘラブナは主な餌源としてプランクトンを捕食します。
特に植物性プランクトンを好んで食べ、水中の微小生物や藻類を濾過して摂取することもあります。
マブナは雑食性で、基本的になんでも食べます。
具体的にアカムシやミミズなど底生動物、藻、動物プランクトン好んで摂取するそうです。
【ヘラブナ釣り&マブナ釣りの概要一覧】
- オススメシーズン:春から秋の暖かい時期(4月〜10月)
- 一緒に釣れる魚:オイカワ、ウグイ、コイ、モツゴ(クチボソ)、モロコ、タナゴなど
- おすすめな釣りフィールド:水の流れが穏やかな中流や下流、湖沼、池など
へらブナ(鮒)釣りに使用する「タックル」「仕掛け」「必要な道具」まとめ
一般的に、ヘラブナ釣りで使用する「タックル」「仕掛け」「道具」をまとめていきます。
ヘラブナ釣りに興味のある人は、ぜひ参考にしてください!
タックル①:「ヘラブナ用ロッド」とは?
下記にヘラブナ用ロッドに必要なアイテムをまとめていきます。
【ヘラブナ用ロッドに必要なアイテム】
- ヘラ竿(2.7m〜3.9m)
- 道糸:ナイロンライン(0.8号〜1.2号)
- ヘラウキ
- ウキゴム・ストッパー
- 板オモリ
- ヨリモドシ
- ハリス:ナイロンライン(0.4号〜0.8号)
※上バリ→25cm・下バリ→30cm - ハリ:ヘラ(3号〜6号)
上記の「ヘラブナ用ロッドに必要なアイテム」を読んでみて気になるポイントはありましたか?
オーソドックスなヘラブナ釣り(底釣り)を楽しむなら、この仕掛けを押さえておくと◎です。
初心者さんは「仕掛けの全長=ロッドの長さと同じ程度」を目安にしてください。
とてもバランスが取れた設定です。
仕掛けの操作性が向上する、ヘラブナの食い込みが良くなりますよ!
また、使用する「袖バリ=1号~3号」にするのもおすすめ。
ヘラブナ以外に「モツゴ」なども狙えちゃいます♪
タックル②:「マブナ用ロッド」とは?
下記にマブナ用ロッドに必要なアイテムをまとめていきます。
【マブナ用ロッドに必要なアイテム】
- 振り出し万能ロッド(3m〜5.4m)
- 道糸:ナイロンライン(1号〜1.2号)
- シモリウキ
- 幹糸:ナイロンライン(1号〜1.2号)
- ガン玉
- ヨリモドシ
- ハリス:ナイロンライン(0.4号〜0.8号/20cm)
- ハリ:袖バリ(2号〜5号)
ヘラブナ釣りに「関連する釣り糸の結び方」とは?
ヘラブナ釣りやマブナ釣りをするなら押さたい「結び方」をまとめていきます。
【押さえたい結び方】
- チワワ結び
- クリンチノット
- 外掛け結び
「エサ」「エサ付け」とは?
ヘラブナ釣り・マブナ釣りでは「エサ」を使用します。
つまり「エサ」「エサ付け」の知識はとても重要なのです!
ヘラブナ釣りやマブナ釣りにチャレンジするなら、絶対に押さえましょう。
ヘラブナは「練りエサ」を使用して釣果を狙います。
通常、練りエサは「バラケ用」「食わせ用」の2種類を用意するのですが..。
ベスト配合の仕方にはコツがあり、正直ビギナーさんが作るのは難しいかと。
ヘラブナ入門したての方には、市販品から揃えるのをおすすめします!
まずは、市販品に付いてくる説明書通りに「練りエサ」を作るのが◎
失敗しないので、1番無難な選択でしょう!
エサを準備できたら、ハリが隠れるくらいの量を手に取ります。
その後、ハリの結び目が隠れるようすっぽり包み、丸め込んだらヘラブナ釣りスタートです!
マブナを狙うなら「アカムシ」を用意してください。
アカムシ「2匹〜3匹」をちょん掛けで針に付けたら準備完了なので、マブナ釣りスタート!
一応、ヘラブナ同様「練りエサ」を使用して、マブナを釣ることも可能です。
ヘラブナ釣りで使う「釣竿」の使い分けとは?
釣竿の長さは「用途」に合わせて選ぶのがおすすめ!
下記に「竹竿」「カーボン竿」「グラスファイバー竿」の使い分けをまとめました。
【釣竿使い分け】
- 竹竿:独特な「粘り」「コシの強さ」が魅力。
※高価なことが懸念点。 - カーボン竿:「軽量」「丈夫さ」が魅力。
※価格が安い場合がある。 - グラスファイバー竿:「安価」が魅力。
※重いのが懸念点。
上記の「釣竿使い分け」を読んでみて気になるポイントはありましたか?
一般的には「8尺〜21尺」の釣竿を選ぶと◎です。
目安ですが「1尺=約30cm」なので、ぜひ参考にしてください♪
近年、ヘラブナ釣りで使用される釣竿の主流は「カーボン製」です。
仕掛け①:「浮子(うき)」
浮子は「トップ」「ボディ」「足」の3パーツから形成されています。
トップについて
「径=1mm前後」を使用すると◎
トップの素材として「セルロイド製(パイプ)」「ポリカーボネイト/PC(パイプ・ムク)」「グラスファイバー製(ムク)」が有名どころ!
※「パイプ=中空」なので、浮力がある。
※「ムク=中身が詰まっている(比重が重い)」ので、浮力がない。
ボディについて
「径=4mm〜6.5mm」を使用すると◎
主流となる素材として「孔雀の羽根」「萱(かや)」が有名どころ!
他にも「バルサ」「発砲スチロール」も使われます。
足について
「径=1.2mm前後」を使用すると◎
素材として「竹」「カーボン」「グラファイバー」が有名どころ!
浮子(ウキ)の種類について
基本的に「底釣り用」「宙釣り用」がある。
釣り方に合わせて選ぶと◎
浮子(ウキ)に対するオモリの調整
浮子(ウキ)のトップが「約2/3程度」見える位置になるよう、オモリを調整してください!
オモリの調整は、ハサミで切りながら行うと良いですよ。
エサ落ちメモリが見えるようにするのがマスト。
仕掛け②:釣り糸
釣り糸の主流は「ナイロンライン」です。
ヘラブナ釣りでは「道糸」「ハリス」2タイプを使い分ける必要があります。
道糸とは?
道糸とは、仕掛けに使われる釣り糸です。
一般的に「竿先〜竿尻」くらいの長さをしています。
「0.3号~3号」程度の道糸を準備すると◎
ハリスとは?
ハリスとは、釣り針(鈎)に直接結ぶ釣り糸のこと。
一般的に「道糸の半分(1/2)の号数を使用しましょう!
目安は「0.2号~2号」くらいが◎
仕掛け③:オモリ
「オモリ=板状の鉛」と捉えてOK。
狙った水層(タナ)に仕掛けを届けるために必須となるアイテムです。
一般的に「オモリの厚さ=0.1mm~0.3mm」のものを使用します!
仕掛け④:ヨリモドシ
ヨリモドシは「サルカン」や「スイベル」と呼ばれる場合も!
道糸とハリスの接続部分に使用することで「糸ヨレを防ぐ」「ヨリを戻す」役割を担います。
仕掛け⑤:鈎(釣り針)
鈎(釣り針)には「かえし」がないタイプを使用してください。
かえしがあると、ヘラブナを痛めるため注意です。
釣り場のレギュレーション違反になる場合も!
繰り返しになりますが「かえしがある鈎(釣り針)」の使用は絶対に避けましょう!
鈎(釣り針)の大きさは「1号~20号」くらいまで、幅広く使用します。
仕掛け⑥:餌(えさ)
ヘラブナ釣りでは、さまざまな食材を「加工配合」した餌を使用します。
具体的に「ジャガイモ」「とろろ昆布」「さなぎ」「魚粉」「小麦」「麩」などを練り合わせますよ!
ちなみに、餌(エサ)の配合は「経験」「好み」「釣り場」「状況」に応じて調整することがほとんど。
初心者さんには、市販されている「練り餌」の購入をおすすめします。
必要な道具①:竿受け
竿受けは、ヘラブナを釣るときに「釣竿を乗せておく」アイテムです。
ヘラブナ釣りは「アタリを待つ」「餌を付ける」際に、釣竿を竿受けに置く必要があります。
竿受けがあるかないかで、ヘラブナ釣りの「快適性」「効率」が大きく変わる、本当に重要なアイテムなのです。
必要な道具②:万力(まんりき)
万力(まんりき)は、竿受けを釣り台に固定する道具です。
素材として「木製」「鉄製」が代表的に使用されています。
必要な道具③:タモ
タモとは、ヘラブナをすくう釣り道具です。
魚を傷つけず、安全に釣り上げるために必須になります。
必要な道具④:フラシ
フラシとは、釣ったヘラブナを一時的に入れておく網のこと。
繊細なヘラブナを安全に保管できるので、弱らせずに済みます。
ヘラブナを大切に扱う上でとても重要なアイテム!
基本的には「長さ:1m〜2m」「直径:40cm〜50cm」で筒状の形をしています!
必要な道具⑤:ヘラバック(ヘラかばん)
ヘラバック(ヘラかばん)は釣り道具を入れておけるアイテムです。
一般的には「小物類」「エサボウル」を入れておきます。
下記に「ヘラバックに入れておくと便利なアイテム|一覧」をまとめました。
【ヘラバックに入れておくと便利なアイテム|一覧】
- ハリはずし
- ハサミ
- バケツ
- 計量カップ
- 玉網
- タオル
- ビニール袋
- 道糸
- ハリス
- 針
- メジャー
ヘラブナ釣りの「準備作業」「仕掛けの作り方」を解説!
ヘラブナ釣りの「準備作業」「仕掛けの作り方」を解説です。
専門用語が多く出てくるので「※(コメ印)」の後ろに「役割」をまとめています。
この見出しを読んでヘラブナ釣りの準備をスムーズに行いましょう!
準備: 道糸にちち輪を作ろう
ちち輪とは、リリアンと道糸を接続するために使用する結び方です。
※リリアン→リールを使わない釣竿(のべ竿)の穂先に付いている、糸を結ぶためのヒモ状の部品。
ちち輪を作る時は、こま結びではなく、8の字結びで作成することをおすすめします。
なぜなら、こま結びに比べ8の字結びの方が「強度」と「使いやすさ」が良いからです。
8の字結びは、こま結びよりも結び目が小さいので、摩擦によるダメージを軽減することが可能になります。
ダメージを軽減できるので、強度が向上するんです。
これからヘラブナ釣りを始める人には、こま結びの方が簡単に結ぶことができます。
あなたが習得している結び方でちち輪を作成してくれてOKです。
準備:道糸に「遊動ストッパー」「浮子ゴム」を取り付けよう
遊動ストッパーをひとつ道糸に取り付けましょう。
まずは、遊動ストッパーにある輪の中に道糸を通してください。
道糸を通すことができたら、浮子ゴムを道糸側に動かすことで、遊動ストッパーを道糸に取り付けることができます。
※遊動ストッパーの役割:ウキやオモリが水面を自由に移動できるようにすること。
※浮子ゴムの役割:ウキを道糸に固定する、ウキが道糸の中で遊動するのを防ぐこと。
準備:道糸に「ヨリモドシ」を取り付けよう
続いて道糸を竿尻(釣り竿の手元側の末端部分)でカットしたら、道糸にヨリモドシを設置しましょう。
ヨリモドシは、道糸とハリスをつなぐ箇所に設置するので、釣り知識として押さえてくださいね。
ヨリモドシを設置することで、釣り糸が捻れたり、釣り糸が絡んだりすることを防ぎます。
準備:「ハリス」を取り付けよう
続いて、ヨリモドシにハリスを付けましょう。
ハリスは、道糸に釣り針を繋いだり、仕掛けの全長を調整したり、仕掛けを魚から見えにくくするといった役割を担います。
準備:「オモリ」を取り付けよう
ヨリモドシの上にオモリを付けたら、仕掛けの準備完了です
オモリを付けることで、仕掛けの重量を調整できますし、ウキの浮き沈みをコントロールすることも可能になります。
へら鮒(ヘラブナ)の釣り方|6種類を解説
へら鮒(ヘラブナ)の釣り方を6種類を解説していきます。
下記に今回紹介する「へら鮒(ヘラブナ)の釣り方まとめ」を記載しているので、まずは全体把握をしてきましょう!
【へら鮒(ヘラブナ)の釣り方まとめ】
- メーター釣り
- 両ダンゴ釣り
- セット釣り
- 深宙釣り(チョウチン釣り)
- 段差の底釣り
- 底釣り
へら鮒(ヘラブナ)の釣り方:「メーター釣りの両ダンゴ釣り(メーター両ダンゴ釣り)とは?
メーター釣りの両ダンゴ釣り(メーター両ダンゴ釣り)についてご紹介です。
そもそもメーター釣りとは、ヘラブナ釣りの釣法のひとつのことを言います。
ウキ止めからオモリまでの距離を1mに設定して、浅い水層(タナ)にいるヘラブナを狙っていく釣り方です。
そんなメーター釣りには、上鈎と下鈎を2つの釣り針を使用しています。
上鈎のハリスの長さは30cm~40cm、下鈎のハリスの長さは10cm前後長い40cm〜50cmのものを用意してくださいね。
上鈎と下鈎の両方に「ダンゴ」と呼ばれる、麩のえさに水を入れて混ぜた物を付けて魚を狙う釣り方が「メーター釣りの両ダンゴ釣り(メーター両ダンゴ釣り)」です。
ダンゴの大きさは、パチンコ玉位が理想ですよ!
へら鮒(ヘラブナ)の釣り方:メーター釣りのセット釣りとは?
セット釣りとは、バラケエサ(魚を寄せる)とクワセエサ(釣り針に食いつかせる)の2種類を用いて、ヘラブナを狙う釣り方のこと。
上記のセット釣りと、浅い水層(タナ)にいるヘラブナを狙っていくメーター釣りを組み合わせた釣り方を「メーター釣りのセット釣り」としてご紹介していきます。
メーター釣りのセット釣りでは、上鈎に「ダンゴ」を下鈎にはクワセエサとして「喰わせ」を付けましょう。
ダンゴには、バラケエサとクワセエサの役割を1つのエサで兼ね備えていて、魚を寄せて食わせることが可能です。
喰わせとは、ヘラブナの食欲を刺激する効果があるので、釣り針にヘラブナが食いつくことが多くなります。
ワラビうどん、即席うどん、グルテン、とろろ昆布等を喰わせとして使用することができますよ。
短い方のハリス(上鈎のハリス)を8cm~15cm、長い方のハリス(下鈎のハリス)を30cm~40cm程度がだと、釣果が安定します。
へら鮒(ヘラブナ)の釣り方:深宙釣り(チョウチン釣り)とは?
深宙釣り(チョウチン釣り)とは、釣竿の長さ一杯の水層(タナ)を狙う釣り方のこと。
深い水層(タナ)にいるヘラブナをターゲットに釣りを楽しみましょう。
穂先から約30cm〜50cmくらい下に浮子を付けることが特徴です。
釣竿と浮子の距離が近いので、ヘラブナがエサに食い込んだ瞬間の衝撃をダイレクトに感じられることが、深宙釣り(チョウチン釣り)の醍醐味といえます。
両ダンゴ釣り、セット釣りどちらの釣り方とも組み合わせることが可能です。
これは余談ですが、棒に提灯(チョウチン)を付けた状態に見えたことから「深宙釣り(チョウチン釣り)」と呼ばれるようになったそうです。
へら鮒(ヘラブナ)の釣り方:段差の底釣りとは?
段差の底釣りとは、バラケエサ(上鈎)とクワセエサ(下鈎)のハリスの長さを変える(段差を取る)ことが特徴。
釣り方自体はセット釣りなのですが、下鈎のクワセエサが水底に着いていることが大きな違いです。
上鈎のバラケエサと下鈎のクワセエサに段差を設けるメリットとして、バラケエサが宙にばらけるので「水底にヘラブナが密集する」ことがあります。
水底にヘラブナを密集させることで、食わせる確率がぐーんと高くなりますよ!
冬などの極寒期では、ヘラブナが水底にいることが多いので、段差の底釣りとても有効な釣り方といえますね。
短い方のハリス(上鈎のハリス)の長さを15cm~30cm程度、長い方のハリス(下鈎のハリス)の長さを45cm〜70cm程度にしておくと◎
底の測り方及び浮子の位置合わせ(底取り)
まずは、底取りをするために下鈎にオモリを付ける、エサの動きをコントロールするために浮子にフロート(穴明き発砲スチロール)を付けましょう!
オモリを水底に付けて、浮子の経つ位置30cm四方の水深を測定してください。
浮子の経つ位置30cm四方の水深を測定しながら、水底の凹凸を確認しておくと◎
続いて、水面に浮子のトップができているかと思います。
浮子のトップが出ている位置と同じ箇所の道糸に目印を付けてください。
目印には、木綿糸を使用することがあるみたいです。
最後にエサ落ちメモリより2cm〜3cmくらい浮子を穂先に向けて上げたら「底取り」の準備完了です。
段差の底釣りの仕掛けについて
道糸:0.6号~0.8号(ナイロンラインorフロロカーボンラインを使用する)
上ハリスの太さ:0.4号〜0.5号程度
下ハリスの太さ:0.2号〜0.3号程度
上ハリスの長さ:10cm〜30cm程度
下ハリスの長さ:30cm〜70cm程度
上ハリ:4号~6号(フトコロが広め)
下ハリ:2号~4号(吸い込みのよい)
へら鮒(ヘラブナ)の釣り方:底釣りとは?
エサを水底に着けてヘラブナを釣る釣り方のことを言います。
水底にエサを置くことで、ヘラブナを寄せやすいこと、魚のアタリが明確にでやすいことが特徴です。
ヘラブナの活性が高い時期の春から秋にかけて威力を発揮してくれます。
底釣りではタナ取り(水深測定)が非常に重要です。
タナ取り(水深測定)をしっかりと行うことで、仕掛けのバランスを調整すること(上鈎がギリギリ着底するくらいが◎)が釣果を安定させるコツ。
一般的な底釣りにおけるハリスの長さは、上ハリス20cm〜30cm程度、下ハリスが30cm〜40cmと考えてくれてOKです。
底測りとは?
底測りは、底釣りをするために欠かすことのできない工程です。
底測りを行うことで、正確なタナ(水深)を測定する、エサが水底に着くようにすることができます。
底測りを怠った場合、水底にエサが着いていないので「ヘラブナの食いつきが悪い」「ヘラブナのアタリが取れない」ことが起こりやすくなります。
ぜひ、底釣りをする際は「釣り座の状態に合わせた、正確な底測りをする!」ということを念頭に入れておいてくださいね。
下記に底取りの手順をまとめたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
【底取りの手順】
STEP①:底取りオモリを上鈎に取り付けるて、空バリの状態にする。
※空バリとは針に餌をつけていない状態(針だけの状態)
STEP②: 板オモリの量を調整して、浮子のトップが水面から約2/3程度の高さになるようにする。
STEP③:仕掛けを水中に投げ入れて、浮子が水面から「どの位置で立つ?」のかを確認する。
STEP④:浮子の立ついちで水深を判断する。
※浮子のトップが水面約2/3程度で立つのなら、水深が浅いと考えてOK。
STEP⑤:判断した水深に合わせて、オモリの量や浮子も種類を調整して、水底に針が届くようにする。
底釣りの浮子について解説
底釣りで使用されるウキは、竹足タイプ、トップが短い、細くて長めのボディをしていることが多いのですが..。
ぜひ、水深の深さに応じて浮子の長さを調整してみてください。
以下に「底釣りの浮子のサイズ目安」をまとめたので、ざっくりを把握してみましょう!
【底釣りの浮子のサイズ目安】
26cm:8尺~10尺
28cm:9尺〜12尺
30cm:11尺〜13尺
32cm:12尺〜15尺
34cm:15尺~18尺
※トップ径:1φ~1.2φ
※尺:釣りの竿の長さを表す単位
※ノーマルな浮きのサイズは26cm~34cm
底釣りの仕掛けのひとつ「共ずらし」とは?
共ずらしとは、ヘラブナ釣りにおける仕掛けのひとつです。
上鈎(上ハリ)と下鈎(下ハリ)両方にエサがついていることが特徴。
バラケエサ(魚を寄せることが目的)とくわせエサ(魚に食わせることが目的)を同時に水底に着けることが可能です。
水底にエサが集まるので魚が寄りやすく、魚のあたりを出しやすいことが魅力的な仕掛けとなります。
「仕掛け(共ずらし)」のポイントは?
ワンポイントとして浮の上に目印(トンボ)を付けてみましょう。
魚が底を掘る(ヘラブナが餌を探すため水底を掘る行為を指す)ことで、水深が1cm〜2cm変化することがあるんです。
そんな時、浮の上に目印(トンボ)を付けておくと、水深の変化を把握することが簡単にできますよ!
【共ずらしの仕掛け】
道糸:0.6号~1.2号程度
上ハリスの太さ:0.4号〜0.5号程度
下ハリスの太さ:0.2号〜0.3号程度
上ハリスの長さ:30cm〜40cm程度
下ハリスの長さ:35cm〜50cm程度(上ハリスより「5cm〜10cm」長くする)
ハリ:3号~5号
ヘラブナ釣り編:これからエントリーする人は水層(タナ)を見極めやすい「底釣り」から覚えよう!
あなたが「ヘラブナに出会いたい!」と考えているなら、まずは底釣りから覚えることがおすすめです。
底釣りとは、水底を探ることが特徴的な釣り方でしたね。
ヘラブナの反応が良い水層(タナ)って季節ごとにが変わるので、釣りをする日で全く違うことが多々あるんです。
底釣りを習得しておくと、水底から探り始めて、徐々にウキ下を短くしていくことで、ヘラブナが反応する水層(食いダナ)を引き当てることができると思います。
上記の考え方は、比較的どのような魚にでも応用することができるので、釣り知識として覚えておくと◎
ヘラブナ釣りの大醍醐味は?
ヘラブナ釣りの醍醐味は「小さいアタリを捉えてヘラブナに釣り針を掛けにいく」ことだと思います。
ヘラブナのアタリって、だいたいはウキのトップ1目盛りほどが沈むか沈まないかと、本当にわずかな反応しか見られません。
この小さいアタリを初心者さんでも捉えるためには「おや?目盛が動いた?」っと感じた瞬間に、必ずアワセを入れることがポイントです!
稀に、ウキが水中に沈んでしまう(ウキが確実に消し込むと表現する)こともあるので、その際は落ち着いて魚に針を掛けにいきましょう。
バラけエサと食わせエサの使い分けは?
ヘラブナ釣りでは、バラけエサと食わせエサを使い分ける必要があります。
バラけエサには、主にグルテンや麩エサなどが使用されることが多いです。
水中にバラけエサを落とすとバラけて落下していき、ヘラブナを集魚させ食わせる効果がありますよ。
一方で、食わせエサにはグルテン、ウドン、麩、マッシュポテトなどが使用されることが多いです。
水中にある食わせエサは、実際に魚を釣り針に掛けることを目的に使われ、食いが渋い時や魚の活性が低い時に効果を発揮しますよ!
簡単にまとめると「バラケエサ=魚を寄せる」「食わせエサ=魚を仕留める」といったイメージでOKです。
ヘラブナ釣りで釣果を伸ばしたいなら、仕掛けをできるだけ同じポイントに投げ入れるようにしてみてください。
魚が特定の場所に集めることができるので、アタリを出しやすくなりますよ!
底釣りのウキ下調節法
確実に水底を取るには、ウキの浮力を調整することから始めましょう。
下記に「底釣りのウキ下調節法」をまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
ステップ①
オモリを使用して、ウキのトップが6目盛〜8目盛分くらい水面に出ているように調整してください。
針に餌をつけていない状態で行いましょう。
ステップ②
上針に「タナ取りゴム(底取りゴム)」を装着して、ゴム管をずらしながらウキ下を調整してください。
目安としてウキのトップが1目盛分が水面に出るくらいが◎
ちなみに、タナ取りゴム(底取りゴム)には底釣りをする時に使用されて、水深を測ったり、狙った水深で仕掛けを調整すといった役割があります
ステップ③
ウキを道糸にはわせてることで、トンボ(目印となる糸)を道糸に巻きましょう。
トンボと巻く目安として、水面から出ていたトップ1目盛くらいの位置が◎
ステップ④
「タナ取りゴム(底取りゴム)」を取り外しましょう。
その後、ウキの目盛りが水面のどこまで浮いているのか確認してください。
水面に出ているウキの目盛りを道糸にはわせて「ステップ③で決めたトンボ(目印となる糸)の位置」まで引き上げましょう。
※上記の工程を行う際は、トンボ(目印となる糸)の位置を移動させないことがポイントです。
春・夏&秋のタナを覚えておこう
季節ごとにヘラブナの生息している水層を把握しておくと、早めに1匹に辿り着けると思います。
春や夏のヘラブナは、水温が上昇すると浅瀬に移動すりうことが多いです。
高い確率で浅層で活動していることが多いので、ヘラブナ釣りをする際の参考にしていてくださいね。
一般的に、秋のヘラブナは浅い層から中層に移動する傾向にあります。
ここで押さえてもらいたいポイントとして秋の朝晩って気温差が大きいので「ヘラブナの水層(タナ)が日によって頻繁に変化する」ことを知っておいてくださいね。
夏場にヘラブナを効率良く釣りたいなら、水深30cm〜1m前後の浅い水層(タナ)を狙う「カッツケ釣り」からスタートしてみましょう。
春や秋にヘラブナを狙うなら宙釣り(ちゅうつり)で深場の中層を攻めるのが◎
浅い水層にいないヘラブナを効率良く探れるので、ヘラブナとの知恵比べに早めに勝利することができると思います。
【底釣り、カッツケ釣り、宙釣りが活躍するシーンとは?】
底釣り:オールマイティに活躍してくれるので釣り場所を選びません。
カッツケ釣り:比較的にですが、魚の活性が高い時間帯や釣り場所、管理釣り場などで活躍します。
宙釣り:主にドン深(水深が深い釣り場)の管理釣り場やダム湖で活躍することが多いです。
マブナ編:「シモリウキ」を使って細かいアタリを感じ取ろう!アクティブに誘い攻めることが大切!
マブナ釣りのセオリーは「シモリウキ仕掛けで攻める!」ことです。
シモリウキ仕掛けとは小粒の玉ウキ(シモリウキ)を道糸に3個~5個程度セットした仕掛けのことを言い、ウキの浮力が分散させることができます。
シモリウキ仕掛けシステムは「マブナの小さく繊細アタリを逃さずキャッチできる」ことがメリットです。
他にも、エサがゆっくりと落ちることで「絶妙な誘いを加えられる」ことも可能なので、必ずマブナを狙う際に威力を発揮してくれます。
マブナを釣りでは、基本的に水底(底ダナ)を狙うことが多いです。
仕掛けを水中に振り込み着底を確認できたら、仕掛けが馴じむのを待ちます。
しばらく待ちマブナのアタリが無かったら、釣竿を持ち上げて誘いを入れましょう!
誘いは、コンパクトにシモリウキ仕掛けを軽く持ち上げ10cm~20cm程度横に移動させるだけでOK。
マブナは動く餌に興味を示し寄ってくる習性があります。
たとえ10cm~20cm程度と少ない移動距離でも、エサが動くだけでアピール力は絶大なんです.
上記の誘いを繰り返して、マブナが反応する位置を見つけましょう!
誘いを加えてもマブナのアタリがない場合は、釣り場を移動しましょう。
目安として5回~6回誘いを入れたら、次の釣り場に移動と思ってくれてOKです。
初心者さんは「魚が反応しないなら移動!」「魚が反応する場所を見つけるまで移動を繰り返す!」ということを基本として念頭に入れておくといいですね。
「シモリウキ」の浮力を調整しよう
先ほどもお伝えしましたが、マブナを釣りでは水底(底ダナ)を狙うことが多いです。
確実にエサが水底(底ダナ)にあるようにウキ下を調整することが、マブナを釣るために重要となります。
ウキ下を調整の目安として道糸にシモリウキを5個~6個セットしてください。
ウキ同士の間隔は7cm~8cmでOKです。
すべてのウキが、ゆっくりを水中に沈む程度にオモリを重く調整するのがポイント!
ウキの下の長さの目安として、水面にシモリウキが2個~3個ほど浮いていてる程度が理想です。
また、水面に対してシモリウキが斜めに入っていたら◎