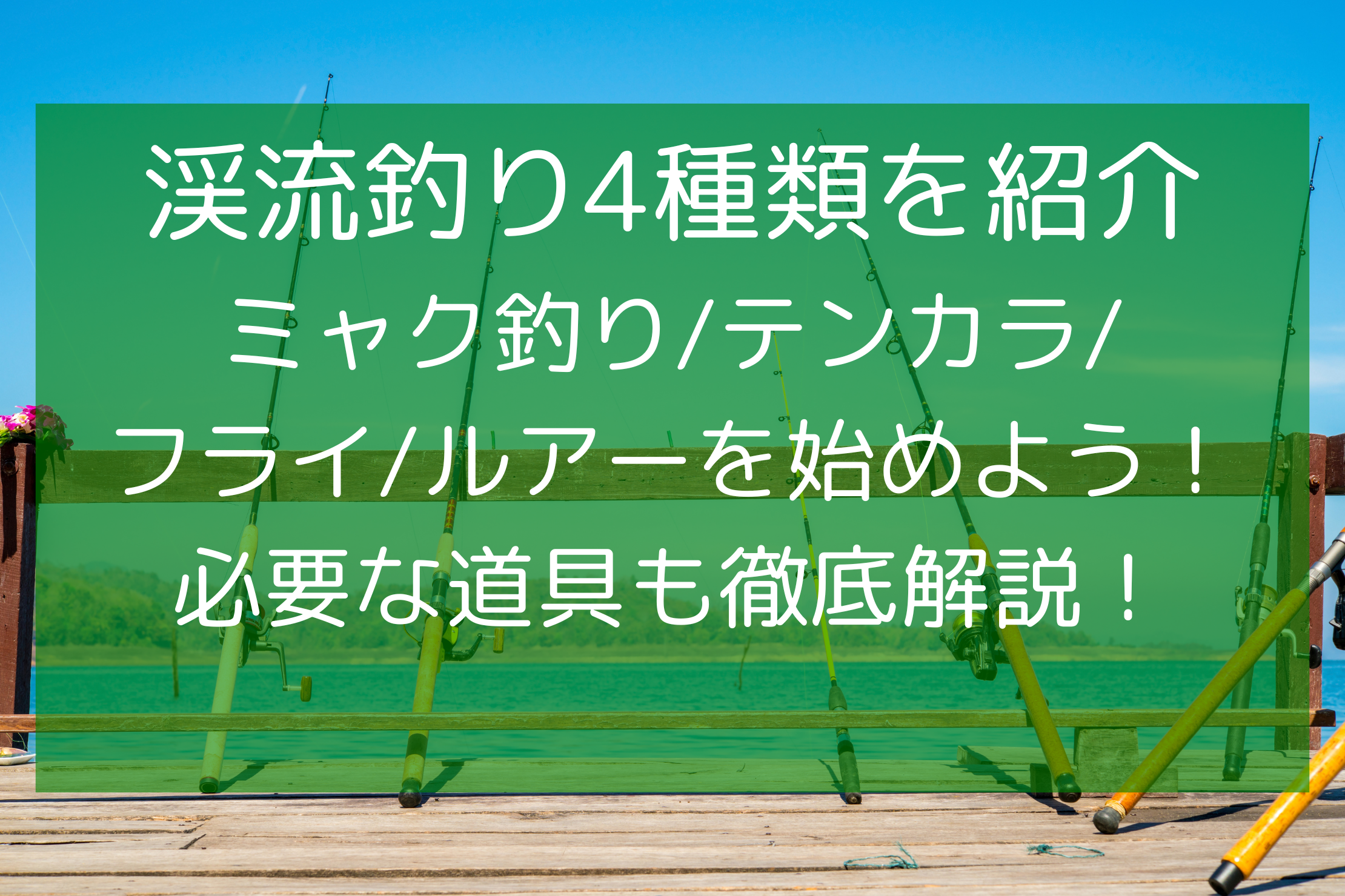Contents
渓流の釣り方「4種類」を解説!
それでは、渓流の釣り方についてご紹介です。
渓流で行われる釣り方には、釣り場となる河川ごとにさまざまなスタイルが継承・発展してきました。
地域ごとに釣れる魚種・川の水流や水量に違いがあるので、個性豊かな釣りスタイルが生まれてきたのですね。
今回の見出しでは「ミャク釣り」「毛鉤(テンカラ、フライフィッシング)」「ルアーフィッシング」といった、ポピュラーな釣法をピックアップいていきます。
近年の主流になる釣り方を厳選していますよ!
あなたが「渓流釣りが気になっている!」「渓流釣りを始めたいけど..どんな釣り方が良いかな?」と考えているなら、ぜひチェックしてみてくださいね。
渓流の釣り方①:ミャク釣り
ミャク釣りとはウキを使わず、竿先の動きや指先に伝わる感覚で魚のアタリを感じ取る釣り方です。
古くからある釣法で、今回の記事でご紹介する釣り方の中で最もシンプルなタックル構成をしています。
使用する釣具として「ミャク竿(手竿を使用する場合もある)「釣り糸(道糸+ハリス)」「釣り針」「オモリ」が挙げられます。
「竿先の動きや変化」「釣り糸の動きや変化」から、渓流魚のアタリを感じ取る必要があるので、釣り人の腕の差が釣果に大きく影響することが特徴的です。
初心者さんにいきなり「ミャク釣りを始めてみては?」とおすすめすることはしませんが、トラブルが少ないのでチェレンジしてもらいたい釣り方だと思います。
ミャク釣りでは多くの釣り方に通じる感覚である「魚のアタリ」を身につけることが可能です。
これから本格的に渓流釣りを始めるなら、1度は経験しておくといいかもしれませんね。
「フライフィッシング」「ルアーフィッシング」「テンカラ釣り」に役立つこと間違いなしです!
ミャク釣りの「釣り方」をご紹介!
ミャク釣りの「釣り方」をご紹介です。
ミャク釣りではエサをコントロールすることが重要。
水流に沿って仕掛けが「渓流魚いそうだな?」と判断できる場所付近を通過するようにコントロールしてくださいね。
渓流魚がエサに食いついたときのアタリ(反応)は「竿先の動きや変化」「釣り糸の動きや変化」で感じ取りましょう。
いつでも渓流魚のアタリ(反応)を感じ取るため、釣り糸は張りすぎても緩め過ぎてもダメです。
釣り糸が「やや張り気味」くらいの状態を維持できたら◎
ミャク釣りの「仕掛け」や「タックル」をご紹介!
ミャク釣りの「仕掛け」にはウキを使用しません。
ウキの代わりに「目印(毛糸やプラスチック片)」を釣り糸にセットすることで、釣り糸の動きを把握していきます。
他に用意する仕掛けとして「軽めのオモリ」「釣り針」と、本当にシンプルな構成をしていますね。
ミャク釣りでは「渓流竿」を使用することもあります。
長さとして4.3m~6.5mくらいが、短めでおすすめです。
基本的に釣竿は「川幅」「周囲の木々の高さ」を考慮して選択しましょう。
「川幅」「周囲の木々の高さ」の状態で、釣竿を振り回せる範囲が決まるので重要ですよ!
源流に向かえば向かうほど釣竿の取り回しが難しいことが多いので、短い釣竿の方が有利に渓流魚を狙うことが可能となります。
ミャク釣りで使用する「餌」をご紹介!
ミャク釣りで使用する「餌」は釣り具で購入することが可能です。
おすすめの餌として「ブドウ虫」「ミミズ」が挙げられるのですが、虫が苦手な方は市販で購入できる「イクラ」でもOK。
また、天然の餌として「川虫」の存在も把握しておくといいですね。
水辺の石の裏に潜んでいる川虫には「ヒラタ」「オニチョロ」「クロカワ虫」「ピンチョロ」などの種類がいます。
とても優秀な渓流釣りのエサなので、ぜひ渓流現地で採取して活用してみましょう!
渓流の釣り方②:テンカラ
テンカラとは、毛鉤を使って「イワナ」「ヤマメ」「アマゴ」など渓流魚を狙う、日本発の釣り方です。
毛鉤を使った釣り方として最も有名で、多くの釣り人を魅了しています。
テンカラの魅力は「シンプルなタックルで始められること」です。
リールを使わないので「釣竿」「釣り糸(道糸+ハリス)」「毛鉤」の3点セットを準備すれば、お手軽にテンカラを始められますよ。
ここからは、テンカラで準備するべき「釣竿」「釣り糸(道糸+ハリス)」「毛鉤」の3点について解説です。
釣竿には、軽量に設計されている「テンカラ専用の釣竿(3.5m~4m程度)」を準備するのがおすすめ。
テンカラって何回もキャストを繰り返して渓流魚を狙うことが多く、軽い釣竿との相性が抜群なんです。
続いて、釣竿と同じ長さの「釣り糸(道糸+ハリス)」を準備し、竿先に結んでください。
最後に、ハリスの先に毛鉤を付けたらタックルの準備完了です。
渓流の釣り方③:フライフィッシング
フライフィッシングは、西洋式の毛針釣りです。
水生昆虫の成虫や幼虫、小魚など様々な形を模したフライ(毛鉤)を使用することが特徴となります。
テンカラは漁法として発展してきた一面がありますが、フライフィッシングにはスポーツ的な要素が強く発展してきました。
世界各地で発展してきた釣法「フライフィッシング」は、今なお格調高い紳士のスポーツとして親しまれています。
フライフィッシングでは「専用のロッド(フライロッド)」「専用の釣り糸(フライライン)」「専用のリール(フライリール)」の3点を組み合わせたタックルを使用します。
日本のフィールドでフライフィッシングを楽しむなら「ロッド番手:4番~6番前後」「長さ:7ft6in(218cm)〜8ft6in(259cm)」のものが使用しやすいサイズ感です。
渓流の釣り方④:ルアーフィッシング
ルアーフィッシングとは、ルアーと呼ばれる擬似餌を屈指して渓流魚(ヤマメ、アマゴ、イワナなど)を対象に狙う釣り方です。
渓流で行うルアーフィッシングでは「スプーン」「スピナー」「ミノー(小型)」の3点を使用することが多いと思います。
初心者さんには「スピナー」がシンプルに巻きやすいのでおすすめです。
また、ロッドワークで操る「ミノー」も楽しすぎるので、興味がある人はチャレンジしてみましょう。
ルアーフィッシングで渓流魚を狙う時のキモとして「水の流れ」「ルアーの動き」の2点を把握することが挙げられます。
水の流れは、渓流魚の行動や潜んでいる場所を理解する鍵ですし、ルアーの動きは渓流魚にアプローチする上で欠かせません。
ここからは、渓流で行うルアーフィッシングで準備するべき「タックル(釣竿、リール、釣り糸)」について解説していきます。
釣竿には短めの「5ft~5.6ftの渓流用ロッド」、リールには小型の「1000番~2000番」のものがおすすめです。
リールに巻く釣り糸には「ナイロンライン(4lb~6lb)「PEライン(0.4号~0.6号)」が、初心者さんでも扱いでしょう!
渓流には木々など障害物が多いので、釣竿を思いっきり振りかぶれないことが多くあります。
短い釣竿を用意しておけば、扱いやすさや操作性の点で有利です。
渓流釣りのざまざまなスタイルについて「初心者」に向いている釣り方は?
「ミャク釣り」「テンカラ」「フライフィッシング」「ルアーフィッシング」について解説してきました。
この見出しでは初心者さんにおすすめしたい「渓流釣り」についてまとめていきます。
「これから渓流釣りを始めたい!」と考えている人は、必見の内容です!
初心者にぴったり!「ルアーフィッシング」がおすすめ
渓流釣り入門として「ルアーフィッシング」から始めるのがおすすめです。
なぜなら、初心者さんでもルアーを管理することは簡単ですし。
他の釣り(海釣りや管理釣り場など)で使用した釣り道具・培ってきた経験を活かすことが可能です。
渓流で行うルアーフィッシングで使用されるルアーとして「ミノー」「スピナー」「スプーン」の3つが代表的です。
これから渓流釣りを始める方は「ミノー」「スピナー」「スプーン」から揃えてみてはどうでしょうか?
おすすめルアータックルをご紹介
渓流で行うルアーフィッシングに向いているタックルをご紹介です。
釣り竿には「スピニングロッド」をおすすめします。
長さは5ft~6ft程度、硬さはMLクラス~ULクラスが◎です。
リールには「1000番台~2000番台スピニングリール」を用意してください。
小さめの番手を用意することで、取り回しが便利になります。
釣り糸(ライン)には「ナイロンライン(4lb~6lb)」を選ぶのがおすすめです。
ちなみに「4lb=0.165mm」「6lb=0.205mm」の太さになります。
少し上級者向け!「フライフィッシング」にチャレンジ!
続いて上級者向けのフライフィッシングについて解説です。
フライフィッシングでは「毛鉤」という疑似餌を使い渓流魚を狙います。
擬似餌を使用する点においてフライフィッシングとルアーフィッシングは似ていますね。
フライフィッシングに使用される「毛鉤」の素材には鳥の羽、獣毛、化学繊維が使用されます。
これらの素材を針に糸で巻き付けて固定することで、水生昆虫や小魚に模した毛鉤を作成するのです。
フライフィッシング最大の特徴として「難易度の高い独特なキャスティング技術」が挙げられます。
フライフィッシング始めたての時は「ロッドの動かし方がわからない!」「正確なループが形成できない!」「ラインの重さをうまく利用できない!」とキャスティング技術に難しさを感じることが多いと思います。
※ループとは、キャスティング時にフライラインがU字型に曲がる部分(ロッドの動きによって生まれる)。
キャスティングのコツを掴むには、反復練習あるのみです。
最初は短いキャスト距離で練習し、徐々にキャスト距離を伸ばすのがおすすめ。
キャスティングが上達していく過程で、フライフィッシングが楽しくなっているはずです。
初心者向けとは言えませんが「人気を誇る釣り方」です
フライフィッシングは初心者さんにはあまりおすすめできません。
あまりおすすめできない理由として「専用の道具が多いこと」「お手軽に始められない(始めるの難しい)こと」「独自性が強いこと」が挙げられます。
ですが、渓流においてフライフィッシングはとても人気の高い釣り方です。
渓流釣りに慣れてきて「新しい釣りを試したい!」「もっと渓流釣りにハマりたい!」と思えるなら、ぜひチェレンジしてもらいたい釣り方になります。
フライフィッシングにチャレンジし始めたら、誰もあなたを渓流釣り初心者さんとは思わないでしょう。
少し上級者向け!「餌釣り(ミャク釣り)」大自然を感じて楽しもう!
渓流で行う餌釣りでは、リールを使用しないことが特徴です。
のべ竿と現地に生息している川虫(カワゲラ、トビケラ、カゲロウなど)を餌にして渓流魚を狙っていきます。
日本で古来から愛され続けてきた渓流釣りの「基本スタイル」と呼べるかもしれませんね。
渓流で餌釣りを行うなら、さまざまな時期に合わせて「自然を観察する」「自然を活用する」ことがとても大事です。
なぜなら、渓流魚が好んで食べる川虫の種類は時期によって異なるからです。
使用する川虫で、渓流魚の食いつきが良くも悪くもなります。
ぜひ、あなたも「釣りをする時期ごとに表情を変える」渓流釣りの醍醐味を味わい尽くしましょう!
「餌釣り(ミャク釣り)」に必要なタックルは?
渓流で餌釣りを始めるなら「ミャク釣りの仕掛け(ウキを使わない)」を使うのが良いでしょう。
懸念点として、初心者さんがいきなり細かい仕掛け作りを学ぶのは大変だと思います。
ということもあり、初心者さんは市販されている「渓流釣り仕掛けセット」を用意してください。
仕掛けセットを選ぶ際のポイントとして、ミャク釣りで使用するのべ竿の長さに近いものを選ぶことです。
ちなみにミャク釣りで使用するのべ竿は「13ft~20ft」くらいだと思ってくれてOK。
初心者さんは、ひとつひとつ丁寧に「ミャク釣りの仕掛け」作りを覚えていきましょう!
少し上級者向け!「テンカラ」日本の伝統的な釣り方を楽しもう!
テンカラは擬似餌で渓流魚を狙う、日本の伝統的な釣り方のひとつです。
使用するタックルが「のべ竿」「釣り糸」「毛鉤」の3点と、非常にシンプルなことが特徴。
難しい仕掛けやオモリなども使用しないので、初心者さんでも始めるのは簡単です。
ですが、毛鉤を投げる(キャスト)には独特な技術が必要なので、魚が定期的に釣れる管理釣り場で練習することをおすすめします。
独特で初心者にはあまり向かない釣り方
テンカラ釣りはあまり初心者さんにおすすめできません。
理由としてフライフィッシング同様に「専用のタックル」「専用の道具(毛鉤など)」を使うので独自性が高い釣り方なんです。
渓流釣りの魅力を堪能できる「テンカラ」は、日本の自然と一緒に育まれてきました。
テンカラ釣りでは、他の釣りでは味わえない渓流の魅力を堪能することが可能です。
ぜひ、初心者さんも渓流の釣りに慣れてきたら挑戦してみましょう!