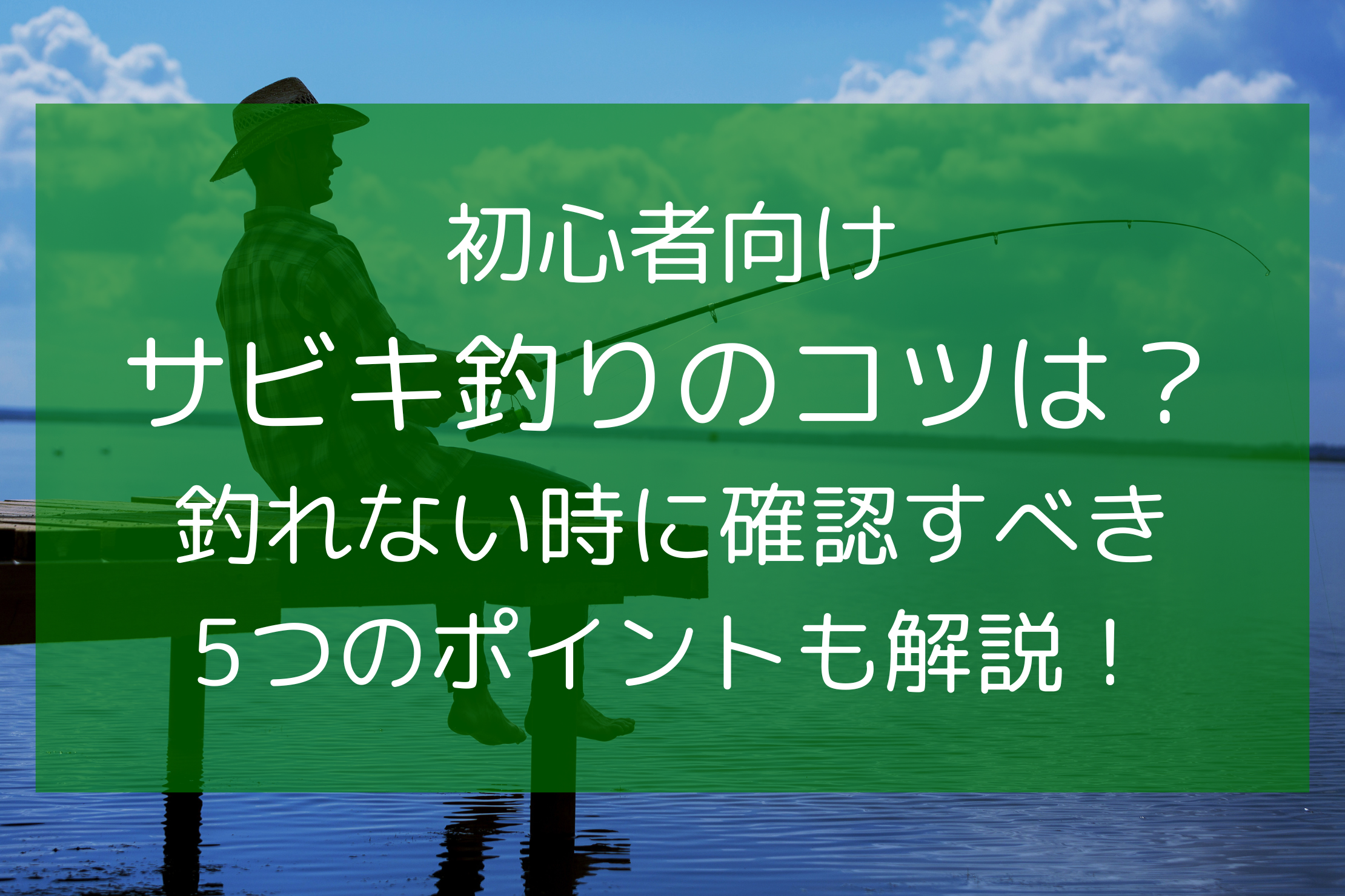サビキ釣りのコツ6選をご紹介!
サビキ釣りのコツ6選をご紹介します。
サビキ釣りって「簡単に魚を釣れる!」「初心者さんにおすすめ!」と言われることが多い釣り方です。
魅力的な情報に誘われ、サビキ釣りを始めてみたものの「思うように釣果が伸びない..」「なかなか魚が釣れない!」といった感じで悩んでいる方も多いと思います。
今回の見出しではサビキ釣りの「コツ」や「テクニック」について解説していくので、ぜひ釣果を伸ばすための参考にしてください。
「サビキ釣りで魚が釣れた!」経験は忘れることができない感動を味わえること間違いなしです。
下記に「サビキ釣りのコツ6選一覧」をまとめたので、まずは全体把握をしてみましょう。
【サビキ釣りのコツ6選一覧】
- 釣り場ごとの釣果情報・回遊情報をチェックする
- タナ(水層)を意識する
- 魚の口のサイズに合わせた釣り針のサイズ(号数)を選ぶ
- 「手返し=チャンス」を意識する
- 魚が釣れてる人(釣り上手さん)のマネをする
- 過度な誘いをやめて置き竿する
上記の「サビキ釣りのコツ6選一覧」を読んでみて、気になるポイントはありましたか?
次回の釣行から活かせそうな情報もありますね!
それでは、サビキ釣りのコツ①として「釣り場ごとの釣果情報・回遊情報をチェックしよう」についてご紹介です。
サビキ釣りのコツ①:釣り場ごとの「釣果情報」「回遊情報」をチェック
サビキ釣りではアジ、イワシ、サバなどの回遊魚をメインに狙うことが多いです。
アジ、イワシ、サバはどれも美味しい魚なので、お目当てにしている人も多いと思います。
いくら回遊魚でも目の前に泳いでなかったら、魚を釣りやすいサビキ釣りでも「釣果」を期待できません。
サビキ仕掛けのついた釣り糸をいくら海に垂らしても魚を釣ることは難しいです。
反対に、目の前の釣り場に回遊魚が泳いでいたらどうでしょう。
初心者さんでも簡単にサビキ釣りで魚を釣ることができそうです。
ぜひ、釣り場に向かう前に「お目当ての魚の回遊情報」を入手してから「釣り場に行く?」「釣り場に行かない?」を判断してみてください。
釣り場に回遊魚がいるなら、必ずサビキ釣りで釣果を伸ばすことが可能です。
魚の回遊情報の入手方法として釣果情報サイトで調べたり、釣具店でスタッフさんに聞き込むのがおすすめです。
「釣果情報サイト」なら信憑性が高いので、安心して釣り場に行くことができると思います。
また地元の釣具店のスタッフさんは、釣り場の状況を把握し尽くしていることが多いです。
ぜひ、釣り場のスタッフさんに目から鱗な情報を教えてもらいましょう!
ちなみに「海釣り公園」でサビキ釣りをするなら、釣り場の公式ホームページをチェックしてみるのもひとつの手です。
回遊魚情報はもちろん、釣果情報も公開していることが多いので、とても参考になりますよ!
基本的には「インターネット」を利用して「回遊魚の情報」を得るのがおすすめですが..。
もしかしたらパソコンなどの機材を扱うことに抵抗がある人もいるかと思います。
パソコンの操作って難しいですよね..。
パソコンなど機材に苦手意識がある方は、釣り場(エリア)付近の釣具店に足を運んでみてください!
「〇〇の港ならサビキ釣りで楽しめるよ!」「今は〇〇が釣れているよ!」と言った感じで、丁寧にあなたの質問に釣具店のスタッフさんが答えてくれるはずです。
大型の釣具店には駐車場があることが多いので車でアクセスすることができることが多いです。
車をお持ちでない方は電車といった移動手段を屈指して釣具店に向かいましょう!
サビキ釣りのコツ②:「タナ(水層)」を意識してみよう
タナ(水層)とは、魚が泳ぎ活動している水深を指す言葉です。
サビキ釣りで釣果を出すなら、必ず押さえてもらいたい釣り知識になります。
あなたが狙うターゲットが泳ぎ活動している「タナ(水層)」にサビキ仕掛けの長さを調整することを「タナ(水層)を取る」と言います。
初心者さんは狙う魚種ごとに泳ぎ活動している「タナ(水層)」が異なることを押さえておきましょう。
サビキ釣りで人気の高いターゲットであるイワシ、サバ、アジを例に挙げて活動している「タナ(水層)」の違いについてみていきます。
イワシや小サバは表層から中層といった、水面付近を回遊していることが多いです。
またアジは中層から低層を好む傾向があり、海底付近を狙うと釣れる確率が高くなりますよ。
あなたが釣りたい魚が「どのタナ(水層)を泳いでいるか?」を常に意識することが、サビキ釣りのコツと言えますね。
釣りをする場所に「魚が入れる」「回遊魚が回ってこれる」水深があるか把握しよう
釣り場に着いたら「魚が入れる水深があるかな?」「回遊魚が回ってこれる水深があるかな?」と確認しましょう。
水深が深い場所・水深が浅い場所では、釣れる魚種やサイズが異なるんです。
ある程度釣り場の水深を把握しておくと、サビキ釣りの戦略を立てる時に役立ちますよ!
十分な水深のある釣り場として「堤防」や「湾内」が挙げられます。
堤防や湾内って漁船やボートなどが航行することが多く、水深が十分にある構造をしていることが多いんです。
水深がある釣り場には、さまざまな魚が住処にしている(生息している)可能性が考えられるので、サビキ釣りをするのに最適!
回遊魚も水深がある場所なら入りやすいので、よく回遊してきてくれます。
水深が浅すぎる場所には回遊魚が入れない可能性が高く、サビキ釣りをするのに不向きです。
回遊魚の入ってきやすい釣り場を見つけることも「サビキ釣りのコツ」なので、初心者さんは押さえておきましょう。
タナ(水層)の取り方は?
まず「サビキカゴ」8分目程度くらいまでのコマセを入れましょう。
サビキカゴにコマセを入れたら、サビキ仕掛けを水底(ボトム)まで沈めます。
この時「サビキ仕掛けは丁寧にゆっくり海に沈める!」ことを初心者さんは念頭に入れておくと◎です。
サビキカゴからエサが飛び出さすアクシデントを避けることができると思います。
サビキカゴにコマセが多く残ると、魚に対したくさんアピールできるので「釣果」に繋がるんです!
水底(ボトム)にサビキ仕掛けが着いたら、糸ふけを回収し釣竿を大きく上に向かって「しゃくる」ことで魚を誘っていきます。
魚を誘っていて「反応(アタリ)がないな〜」と感じたら1m程度サビキ仕掛けを巻き上げてください。
その後、あらためて釣竿をしゃくって魚にアピールをして誘っていきます。
しゃくりを行った後は数分間「じ〜っと」魚の反応(アタリ)を待つのも効果的。
魚がコマセを食べ尽くした後に、擬似エサに興味を示してくれることもありますよ。
※水底(ボトム)にサビキ仕掛けが着いたことを確認する方法を2通りまとめました。
初心者さんは、ぜひ参考にしてみて下さいね。
「釣り糸動き」「ウキの動き」に注目するとサビキ仕掛けが着いたことを判断することができます。
具体的には「釣り糸=たるむ」「ウキ=水面から沈む」タイミングが、水底(ボトム)にサビキ仕掛けが着いた瞬間になります。
サビキ仕掛けを2連にしてみよう
サビキ仕掛けを2つ繋ぎ「タナ(水層)を探る」方法もあります。
サビキ仕掛けを2つ繋ぐので、単純に2倍の深さの水深を探ることが可能です。
2連のサビキ仕掛けを使用することで、魚が掛かった釣り針の位置から「狙うタナ(水層)の目処」を立てることができますよ。
短いサビキ仕掛けで少しずつ徐々にタナ(水層)を探る必要がないので、スピーディーに効率よく「サビキ釣り」を楽しみたい方におすすめです。
仕掛け自体がかなり長くなるので初心者さんは「ライントラブル」に注意しましょう。
釣り針と釣り糸が絡む「ライントラブル」が起こり安いんです。
2連のサビキ仕掛けを使用するなら、磯竿など「長い釣竿」を使用するのが、初心者さんにおすすめ。
長い釣竿なら2連のサビキ仕掛けでも、比較的簡単に扱うことができると思います。
サビキ釣りのコツ③:魚の口のサイズに合わせた「釣り針のサイズ(号数)」を選ぼう
魚の口の大きさは「魚種」によって異なります。
サビキ釣りのターゲットにも同じことが言えてるので、釣り知識として押さえましょう。
小型魚の口は小さく(アジやイワシなど)、中型魚や大型魚(サバやメジナなど)の口は大きいと押さえておくと◎
サビキ釣りをしていて「釣れないな」と感じた時は、「サビキ針のサイズが魚の口のサイズに合っていないのか?」と疑問を持てると良いですね。
サビキ針のサイズ大きすぎたり、小さすぎることが原因で釣果が出ていないのかもしれませんよ。
それでは、サビキ釣りに使用する「サビキ針のサイズ(号数)」を確認していきましょう。
一般的に、豆アジ(全長5cm〜15cm程度)やイワシなど小さい魚を狙うなら「3号以下」、小アジ(全長10cm以上〜20cm未満)を狙う場合は4号~5号がおすすめ。
サバやメジナなど中型魚を狙う際は「6号以上」のサビキ針を準備しましょう。
サビキ釣りで釣果を伸ばしたい人は「豆アジ用=1号サビキ針」「小アジ用=4号サビキ針」を複数用意しておくと良いですね。
複数枚のサビキ針を用意しておくと、さまざまな状況に対応することが可能になります。
魚が釣れていない状態を打開できるかもしれません。
周囲の釣り人に「おすすめのサビキ針は?」と質問をして、釣果に繋がるような情報を入手することも大切なスキルです。
有益な情報から、釣行日の魚に最適な釣り針にたどり着くことできるかもしれません。
ぜひ、魚の口のサイズに合っているサビキ針を使用して「釣果」を伸ばしましょう!
サビキ釣りのコツ④:「手返し=チャンス」を意識してみよう
サビキ釣りで釣果を出すには「手返し」意識することも重要です。
手返しとは「海に投げ入れた仕掛けを回収→再び仕掛けをセットして海に投入」する動作のことを言います。
ちなみにサビキ仕掛けを回収するタイミングは「魚がヒットした」「サビキカゴにエサが無い」「魚の反応(アタリ)が無い」ときに行うのが基本です。
サビキ釣りは1匹釣れると、2匹3匹と釣れ続くことが多い釣り方です。
1匹魚が釣れて喜こぶのも良いのですが、次の一手で2匹目が釣れる「チャンス」を逃してしまうかもしれません。
目の前に回遊魚が泳いでいる時間を大切にしてくださいね。
この記事を読んでいる方は「仕掛けを海に投げ入れた回数=チャンスの数」と考えてくれてOKです。
回遊魚は1匹釣れ始めると、釣れ続ける傾向があります。
サビキ釣りで釣果を伸ばす絶好のチャンスなので、ぜひ「手返し」を意識して効率的に魚を釣り上げましょう!
初心者さんは、新しいサビキ仕掛けの準備に手こずることもあると思います。
そんな時に「回遊魚が逃げてしまう!」と焦らなくて大丈夫です!
コマセを海に撒くことで、コマセが食い尽くされるまでの少しの間なら回遊魚の群れを引き止めることが可能です。
回遊魚の群れが引き止められている間に、落ち着いてサビキ仕掛けを準備してくださいね。
コマセを屈指して回遊魚の群れを引き止めている間の「手返し」は丁寧に行うと◎です。
魚がヒットしたら、まずは丁寧に引き上げる。
その後、丁寧に魚から釣り針を外して、クーラーボックスに入れて保存する。
魚がクーラーボックスに保存できたらサビキカゴにコマセを詰め、サビキ仕掛けの準備完了です。
あとは「サビキ仕掛け」を再び海に投げ入れて魚を狙いましょう。
サビキ釣りのコツ⑤:魚が釣れてる人(釣り上手さん)の「マネ」をしてみよう
サビキ釣りのコツとして「魚が釣れてる人(釣り上手さん)のマネ」をしてみましょう。
釣り場についたら周りを観察してみて「魚をよく釣れている人」を見つけてください。
ポイントとして「釣り場選び」「使用する仕掛け」の2点をマネするのがおすすめです。
釣れている人が「〇〇がある場所でサビキ釣りをしている!」「〇〇のような場所だと魚が釣れるのかな?」といった感じで、よ〜く観察することがサビキ釣り上達の1歩目です。
また釣れている人が「どのような仕掛けを使用しているのか?」「仕掛けを使用して攻めている水層(タナ)は?」といったことにも注目しましょう。
サビキ釣り始めたての頃は、釣れている人と自分自身の違いがわからないかもしれません。
違いがわからない時は釣れている人に「積極的にコミュニケーション」を取りに行くのがおすすめ。
緊張するかもしれませんが「釣り知識」を質問されて嫌がる釣り人さんは少ないです。
サビキ釣りもそうですが、釣り全般において「有益な情報」は釣果に直結するので大変貴重です。
少しでも「魚が釣れない!」「力不足かも!」と思ったら、釣れている人から「有益な情報」を仕入れましょう!
魚が釣れていない状況を打開できるかもしれません。
サビキ釣りのコツ⑥:「過度な誘い」をやめて「置き竿」をしてみよう
サビキ釣りでは過度な誘いを避け、自然に誘うことが効果的なこともあります。
「誘いを入れても魚の反応が無い!」と感じた時は、置き竿をしてみるのも1つの手です。
置き竿とは、仕掛けを海に投げ入れてから釣竿を竿掛けなどに置き、魚の当たりを待つ釣り方のことを言います。
仕掛けを潮の流れに任せて放置してみると、魚に違和感を与えずに誘えるんです。
魚が釣れない時間帯って、ついつい魚を誘いたくなってしまいますよね。
逆効果だとわかっていても肩に力が入ったり、気持ちが空回りして、釣竿をあおり(上下に動かして)誘いを入れがちです。
急に激しく動き出す「サビキ仕掛け」に魚は驚くことを知識として押さえましょう。
驚いた魚は遠くに逃げてしまうので、注意してくださいね。
これは余談ですが、置き竿をして仕掛けを放置している時は「ルアー釣りを楽しむ」「ラジオ放送を聴く」「youtubeを見る」「スマホをいじる」ことで時間を潰すのがおすすめです。
何気ない時間ですが「魚が釣れなかったらどうしよう..」といった不安感から解放されるかもしれません。
せっかく楽しい「サビキ釣り」に来たのですから、リラックスして心に余裕を持って楽しみましょう!
サビキ釣りで「魚が釣れない!」ときのコツ5選
ここからは、サビキ釣りをしていて「全然釣れない!」「魚がいないかも!」と魚が釣れていない時のコツやテクニックについてご紹介です。
なかなか魚が釣れないと不安な気持ちになりますよね。
初心者さんなら尚更、気持ちに余裕が持てなくなると思います。
この見出しを読むことで「サビキ釣りで魚が釣れない!」といった状況を打開することができるかもしれません。
釣り知識として押さえることで、次回の釣行時に役立ててくださいね。
下記にこれから紹介する「サビキ釣りで魚が釣れないときのコツ5選」をまとめたので、まずは全体把握からしてみましょう!
【サビキ釣りで魚が釣れないときのコツ5選】
- タナ(魚が泳いでいる水層)をできるだけ早く見つけること
- 追い食いを狙って釣果数を稼ぐこと
- 魚の口に合った釣り針(号数)を選ぶこと
- 最適なスキンカラーを選ぶこと
- 足元に魚が寄らないときは沖を狙うこと
上記の「サビキ釣りで魚が釣れないときのコツ5選」読んでみてシブい状況(魚が釣れない)を打開するコツは見つかりましたか?
あなたが少しでも「安心してサビキ釣りを楽しめる」「今回はサビキ釣りで魚が釣れそう!」と思えたら幸いです。
それでは早速サビキ釣りで魚が釣れないときのコツ①として「タナ(魚が泳いでいる水層)をできるだけ早く見つけよう」を解説していきます!
サビキ釣りで魚が釣れないときのコツ①:「タナ(魚が泳いでいる水層)」をできるだけ早く見つけよう
サビキ釣りで魚が釣れない時は「タナ(魚が泳いでいる水層)」をできるだけ早く見つけましょう。
「タナ」は魚が群れて泳いでいる水深のことを指していて、魚を釣るためにとても重要。
いくら魚好みのエサや口のサイズに合った釣り針を使用していても、海に魚がいなかったら「釣果を期待する」ことは難しいです。
釣り全般で言えことなので、サビキ釣り以外にも興味がある人は、必ず知識として把握しておきましょう。
それでは、魚が泳いでいるタナの見つけ方を解説していきます。
タナの見つけ方はあまり難しく考えなくてOKです。
「上層⇄中層⇄低層」を順番にひとつずつ探ることがコツ!
上記のコツを押さえておくと簡単にタナを見つけることできますよ。
具体的には、海底(ボトム)付近で魚の反応(アタリ)がないなら「低層(海底付近)→中層(水面と海底の間の水層)」を探ってから「上層」まで魚の居場所を見つけましょう。
表層(水面付近)に魚の反応(アタリ)がない時は「上層」を探り「中層(水面と海底の間の水層)→低層(海底付近)」に魚がいないか調査するのがおすすめ。
ちなみにサビキ釣りでターゲットになるイワシやサバは「上層付近」といった浅いタナを泳いでいることが多いです。
アジは「低層」「中層」など海底付近にいるケースがあるので、サビキ釣りをする際の参考にしてみてください。
釣り場環境(潮目、天気、風など)や魚の状況(活性は高い?低い?など)によって、魚が泳いでいる「タナ(水層)」は変化します。
魚が釣れない時間が続くようなら「タナが変わったのかな?」と疑えるようにしておくと◎です。
これだけでも魚が釣れる可能性がぐ〜んと高まりますよ。
サビキ釣りで魚が釣れないときのコツ②:「追い食い」を狙って釣果数を稼ごう
サビキ釣りで魚が釣れないときは「追い食い」を狙うのもコツです。
追い食いとは、複数の釣り針がついたサビキ仕掛けを使うことで魚を狙うことを言います。
具体的には、魚が1匹掛かってもすぐに仕掛けを回収せず、他の釣り針に複数の魚が掛かるまで待つテクニックです。
小型回遊魚(アジ、イワシ、サバなど)は群を成して水中を移動します。
サビキ釣りって1匹目の回遊魚が釣り針に掛かり暴れることで、2匹目、3匹目が後を追うようにヒットすることが多いんです。
これは1匹目の魚や仕掛けの動きが、サビキ仕掛けの周りにいる他の魚を刺激することで起こる現象になります。
この現象を上手に活用するテクニックが「追い食い」と呼ばれていて、サビキ釣りで魚が釣れない時の打開策!
「追い食い」をする際、初心者さんに注意してもらいたことがあります。
それは複数の釣り針が付いたサビキ仕掛けを使用するので、釣り糸と釣り針が絡まってしまう「ライントラブル」が多発することです。
初心者さんだけで「ライントラブル」を解消するには、かなりの時間と労力を使用してしまうかもしれません。
これからサビキ釣りを始める初心者さんは、ぜひ3本〜5本くらいの釣り針が付いている「サビキ仕掛け」を使用することをおすすめします。
サビキ釣りで魚が釣れないときのコツ③:魚の口に合った釣り針(号数)を選ぼう
サビキ釣りで魚が釣れないときは「魚の口のサイズに合わせた釣り針(号数)を選ぶ」こともコツになります。
魚の口のサイズに釣り針の号数がマッチしない場合「掛かりにくい」「ばらしやすい(外れやすい)」「伸びやすい」「食いつかない」といったアクシデントが起こりやすいです。
少し難しいかもしれませんが、初心者さんは魚がヒットしても逃げてしまったり、釣れない時間が続いた際に「釣り針の号数が違うかも!」「号数を変えてみよう!」といった考えができると◎
魚の口のサイズに対して最適な釣り針の号数を選択できたら、バラシを回避することができ「貴重な1匹」をゲットすることに繋がること間違いなしです。
「魚をバラして(逃して)しまった..」と落ち込まずに済むので、気分が暗くなる心配も少なくなります!
効率良く釣果を稼いでいきましょう。
【アジのサイズ・釣り針の号数】
12cm前後までの小型:3号〜4号
15cm前後の中型:5号〜7号
20cm前後の良型:6号〜8号
25cm以上の大型:8号〜10号
サビキ釣りで魚が釣れないときのコツ④:最適なスキンカラーを選ぼう
サビキの素材は「スキン」「サバ皮」「ハゲ皮」の3種類と複数に分けることが可能です。
主に合成ゴムで作られていて、魚の皮を模した形状や色をしてます。
小魚(アジやイワシなど)を真似たの動き方をするので、魚が興味を示してくれますよ!
サビキ釣りでは「サビキのスキンカラー」が釣果を左右するくらい大切です。
サビキのスキンカラーは主に「ピンク」「白」「グリーン」などが代表的。
魚の状況や海の水質に応じた最適なスキンカラーを選びましょう!
ここからは、サビキのスキンカラーを選ぶときのポイントを見ていきます。
海水が澄んでいるときは「白色」や「青色」のスキンが自然な動きを演出してくれるので、魚が違和感を感じにくくなります。
反対に海水が濁っていたり、曇りの日などは「ピンク」や「ラメ入り」といったスキンが水中で目立つので、効果的に魚を釣ることが可能です。
ほかにも潮の流れが速い場所・水深が深い場所なら「ケイムラ」スキンが、夜にサビキ釣りを楽しむなら「夜光」スキンが魚を引き寄せてくれます!
サビキ釣りで魚が釣れないときのコツ⑤:足元に魚が寄らないときは「沖」を狙おう
最後のコツは初心者さんにとって、少し難しいかもしれません。
サビキ釣りに「ある程度慣れてきた!」と感じたら、ぜひチャレンジしてもらいたいコツになります。
足元にいる魚をターゲットにサビキ釣りをしていて「釣れないな〜」と感じることもあるでしょう。
「タナ」「追い食い」「釣り針(号数)」「サビキのスキンカラー」など、いろいろなコツを試しても釣れないかもしれません。
そんな時は、足元の魚から沖にいる魚にターゲットを変更するのがおすすめです。
具体的なコツとしてサビキ仕掛けを沖に投げてみましょう。
それではサビキ仕掛けで沖を狙う際のポイントをご紹介していきます。
沖にいる魚を狙う時はサビキ仕掛けにウキを付けてください。
闇雲に沖を狙うのではなく「敷石の沖側」「魚が跳ねている」「潮がヨレがある」「潮目」といった、何か変化のあるポイントを中心に探ると◎です。
広大な海に潜む魚を効率よく探ることが可能となります。
初心者さんでも「魚は水流や地形に変化のあるポイントを好む傾向がある!」ことを押さえるだけで魚に出会える可能性が高まりますよ。
サビキ仕掛けで沖を狙う時のコツは?
サビキ仕掛けで沖を狙う時は、サビキカゴにしっかりと「アミエビ」を詰めてください。
この工程は足元にいる魚を「サビキ仕掛け」で釣るときと同様です。
「アミエビ」を詰めたら、狙いたいポイントを定め、沖に向かいサビキ仕掛けを投入しましょう。
サビキ仕掛けが着水したらウキの位置を確認して、「狙っていた場所」と「着水した場所」がどれくらい離れているかを把握します。
「狙っていた場所」と「着水した場所」の距離が離れていたら、必要に応じてリールを巻き、仕掛けの位置を調整してくださいね。
サビキ仕掛けを狙いたい場所に調整できたら、釣竿を大きく上下に動かす(あおる)ことで、サビキカゴからアミエビを放出しましょう。
海中に放出されたアミエビが近くにいる魚にアピールしてくれますよ!
初心者さんは、サビキ仕掛けとウキ止め(ウキが沈む深さを調整するパーツ)までの長さを短くするのがおすすめ。
なぜなら、低層(浅いタナ)から丁寧に探ることで「今どの水層を探っているのかな?」といった迷走状態を回避できるからです。
低層(浅いタナ)で「魚の反応(アタリ)がない」と感じてから、サビキ仕掛けとウキ止めの距離を離していくと◎
少しずつウキ止めの位置を上にズラすことで、サビキ仕掛けが沈む水層(タナ)を深く調整することができますよ。
ちなにみサビキ仕掛けで沖の魚を狙う際は、魚の反応(アタリ)はウキの動きで判断してください。
ウキが「水中に沈む」「水中を変に移動」したら魚がヒットしている可能性が高いです。
最後になりますが、魚が釣り針に掛かったら釣竿を立てることがポイント。
釣竿を立てることでラインテンションが弛まず、魚を逃す(バラす)可能性が減ります。
あとは集中してリールハンドルを一定スピードで巻き、魚を取り込めばバッチリです。