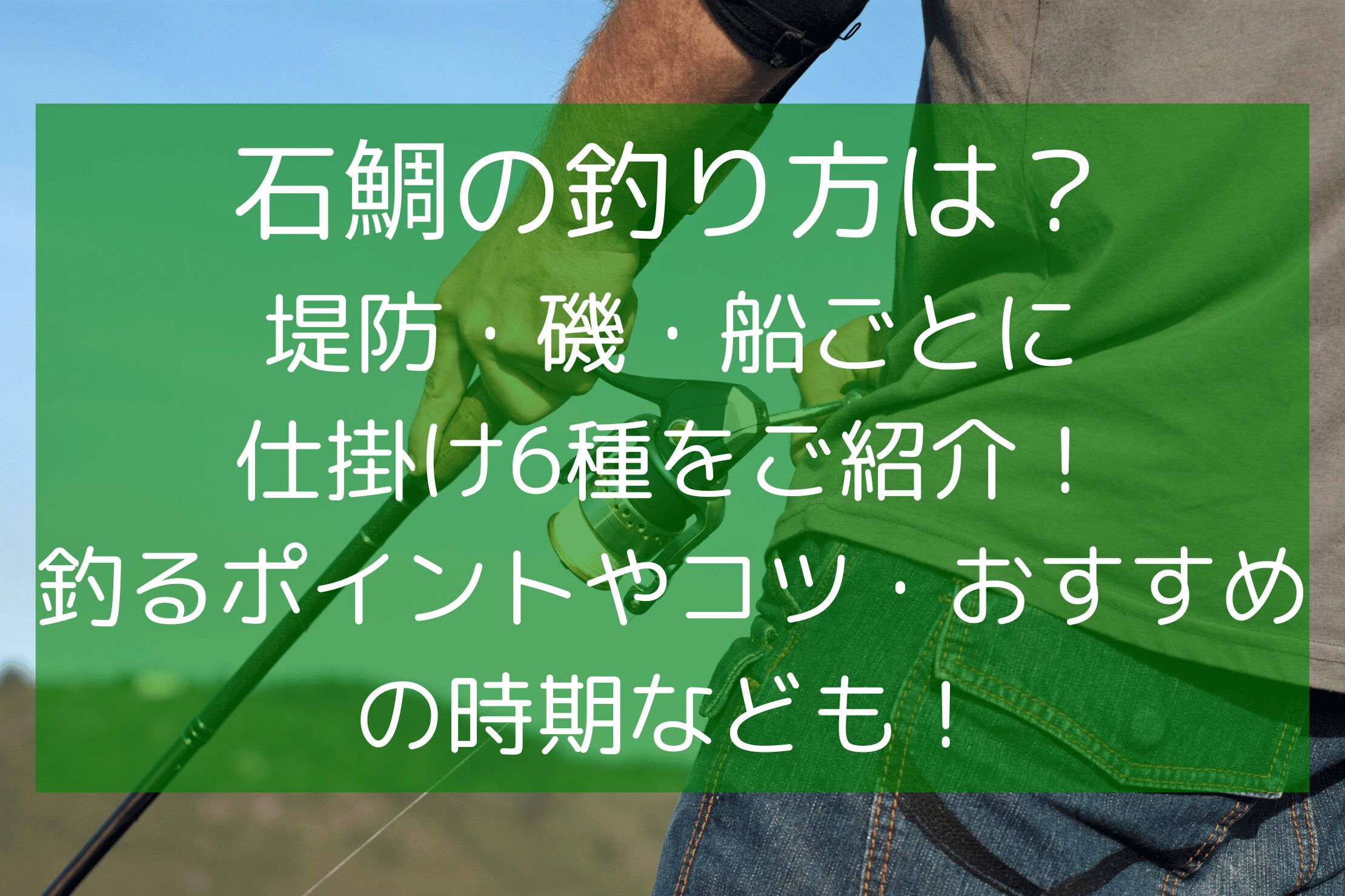Contents
石鯛はどのような魚?
意外と知られていない、石鯛の「特徴」「生態系」についてまとめていきます。
石鯛釣りにチャレンジする前に、相手を知ることから始めましょう!
石鯛は意外と身近で釣れる!
50cm以上の巨大魚になる場合も!
石鯛は身近な海で釣れる魚で、日本各地で人気がある釣魚です。
生息域も広く「太平洋」「オホーツク海」「日本海」どこでも釣れますよ!
確かに石鯛はいろいろな場所で釣れるのですが..。
実は、石鯛の特徴を掴み、石鯛が好む釣り方をしないと釣り上げるのが難しい魚になります。
今回の記事では、そんな石鯛に特化した「釣り方」「テクニック」をご紹介していくので、石鯛釣りに興味のある人はチェックしてください!
なかには「石鯛とはどんな魚?」と気になる人もいるでしょう。
石鯛の大きな特徴として銀と黒が織りなす「縦縞模様(たてじまもよう)」があります。
シルエットは、釣り人に大人気「真鯛」と似ているのでイメージしやすいですね♪
余談ですが「石鯛」「真鯛」には、共通して「鯛」という漢字が使われています。
認知されていませんが「石鯛≠鯛の仲間」なので注意しましょう!笑
石鯛はイシダイ科という独自グループに属するので、知識として押さえておくと◎
成魚になると「大きさ=50cm程度」まで育ちます!
稀にですが、なんと70cm超えの大型個体も存在しているので、いち釣り人としては「釣り上げたい魚」でしょう。
パワフルな石鯛は「磯の王者」と呼ばれている!
石鯛は「磯の王者」と称されています。
これは、石鯛が「パワフルな引き」「体高が高い」ことが理由です。
特に「パワフルな引き」が、多くの釣り人を魅了しているのでしょう。
ヒットした瞬間「ジジジ」というドラグ音が、釣り場に鳴り響く快感はたまりません。
個体にもよりますが、大物の石鯛がヒットした時の「引味は非常に強烈」です。
成人男性アングラーでも、よろめく可能性があるので油断は禁物!
昔から石鯛釣りは関西を中心に高い人気を誇ってきました。
和歌山ではメジャーな釣魚なんですよ♪
歴代のアングラーが研究・思考して生み出してきた「釣り方」「エサ」は無数に存在しています。
石鯛の「捕食の仕方」や「特徴」を解説!
石鯛の「食性」についてまとめていきます。
なんと石鯛は「硬い殻を持つ生き物(甲殻類・貝類・ウニなど)」ばかりを好んで捕食するんです。
主な餌のほとんどが「硬い殻を持つ」ため、石鯛の顎や歯は特別な進化を果たします。
顎と歯が融合して「クチバシ状」になっているのです。
他の魚では、なかなか見れない口元をしているので、初見の人は驚くこと間違いなし。
そんな頑丈な歯を屈指して、硬い殻を噛み砕くので、釣り糸や釣り方を工夫しないと「ラインブレイク」が多発するので注意ですよ!
話が逸れましたが、石鯛が釣れた際には「顎」「歯」を観察してみてください。
磯の王者たる所以が垣間見れるでしょう。
石鯛釣りで使う「仕掛け」について
石鯛は「磯の王者」と呼ばれるので「磯釣りでしか釣れない魚」と認知されることが多いそう。
私も「石鯛=磯で狙う魚」とイメージしていたので、気持ちはめちゃめちゃわかります!笑
ここで押さえたいのが、石鯛は「磯」「堤防」「船」など、さまざまな釣り場で狙える好ターゲットということ。
また、上記3種類の釣り場(磯・堤防・船)ごとに「仕掛け」「釣り方」が異なることも把握しておくと◎です。
同じターゲットを狙っていても、釣り場が違うだけで「楽しみ方が変わる」ことも釣りの醍醐味でしょう。
磯で石鯛を狙うなら「1匹の石鯛に馳せる」ようなロマン溢れる楽しみ方ができます。
船釣りなら「大量釣果を狙える」ので、帰宅時にクーラーボックスが満タンになってしまうかも!笑
個人的には、安全性が高く「ファミリーフィッシング」を楽しめる、堤防で石鯛を狙うのがおすすめです♪
今回の記事では「磯」「堤防」「船」それぞれの釣り場で、基本になる仕掛けをまとめていきます。
石鯛釣りを始める前にチェックしてください!
磯で使うべき「石鯛釣りの仕掛け(石鯛仕掛け)」とは?
それでは、磯で石鯛を狙う時に必要となる「タックル」「仕掛け」をご紹介です。
石鯛を磯で狙うなら大きく分けて、2通りの仕掛けを把握しておくと◎
具体的には「捨てオモリ仕掛け」「宙釣り仕掛け」になるので、頭の片隅に入れておくと良いかと。
「捨てオモリ仕掛け」「宙釣り仕掛け」ともに、石鯛専用の仕掛けになります。
極太の道糸やワイヤーを用いていて、磯の王者である石鯛の「強烈な引き」にも負けない強度を誇りますよ!
石鯛は、グレに並び「磯釣りで代表的なターゲット」です。
余談ですが、磯で石鯛を狙う釣りを「THE・石鯛釣り」と呼称することもあるくらい!
そんな石鯛が磯でヒットしたら、釣竿が海面を突き刺すが如く曲がります。
穂先が折れないか心配になるくらいです。笑
唯一無二の「パワー」「強烈な引き」を味わえる石鯛とのファイトが、多くの釣り人を魅了する理由でしょう。
あなたも磯釣りでしか味わえない「力と力の真っ向勝負」を体験してみませんか?
磯向け|石鯛釣りで使用する「釣竿(ロッド)」は?
それでは、磯で石鯛を狙う際に必要な「ロッド」をご紹介です。
結論から言いますと、石鯛の強烈な引きに耐えられる「パワフルロッド」を選ぶのがおすすめ。
難しく考えず「専用ロッド」を購入するのが良いかと!
「ダイワ」「シマノ」など、多くの釣具メーカーが開発しているので、あなた好みの1本を選んでくださいね♪
個人的に「5m〜5.4m」くらいの専用ロッドを選べたら、問題なく磯で石鯛を狙えると思います。
あなたの身長に合った釣竿を見つけてくださいね!
磯向け|石鯛釣りで使用する「リール」は?
続いて、磯で石鯛を狙う際に必要な「リール」をご紹介です。
磯で石鯛を狙うなら「大型両軸リール(ベイトリール)」も必須になります。
かなり太い釣り糸(20号クラス)を200m以上、巻けるリールなら文句の付けようがございません。
もしかしたら「どの大型両軸リール(ベイトリール)を選べば良いの?」と悩んでいる人もいるでしょう。
迷ったら、ロッドと同様「釣具メーカー(ダイワ・シマノなど)」が販売している「石鯛釣り専用リール」を購入するのがおすすめ!
馬力や糸巻き量ともに、安心して使用できるでしょう。
磯向け|石鯛釣りで使用する「ライン」「フック」は?
続いて、磯で石鯛を狙う際に必要な「ライン」「フック」をご紹介です。
石鯛のパワーに負けない強度を誇る「ライン」を選ぶことは、とても重要。
油断していると、すぐ「ラインブレイク」するので注意しましょう!
道糸にナイロンラインを使うなら「20号前後」PEラインを使うなら「15号前後」を選ぶのがおすすめ。
どちらも、かなり強力なので「石鯛のパワー」にも負けません。
またリーダーに「ワイヤー(37号〜38号)」を使用することで、石鯛の鋭い歯による「ラインブレイク」を回避してください。
石鯛の強固な顎を貫通させられる「フック(釣り針)」を選ぶのも重要。
石鯛釣りでは「穴あき針」を使用します。
穴あき針には「10号〜18号」とさまざまな大きさがありますが、慣れるまでは「15号前後」が使いやすくておすすめです。
個人的には「セット仕掛け」を購入しておけば、間違いないと思います。
セット仕掛けとは「ワイヤー」「フック(釣り針)」が一緒になって販売されている商品です。
1度購入するだけで、磯釣りに必要なアイテムが揃うので、初心者さんも嬉しいかと♪
石鯛釣りの仕掛け(石鯛仕掛け)①:捨てオモリ仕掛け
石鯛仕掛け①として「捨てオモリ仕掛け」をご紹介です。
関東や関西方面で幅広く使われている仕掛けなので、知識として押さえましょう!
一般的に「置き竿」という釣法で石鯛を狙います。
捨てオモリ仕掛け、最大の特徴は「根掛かりから脱出できる」ことでしょう。
根掛かりが起こった際に、オモリだけを切り離せるので「仕掛け全体がロストする」可能性が低いのです。
沖目にいる石鯛を狙いたい時に「遠投」できることも魅力です。
「根掛かりリスクが低い」「遠投できる」というメリットを屈指して、普段なら臆してしまいそうなポイント(荒れた海底や潮流が速いなど)を攻めちゃいましょう!
今まで釣れなかった石鯛に巡り会えるかもしれません。
捨てオモリ仕掛けは構造上「魚のアタリ(反応)」がオモリを介さず、竿先や手元にダイレクトに伝わります。
いきなり「ドン」と鮮明なアタリが竿先や手元に現れるので、慣れるまで「早アワセ」に注意すると◎
早アワセをしてしまうと、石鯛の口に釣り針を貫通させられません。
竿先にアタリが現れたら「しっかり食い込ませる!」ことを意識してください。
最初の頃は「ラインブレイクが怖い..」と感じますが、ワイヤーハリスを使用すれば問題なし!
基本的に、飲み込まれても「釣り糸が切れる」心配はありません。
石鯛の口の中に釣り針が食い込んだら、釣竿を立てて確実にフッキングしてくださいね♪
エサには「ヤドカリ」「サザエ」「ガンガゼ」などを使用すると◎
また、エサのサイズ感に合わせて「釣り針の号数(大きさ)」を選ぶと良いですよ!
石鯛釣りの仕掛け(石鯛仕掛け)②:宙釣り仕掛け
石鯛仕掛け②として「宙釣り仕掛け」をご紹介です。
こちらは九州方面で使用されている仕掛けになります。
一般的には「手持ち」という釣法で石鯛を狙いますよ!
宙釣り仕掛け、最大のメリットは「磯際を丁寧に探れる」ことです。
これは「中通し式オモリ」を使うので、できる芸等。
磯の壁際や海底に「仕掛け」を沿わせて、石鯛にアプローチしてください♪
磯際は石鯛が潜んでいる可能性が非常に高いポイントです。
如何に磯際を精度高く狙えるかが「釣果」に大きく影響するので、知識として押さえましょう!
磯の壁際や海底に仕掛けを沿わせると「ラインブレイク」が怖いですよね?
オモリ付近の釣り糸を中心に「擦れたり」「傷つく」ことが考えられます。
ラインブレイクを回する対策として「瀬ズレワイヤー」を使用すると◎です。
宙釣り仕掛けで石鯛を狙う時に使用するエサは「ヤドカリ」「サザエ」「ガンガゼ」になります。
これは捨てオモリ仕掛けと同様です。
宙釣り仕掛けで釣果を伸ばすなら「マキエ」を使用するのがおすすめ。
マキエを上手に使えると、効率良く足元に魚を寄せられます♪
ガンガセをハンマーで細かく砕いて、マキエにすると良いですよ〜!
堤防で使うべき「石鯛釣りの仕掛け(石鯛仕掛け)」とは?
堤防の石鯛釣りで基本となる仕掛けは「胴突き仕掛け」「ウキ釣り仕掛け」の2種類になります。
どちらも簡単な仕掛けなので、初心者さんでも扱いやすいですよ。
秋ごろになると石鯛の幼魚が餌を求めて堤防へ接岸してきます。
しかも群れでやってくるので、比較的簡単に「釣果」を狙うことが可能です。
成魚や幼魚関係なく「石鯛」が堤防から釣れた時の楽しさはたまりません!
石鯛の幼魚は「関東=シマダイ」「関西=サンバソウ」と呼ばれています。
見た目が厳つく体高の大きい成魚と対象的に、石鯛の幼魚は縞模様(しまもよう)がはっきり確認できるのが特徴的です。
幼魚といえど「磯の王者=石鯛」なので愛らしい姿に騙されてはいけません!
仕掛けにヒットした途端「強い引き」で釣り人を楽しませてくれます。
このスリル満点の「強い引き」が多くの釣り人を魅了しているのです。
上手に釣竿を曲げて、石鯛との駆け引きを制してくださいね。
堤防向け|石鯛釣りで使用する「釣竿(ロッド)」は?
堤防で楽しむ石鯛釣りでは、磯で使用するような「強力タックル」を準備する必要はありません。
堤防で釣れる石鯛のサイズや引きの強さって磯で釣れる石鯛に比べると劣ることが多いです。
「サイズ=小さい」「引き=弱い」わけではないので油断は禁物ですよ!
堤防で石鯛を狙うときは「磯竿(5m前後)」を使用してOKです。
遠投や置き竿で石鯛を狙うなら5.3m以上の長さがあると快適に釣りを楽しめると思います。
磯竿以外にも「投げ釣り用のロッド」「シーバスロッド」などで代用することも可能です!
長さは3m〜4.5mくらいが最適で、十分に堤防釣りを楽しめるでしょう。
堤防は足場が安定しています。
操作性を意識するなら長さ3m〜4.5m程度の釣竿が、初心者さんでも扱いやすいのでおすすめ。
調子はMクラス〜MLクラスを選ぶのが◎
繊細な操作ができるのでストレスなく石鯛釣りを楽しめますよ。
堤防向け|石鯛釣りで使用する「リール」は?
堤防で石鯛を狙う際は「2000番台のスピニングリール」を準備しておくと◎
王道のサイズ感なので、初心者さんでも十分扱いやすいと思います。
また軽量かつコンパクトなので持ち運びが便利なことも嬉しいポイント。
ですが大物の石鯛を狙うなら「パワー不足」は否めません。
パワー不足が気になるなら「4000番台〜5000番台のスピニングリール」を使うと安心して釣りを楽しめます。
あなたが堤防で大型の石鯛(一般的に全長50cm以上)を狙う際の参考にしてくださいね。
ギア比は「ローギア」のリールがおすすめです。
ローギアはパワーギアと呼ばれることもあり「ギア比:5未満」のリールのことを言います。
速い巻き取りスピードや強いパワーを備えていて、石鯛の強い引きにも負けません!
堤防向け|石鯛釣りで使用する「ライン」「フック」は?
堤防で石鯛を狙う際はメインラインに「ナイロンライン(3号〜5号)」を準備しましょう。
ライントラブルが少ないので初心者さんにも扱いやすいこと間違いなし。
またリーダーショックには「フロロカーボンライン(2号〜4号)」を準備しておくと◎です。
堤防釣りはライトな仕掛けを使うので、比較的細い釣り糸(ライン)を使うことができます。
ラインブレイクが心配な方は、太めの釣り糸(ライン)を準備してみてくださいね。
堤防で石鯛を狙うときに使用する釣り針(フック)は「伊勢尼針(10号〜13号)」がおすすめ。
釣り針(フック)も磯で使うものに比べると、そこまで強靭なものを準備しなくてOKです。
石鯛釣りの仕掛け(石鯛仕掛け)①:胴突き仕掛け
堤防で石鯛を狙う際は「胴突き仕掛け」を使用します。
胴突き仕掛けとは、仕掛けの先端にオモリを付け、幹糸に複数の枝ハリスを結んである仕掛けのことです。
海底に潜んでいる石鯛を狙いたい時に効果抜群!
胴突き仕掛けを使う釣り方ってシンプルなことが魅力的です。
まずは足元に胴突き仕掛け落として「石鯛がいないか?」と探りを入れましょう。
石鯛の反応がない場合、堤防を歩いて移動することを繰り返し「釣果」を伸ばす釣り方になります。
サシエ(ハリに付けるエサ)にはオキアミ・活エビ・虫エサを使用することが多いです。
動きと匂いを屈指することで石鯛を惹きつけましょう!
石鯛の反応(あたり)がないことも多々あります。
初心者さんの中には「釣れないかも..」と不安になる人がいるかもしれません。
不安になる前に「釣竿を少し持ち上げる→仕掛けが浮かぶ→釣竿を元の位置に戻す→再度仕掛けを落とす」といったアクションを行いましょう。
このアクションが石鯛を誘い好反応を得られることがあるんです!
自然界に生息している魚は「エサは上から落ちてくる!」と認識しています。
この認識を上手に利用してくださいね。
下記に「胴突仕掛けのタックルセッティング」についてまとめたので、チェックしてみてください。
【胴突仕掛けのタックルセッティング】
- 2000番クラスのスピニングリール
- ルアーロッド(6ft〜8ft/Mクラス・MLクラス)・磯竿や投げ竿(3.6m〜4.5m)
- 道糸:ナイロンライン(2号〜3号)
- スナップ付きヨリモドシ(5号〜6号)
- 幹糸:フロロカーボンライン(2号〜3号)1m前後準備する
※幹間30cm前後がおすすめ - 針:ムツ(10号〜12号)・丸セイゴ(11号〜13号)
- 枝ス:フロロカーボンライン(2号〜3号)15cm〜20cm準備する
- 捨て糸フロロカーボンライン(2号)20cm準備する
- オモリ(3号〜10号まで)
上記の「胴突仕掛けのタックルセッティング」を読んでみて気になるポイントはありましたか?
これから胴突き仕掛けで石鯛を狙う方は、ぜひ参考にしてくださいね。
石鯛釣りの仕掛け(石鯛仕掛け)②:ウキ釣り仕掛け
堤防で石鯛を狙う際は「ウキ釣り仕掛け」を使用することもできます。
グレ、チヌ、メバルを狙うフカセ釣りでも「ウキ釣り仕掛け」は使われますね。
サシエにはオキアミ・活エビ・虫エサを使うことが多いです。
先ほどご紹介した胴突き仕掛けと同じものになります。
コマセ(撒きエサ)としてアミエビを使うと「集魚効果」が期待できるので、石鯛を引き寄せることが可能です。
ウキ釣り仕掛けはキャスト(投げる)することが可能です。
沖目や障害物(テトラポットなど)の隙間に潜む石鯛を効果的に狙うことができますね。
ヒットした石鯛はテトラポッドや岩礁といった根に逃げ込む習性があります。
根に潜られてしまうと「ラインブレイク」する可能性が高いので、できるだけ素早く取り込むようにしてください!
船で使うべき「石鯛釣りの仕掛け(石鯛仕掛け)」とは?
船から石鯛を狙う時に使う「仕掛け」をご紹介です。
磯釣りでは「石鯛専用仕掛け」を使いましたが、船釣りは対照的に「一般的な仕掛け」を屈指して石鯛を狙います。
「大物を狙う」「強烈な引き」など、1匹とのファイトを楽しむことが磯釣りの魅力でしたが、船釣りの魅力は「数釣り」です。
「シマダイ」「サンバソウ」と呼ばれる中型サイズの石鯛をたくさん釣り上げましょう。
また、石鯛以外に「真鯛」「カワハギ」などの魚が釣れることも「船釣り」の嬉しいポイント。
「石鯛五目」と呼ばれていて、とても楽しく・盛り上がるので、ぜひチャレンジしてください!
余談ですが、石鯛は「白身のトロ」と呼ばれるくらい、脂が乗っていて食味が抜群ですよ♪
それでは、船釣りで使用する「仕掛け」のキモを確認していきましょう。
石鯛釣りの仕掛け(石鯛仕掛け)①:天秤仕掛け
石鯛仕掛け①は「天秤仕掛け」です。
関東で主流な仕掛けで、一緒に「コマセカゴ」を用いて石鯛を狙いますよ!
コマセやサシエには「オキアミ」を使うのがおすすめ。
擬似餌である「ウィリー針」を使うと、効果的に石鯛を誘えたり、食いつきが良くなりますよ!
誘いのアクションは「釣竿」をしゃくるのがコツ。
大きく・ゆっくり動かすことで「コマセを広範囲に拡散できる」「自然な動きを演出できる」でしょう!
釣果に大きく影響するので、ぜひお試しあれ。
天秤仕掛けでは「大物」が釣れる可能性があります。
いきなり40cm越えの石鯛がヒットすることも!
ということを踏まえ、強度のある釣り針やハリスを使用すると◎
具体的には「伊勢尼=6号前後」「ハリス=4号以上」がおすすめ。
繰り返しになりますが、石鯛の顎や歯は「甲殻類を噛み砕く」くらい、強力です。
クチバシのような形をしていて、釣り糸を簡単に切ってしまいます。
そんな石鯛に挑むなら、細い釣り糸や細いハリスを使用するのは禁物です。
石鯛釣りの仕掛け(石鯛仕掛け)②:胴突き仕掛け
石鯛仕掛け②は「胴突き仕掛け」です。
多くの釣り人さんが使用した経験がある、オーソドックスな仕掛けになります。
胴突き仕掛けを使用すると「海底の磯に潜む石鯛を直撃する」ことが可能。
コツは「素早い底取り」と「根掛かり回避」の2点です。
素早く海底を取ることで石鯛に出会えるチャンスが増えますし。
根掛かりが起こらなければテンポ良く船釣りを楽しめます!
船から胴突き仕掛けを使用して石鯛を狙うなら「サシエ」「マキエ」に工夫を加えましょう。
サシエには定番の「オキアミ」「活エビ」を用意するのがおすすめ。
海に活エビが豊富に生息している場合、船にあるパイプを利用して海底に「マキエ」を撒くと効果的です。
石鯛が集まる、石鯛の活性が高まるので「釣果」を出しやすくなりますよ。
石鯛は警戒心の強い魚でした。
そんな石鯛の警戒心を弱めるために「マキエ」を使うのも手段のひとつですが..。
ハリスに工夫をするのも良いかと。
具体的に「ハリス=50cm程度」と長めに取るのがおすすめ。
石鯛にプレッシャーを与えず、ナチュラルにアプローチしてください。
ラインブレイクに備え「ハリスの号数=4号以上」にしておくと、大物がヒットしても安心です♪
また、胴突き仕掛けを使用して大物を狙うなら「チヌ針=5号程度」も準備しておくと◎
石鯛のパワフルな引きにも、負けずに対応してくれるでしょう!
「遠投仕掛け」「宙釣り仕掛け」の違いを知り、上手に使いこなそう!
それでは「遠投仕掛け」と「宙釣り仕掛け」の違いをまとめていきます。
2つの仕掛けを使い分け、磯の王者である石鯛を釣り上げましょう!
遠投仕掛けは「釣り場=遠浅」な状況下で活躍!
石鯛釣りで使う仕掛けには大別すると「遠投仕掛け」と「宙釣り仕掛け」の2種類がありました。
この見出しでは「遠投仕掛け」について解説です。
遠投仕掛けは「石鯛が潜むポイントが遠い」場合に活躍します。
仕掛けの名前にある通り、遠投ができるためです。
遠投仕掛けの中にも「捨てオモリ型」「誘導テンビン型」と2種類のタイプがあります。
石鯛釣りビギナーは「どちらの仕掛けを使うべき?」と迷ってしまいますね..。
石鯛釣りは基本的に「底釣り(海底を狙う釣り)」なので「根掛かり」が怖いです。
このことを踏まえ初心者さんには、慣れるまで「捨てオモリ型」の遠投仕掛けをおすすめします。
捨てオモリ型の場合、根掛かりしても「オモリだけを切り離す」ことが可能。
危険が迫ると自ら切り離す「トカゲの尻尾」のようなイメージです。
オモリは犠牲になりますが、残った仕掛けを回収できるので「仕掛け全体がロストしない!」ことが、捨てオモリ型の魅力になります。
釣具代が安く済むので、財布に優しいんです。
下記に「遠投仕掛けに必要な道具」をまとめました。
【遠投仕掛けに必要な道具】
- イシダイ竿(5.0m)
- イシダイ用両軸リール(ベイトリール)
- 道糸(ナイロンライン20号前後・PEライン16号)
- ハリスワイヤー(38番を30cm用意)
- 三又コークスクリュー付サルカン
- 捨て糸(6号〜号10/0.5m〜1.5m)
- 六角オモリ(15号〜30号)
上記の「遠投仕掛けに必要な道具」を読んでみて気になるポイントはありましたか?
捨てオモリ型の遠投仕掛けを使用する場合。
道糸にサルカンを結び「ワイヤー(37号)」をつないでください。
ワイヤーをつないだ先に「三又サルカン」を結び「中間の穴=ワイヤーハリス・釣り針」「下部の穴=捨て糸(フロロライン7号)・オモリ」を接続します。
ポイントは「捨て糸(オモリを接続している糸)を細くする」こと。
根掛かりした時、耐久性が低い細い糸だけが切れるからです。
こうすることで「オモリ以外の遠投仕掛け」が回収しやすくなりますよ!
宙釣り仕掛けは「釣り場=急深な磯や堤防」で活躍!
続いて、宙釣り仕掛けについて解説です。
宙釣り仕掛けは「石鯛が足元に潜む」場合に大活躍。
急深の磯や堤防でよく使われます。
釣り方はシンプルで、海に仕掛けを落とし、違和感を与えないよう漂わせましょう。
積極的に誘いを入れると石鯛がヒットする確率が高まりますよ!
下記に「宙釣り仕掛けに必要な道具」をまとめました。
【宙釣り仕掛けに必要な道具】
- イシダイ竿(5.0m)
- イシダイ用両軸リール(ベイトリール)
- 道糸(ナイロンライン20号前後・PEライン16号)
- 瀬ズレワイヤー(37番を1ヒロ)
- ゴムキャップ
- 真空オモリ(15号〜25号)
- ビーズ玉
- スクリューサルカン
- ハリスワイヤー(38番を40cm用意)
- イシダイバリ(14号〜18号)
上記の「宙釣り仕掛けに必要な道具」を読んでみて気になるポイントはありましたか?
道糸の先にサルカンをセットしてワイヤー(37号がおすすめ)を結びます。
続いて「オモリ→ゴムチューブ」の順番でワイヤーに通し、その先に「スクリューサルカン」をセット。
スクリューサルカンに「ワイヤーハリス」と「釣り針(イシダイバリ)」を結んだら、宙釣り仕掛けの準備は完成です。
石鯛釣りのコツ4選をご紹介
石鯛釣りのコツ4選をご紹介です。
下記にこれから紹介する「石鯛釣りのコツ一覧」についてまとめたので、まずは全体把握をしてみてください。
【石鯛釣りのコツ一覧】
- エサ選び
- 餌の付け方
- 釣り場所に適した道具選び
- アタリに対する合わせ方
上記の「石鯛釣りのコツ一覧」を読んでみて気になるポイントはありましたか?
これから石鯛釣りを始める方は、ぜひ「釣果」を伸ばす参考にしてくださいね。
石鯛釣りのコツ①:エサ選びについて
石鯛には甲殻類、貝類、ウニなど硬い殻を好んで食べる食性があります。
この食性に合わせた「独特のエサ」を石鯛釣りで使用することが多いです。
他の釣り方では、ほとんど使用しないエサなので驚くこと間違いなし!
具体的には「ウニ系」「ヤドカリ系」「貝系」のエサを使用します。
ウニやサザエなどは高級食材なので、釣り場の状況を見極めて使用するようにしましょう。
それでは、石鯛を釣るのにとても大切な「エサ選び」について具体的に解説していきます。
エサ選び:ウニ系のエサ
石鯛釣りでは「ウニ系のエサ」を使用します。
ウニ系のエサって外道対策として有効です。
外道とは本命以外の魚のことを言い、石鯛釣りではカワハギ、ブダイ、アカハタなどが外道としてエサを狙ってきます。
ウニ系のエサは外道の食いつきが悪いので、餌を変える頻度を抑えることができますよ。
ウニ系の餌として「ガンガゼ」と「バフンウニ」が主な2種類として挙げられます。
それぞれの特徴を見ていきましょう!
ガンガゼは「集魚効果」が非常に高いです。
ですが棘が長く、毒があるので、扱う際には注意してください。
弱りやすい難点があるので、バッカンや発泡スチロール箱に入れて保存しましょう。
バフンウニも自然な香りが石鯛を誘います。
硬さを兼ね備えているので持ちが良いことが魅力です。
撒エサとして「砕いたガンガゼ」、食わせエサとして「バフンウニ」を使い分けるのが良いと思います。
ぜひ「ウニ系のエサ」を使う際の参考にしてくださいね。
エサ選び:ヤドカリ系のエサ
石鯛釣りでは「ヤドカリ系のエサ」を使用します。
以前は定番のエサとして高い人気を誇りましたが..。
ヤドカリの個体数が減少してしまい、現在では入手困難な「貴重なエサ」になりつつあります。
「釣具屋」でなら生きたヤドカリが手に入るかもしれません。
ですが、入手するのはかなり難しいと思うので「冷凍タイプのヤドカリ」の購入をおすすめします!
ネットショッピングで入手できるので、ぜひ上手に活用して「冷凍タイプのヤドカリ」を準備しましょう。
ヤドカリ系のエサは「遠投投げ仕掛け」に使うのに最適。
生命力が高いですし、針持ちも良いので遠投しても外れにくいんです。
独特の匂いや食感で石鯛を誘うので食いつきが良いことも嬉しいポイント!
エサ選び:貝系のエサ
石鯛釣りでは「貝系のエサ」を使用します。
安価で入手でき、集魚効果が高いので非常に人気の高いエサです。
主な貝系のエサとしてカラス貝、サザエ、トコブシが挙げられます。
初心者さんにはカラス貝がおすすめ。
扱いやすいですし、比較的入手もしやすいです。
釣具店や海鮮店で冷凍のカラス貝が販売されています。
一部の地域では、自然採取することも可能です。
サザエは石鯛の食いつきが良いというメリットがありますが、エサ取りに食べられてしまうことも多いです。
すぐにエサ取り食べられてしまうので、エサ交換に手間がかかります。
値段も高いので、初心者さんにおすすめできません。
トコブシも入手困難なことがデメリットです。
道具の準備に時間がかかりすぎるので、あまりおすすめはできません。
石鯛釣りのコツ②:餌の付け方について
石鯛釣りではエサを仕掛け付けるテクニックが必要になります。
「貝系のエサ」はエサ持ちが良いので、そのまま釣り針にセットして良いのですが。
「ヤドカリ系のエサ」を使用する際はテクニックが必要となります。
お腹の部分に釣り針を通したら、釣り糸でしっかりと縛ることがポイントです。
釣り糸でヤドカリ系のエサを縛ることでエサ持ちが良くなります。
石鯛の食いつきや、釣りを続けられる時間が向上するので、さらに石鯛釣りを楽しめるでしょう!
「ウニ系のエサ」を使用する際もテクニックが必要となります。
ウニの足やトゲに釣り針を引っ掛けるための専用道具「ウニ通し」を使用しましょう。
ウニ通しを使用して、ウニの中心に落ち着いて穴をあけて、釣り針を通せたら◎です。
足やトゲを傷つず、釣り針が外れないようにしてくれます!
ウニ系のエサを使うときのコツは?
ウニ系のエサを使用する時は「サルカン(スクリュータイプ)」を準備しておくと◎です。
仕掛けの準備時間を大幅に短縮してくれます。
ウニ系のエサって毎回釣り針とワイヤーハリスを外してウニに通す必要があるんです。
慣れるまでかなりの時間と労力を使用します。
作業の手間を省くテクニックとしてワイヤーハリスの先端(釣り針側)に「サルカン(スクリュータイプ)」を結んでおくと良いですよ。
糸ヨレも防いでくれますし、何よりワイヤーハリスを簡単に脱着できるのでウニ系のエサの交換がスムーズになります!
石鯛釣りのコツ③:釣り場所に適した道具選びについて
石鯛釣りで使用されるオモリの重さは「30号〜40号」になります。
慣れてきたら釣り場の状況に合わせてオモリを付け替えるのがいいですね。
潮の流れが早い場所で石鯛を狙うなら「50号」のオモリに付け替えるのが◎
潮の流れが緩い釣り場なら「20号」のオモリを使用しましょう!
石鯛釣りって根掛かりしやすいことがネック。
トラブルに備えて複数のオモリや仕掛けを用意しておくといいですね。
仕掛けを作り直す必要性はありますが、釣りを中断するケースを避けることができます!
石鯛釣りのコツ④:アタリに対する合わせ方について
石鯛は賢くて警戒心の強い魚なので、エサの種類や安全性を1度つっついて確認する習性があります。
異常がないと判断をしたら口を大きく開け、エサを食べ始めるんです。
最後はエサをいっきに咥えて逃げるので「強烈な引き」を味わえます。
この習性を踏まえ石鯛のアタリを感じても、すぐにアワセを入れないようにしてください。
まずはじ〜っと我慢です!
完全にエサを食い込む前に伝わる「前アタリ」を感じたら、落ち着いて穂先を下にさげます。
石鯛に警戒されないよう、少しずつ穂先を下げるのがコツです。
あとは石鯛が完全にエサを飲み込んだ時に現れる「本アタリ」に備えましょう!
本アタリは確実に石鯛を掛けられるタイミングです。
ここからは、初心者さんでも「本アタリ」というチャンスを逃さないためのポイントをご紹介していきます。
引き込まれるような「本アタリ」を逃さない!確実に合わせを入れよう
結論から言いますと「穂先を揺らさないこと」が石鯛の本アタリを確実にものにするコツです。
石鯛の警戒心は凄まじく、少しでも違和感を感じると逃げる可能性があります。
穂先を揺らさないために、しっかり釣竿を両手で握るのが石鯛釣りの基本です。
上記のテクニックを屈指することで、初心者さんでも上手に「本アタリ」のチャンスタイムに入ることができるでしょう。
海に身体が引き込まれるような、本当に強い石鯛の抵抗には驚きを隠しきれません。
スリリングな石鯛との駆け引きを心の底から楽しんでくださいね。
「本アタリがきたな!」と感じたら、いっきに釣竿を上に引き上げ「フッキング」を成立させましょう。
釣り針を石鯛の口に掛けることができます。
あとは落ち着いて石鯛を取り込めばOK!
石鯛が「釣れるポイント」とは?
石鯛が釣れるポイントを解説していきます!
効率良く石鯛を釣りたい人は、ぜひチェックしてください♪
石鯛釣りといえば「磯」と言われるくらいメジャー!
石鯛釣りで1番メジャーな釣り場は「磯」になります。
磯にはいろいろなポイントがあるのをご存知ですか?
陸地から歩いて向かう(地続き)場所や、船を利用しなければ辿り着けない場所まで、さまざまな「磯」が存在するんです。
基本的に磯は足場が悪いので「危険性」が高いです。
調査したら、潮の満ち引きが影響して「水没」するケースもあるそう。
正直「磯で行う石鯛釣り=上級者向け」だと思います。
これから磯釣りデビューをする人は、ぜひ「経験」「知識」「テクニック」が身についている釣り人と一緒に「磯」に向かうようにしてください。
磯での石鯛釣りは、基本的に2パターンの釣り方を使い分けられると◎です。
具体的には「遠投仕掛け」「宙釣り仕掛け」のどちらかを使用して、石鯛を狙いますよ!
使い分けとして「遠くにチャンス(カケアガリ・瀬など)がある場合=遠投仕掛け」「足元にチャンス(足元が深いなど)がある=宙釣り仕掛け」と考えてOK。
「堤防」はライトな仕掛けで石鯛を狙える!
個人的には、石鯛釣りは「堤防」からスタートするのがおすすめ。
磯に比べ足場が安定しているポイントなので「安全性」が高いんです。
また、潮の満ち引きが「満潮」になっても、足場が水没して消えることはありません。
石鯛釣りに興味のある初心者さんは、ぜひ堤防釣りからチャレンジしましょう!
もしかしたら「石鯛は堤防で釣れるの?」と疑問を抱く人もいるでしょう。
石鯛は堤防に接岸してくる魚なので、足元のすぐ下に潜んでいるんですよ〜!
足元にチャンスがあるので「宙釣り仕掛け」をメインで使用してくださいね♪
石鯛が「釣れる時期」とは?
それでは、石鯛が釣れる時期をご紹介です。
石鯛釣りを始める「ベストタイミング」がわかれば、初心者さんでも簡単に釣果を出せるかもしれません♪
石鯛が活発的になる「最適水温」とは?
石鯛が活発的になる水温は「16度〜24度」です。
比較的、暖かい水温を好む魚だと言えますね!
そんな石鯛を狙うなら「春(4月〜6月)」「秋ごろ(9月〜11月末)」がベストシーズン。
夏場は水温が上昇し過ぎるので、活性が低下したり、深場に逃げてしまうのです..。
ここで押さえたいのが「石鯛=1年を通じて釣れる魚」ということ。
日本各地に生息しているので、場所を選べばいつでも石鯛釣りにチャレンジできそうです。
流石の石鯛でも真冬は活性が低下します。
この時期から石鯛釣りを始めるのはおすすめできません。
水温が高まり始める、春先まで石鯛釣りをワクワクしながら待ちましょう。
「春先(4月〜6月)」は乗っ込みシーズンでチャンス!
春先(4月〜6月)は「乗っ込みシーズン」と呼ばれています。
乗っ込みシーズンとは、石鯛が産卵期を迎え「深場→浅瀬」に来るタイミング。
多くの釣り人にとって、絶好のチャンスなのです♪
また、大物が釣れる確率が高い時期でもあるので、ビギナーズラックを期待しちゃいましょう!
しっかりと強いタックルを用意しなければ、釣竿が破損したり、釣り糸が切れるので注意が必要です。
ぜひ「石鯛釣り専用タックル」をご用意くださいね♪
春先(4月〜6月)に石鯛を釣るなら「潮通りが良い磯」が主なポイントになります。
太平洋側の磯(和歌山県など)には、黒潮が流れ込むので狙い目ですよ!
石鯛が釣れやすい時期である「春先(4月〜6月)」でも油断は禁物。
もしかしたら「釣果ゼロ(ボウズ)」になるかもしれません。
少しでも釣果が出る確率を高めるために「アタリ(反応)数を上げるテクニック」を押さえましょう!
結論から言いますと「エサ撒き」をするのが有効です。
足元に石鯛を集められるので、石鯛が釣れやすくなります。
ウニを砕いて、自分が釣りをしているエリアに撒くのも良いのですが..。
ぶっちゃけ、出費が気になりますよね?
個人的には市販されている「エサ(石鯛釣り用)」を購入するのがおすすめ。
ほかにも、釣り場にいる「フジツボ」「亀の手」「ヤドカリ」を現地調達して、撒き餌として代用するのも良いかと!
お財布に優しいですし、確実に石鯛を足元に寄せられるでしょう。
「秋(9月〜11月末)」は食い気があるシーズン!
秋ごろ(9月〜11月末)は、石鯛が食い気を出す季節です。
この時期は、孵化したばかりの「小型〜中型」の石鯛がメインで釣れます!
秋は堤防に「若い石鯛」が餌を求めて集まるので、積極的に「アタリ(反応)」が出るタイミングです。
まだ経験の少ない石鯛を相手にするので、初心者さんでも釣果を伸ばせるでしょう。
環境によりますが、「春」「夏」「冬」と比べて、石鯛が釣れやすい傾向があると考えてくれてOKです。
これから石鯛釣りを始める人は、まずは秋(9月〜11月末)からスタートしてみては?
注意点として押さえたいのが、外道による「エサ取り」が多発ということ。
外道対策として「ウニ系のエサ」を使うのがおすすめ。
貝系に比べて、エサ持ちが良いので「餌が取れられた..」というトラブルが減少するはず。
石鯛釣りは「磯の王者」を相手に白熱ファイトが楽しめる♪
意外と敷居が低い石鯛釣りにチャレンジしよう!
石鯛釣りに必要になる、さまざまな「知識」「テクニック」「仕掛け」「釣り方のコツ」をご紹介してきました。
始めたての頃は「石鯛を釣るのは難しいなぁ..」と感じる人もいるでしょう。
ですが、トライアンドエラーを繰り返し、苦労して「石鯛が釣れた」時の感動体験は半端じゃありません。
1度味わったら、どんどん石鯛釣りの魅力にハマっていくはず!
この記事を参考にしていただき、ぜひ石鯛釣りにチャレンジしてくださいね♪
磯釣りには「専用タックル」が必要になります。
正直、釣竿やリールは非常に高価なので、気が進まない人もいるでしょう。
一見敷居が高そうですが..。
船釣りや磯釣りでは、「普段使用している仕掛け」が使えるので、思ったほど敷居は高くありません。
石鯛は漁獲するのが難しい魚ということもあり、なかなか市場に流通しません。
白身のトロと呼ばれるくらい、美味しい石鯛を食べれないなんて極めて勿体無い!
そんな石鯛をご自身で釣り、食べることこそ「釣り人の特権」と言えるでしょう。