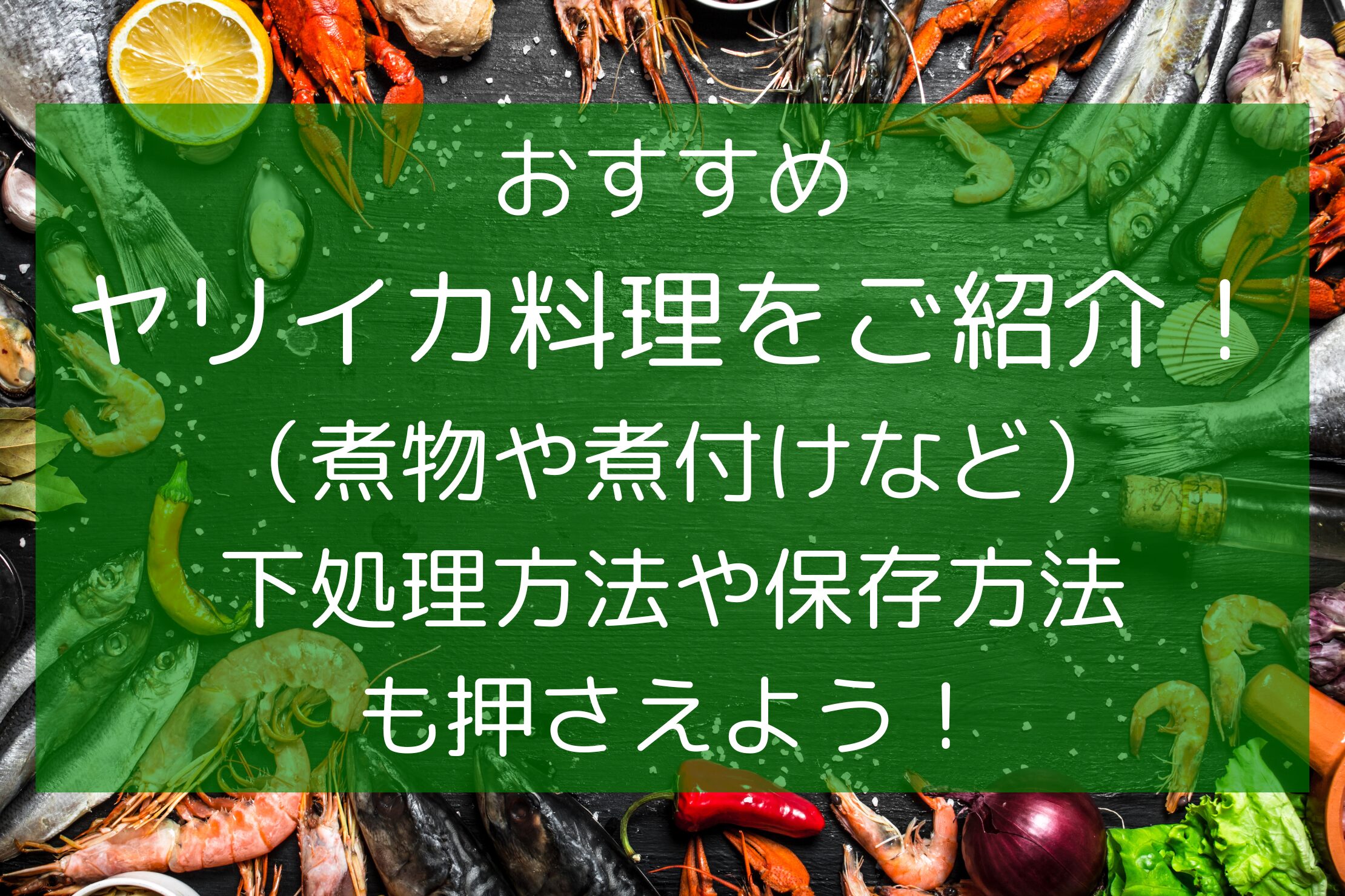Contents
まずは「ヤリイカについて」解説!
今回の記事の主役である「ヤリイカ」についてご紹介です。
ヤリイカは頭足綱(とうそくるい)ヤリイカ科に属しています。
漢字表記で「槍烏賊」と書くので、知識として押さえおくと◎です。
見た目が「槍の穂」に似ていることが、ヤリイカの名前の由来。
ビックリするくらい、鋭く尖った姿形は武器と使用する「槍」に似ています!
そんなヤリイカの胴体部分の長さは「雄」「雌」で違いがあります。
目安ですが「雄=30cm~40cm」「雌=20cm~25cm」程度まで成長するんです。
よ〜く見ると雄よりも雌の方がふっくらと丸みを帯びているのも印象的。
そんなヤリイカの食味は抜群で、とても美味しいです♪
あっさりと上品な甘さが、口一杯に広がります。
噛んでいて楽しい、程よく柔らかい食感もたまりません。
定番のお刺身や煮付け、炒め物にして調理すると、ヤリイカ本来の旨さを引き出せるでしょう!
美味しいイカであるヤリイカは「北海道〜九州(日本海側)」「インドネシア」と、幅広い地域に生息しています。
意外と身近な場所で釣れるイカ類なんですよ?
あなたが少しでも「美味しいヤリイカを釣って食べたい!」と考えているなら、ぜひヤリイカ釣りにチャレンジしましょう。
ヤリイカの「旬」はいつ?
釣れる時期で食味が変わる!
ヤリイカには「冬〜初春(1月〜3月)」「夏〜初秋(9月から10月)」にかけて、年に2回の旬が訪れます。
それぞれの季節で召し上がれるヤリイカに違いがあるので、ご紹介です。
冬〜初春(1月〜3月)にかけてヤリイカは「繁殖期」に入ります。
この時期に雌のヤリイカが釣れるとラッキーが起こるかも!
胴体にたくさん卵がたくさん詰まっている「子持ちヤリイカ」である可能性があります。
ヤリイカの「柔らかい食感」と卵の「プチプチ食感」が楽しくクセになり、大人気です♪
「夏〜初秋(9月から10月)」に水揚げされるヤリイカは「小ぶり」であることが特徴になります。
小さいヤリイカを馬鹿にしてはいけません。
この時期にしか味わえない、とろりとした口当たりが半端なく美味しいのです♪
小ぶりサイズをいかして「姿焼き」でいただくのがおすすめになります。
「ヤリイカ」と「ケンサキイカ」の違いを解説!
ヤリイカとケンサキイカの違いを解説していきます。
実際に見てもらうとわかりますが「ヤリイカ」「ケンサキイカ」は姿形が非常に似ているんです!笑
よ〜く観察すると「胴体部分」「触腕(腕のような部位)」で見分けられるので、詳しくみていきましょう。
一見、見分けるのが難しそうですが、上記の2点を押さえておくと「ヤリイカ」「ケンサキイカ」の見極めはバッチリです♪
それでは、早速「ヤリイカとケンサキイカの見分け方」についてまとめていきます。
まずは「胴体部分」の違いについて。
結論から言いますと、胴体の太さが「ケンサキイカ>ヤリイカ」と違いがあります。
ヤリイカはお名前にもある通り、まるで「槍」のように細長く・スタイリッシュな姿形をしているんです!
続いて「触腕(腕のような部位)」の違いについて。
「ヤリイカの触腕=胴体部分よりも短い」「ケンサキイカの触腕=胴体よりも長い」という特徴を押さえておくと◎です。
少し話は逸れますが「ヤリイカ」「ケンサキイカ」の食味が気になったので調査してみました。
ヤリイカは「あっさりと上品な甘さ」「コリコリ食感」を堪能でき、ケンサキイカは「ねっとりと濃厚な甘さ」「柔らかい食感」がお口に広がります♪
どちらのイカも「美味しい!」というポイントにおいて共通点があるんです!
ヤリイカ・ケンサキイカともに「幅広い料理」で堪能することが可能になります。
王道で、食材本来のおいしさを味わえる「お刺身」はもちろん。
優しい味わいが嬉しい「煮付け」、ご家庭の特色が出る「炒め物」などなど。
みなさんがお好きなイカ料理はなんですか?
今回の記事では「ヤリイカの煮物」をご紹介しているので、ぜひ1度味わってみてくださいね♪
煮汁が染みたヤリイカの身はたまりません〜!
美味しいヤリイカを「見分ける方法」を解説!
美味しいヤリイカの見分け方をご紹介です。
結論から言いますと「ヤリイカの鮮度=ヤリイカの色」で見極めてください。
海鮮卸売業者さんなど、目利きのプロも話していたので間違いない情報かと。
鮮度の高いヤリイカは「透明感があり、あざやかな赤黒色」をしています。
時間が経過するにつれ、ヤリイカの鮮度が徐々に消えていき「白く濁った」見た目に変化していくんです。
イカ類全般に言えますが「透明→茶色→白色」と、身は変色するので押さえておくと◎
美味しいヤリイカに出会える確率がグ〜ンと高まるでしょう。
繰り返しになりますが「美味しいヤリイカを食べたい!」と考えているなら、ぜひ「透明感があり、あざやかな赤黒色」をしたヤリイカを目利きして選んでください!
美味しいヤリイカを目利きできたら、食材本来の「新鮮さ」「旨味成分」「食感」をダイレクトに堪能できる「お刺身」でいただくのがおすすめです♪
ヤリイカの魅力のひとつである「食味の良さ」の虜になること間違いなし。
基本的な「ヤリイカの下処理方法」を解説!
それでは、ヤリイカの下処理方法を解説です。
今回の主人公である「ヤリイカ」は冬から春先にかけて「旬」を迎えます。
この時期のヤリイカが1番美味しくいただけるでしょう♪
ヤリイカは食材として「身が柔らかい」ことが特徴。
火を通しても、ヤリイカの身は硬くなりにくいので「煮物」に最適なんですよ。
他のイカ類である「スルメイカ」「アオリイカ」と比べても、抜群な口当たりを楽しめる「ヤリイカ」をご賞味ください♪
ヤリイカの姿形についておさらいです。
ざっくり「形状=先端が尖った、細長い槍のよう」「耳(エンペラ)部分=大きい」ことが特徴的でした。
見た目に特徴があるので、他のイカ類と見分けやすいと思います。
美味しいヤリイカを購入するには「色に透明感があるか?」「体液(ドリップ)が出ていないか?」をチェックすると◎
鮮度の高いヤリイカの身って「透明感があり、あざやかな赤黒色」をしていました。
白く濁り始めていたり、体液(ドリップ)が出ている個体は「食味が良くない」「生臭い」可能性があるので注意。
前置きが長くなりましたが..。
ここからは「ヤリイカの下処理の手順」を詳しくご紹介です!
下処理①:ヤリイカの胴体とゲソを指でゆっくり離し、ワタを引き抜こう!
下処理①は「ヤリイカの胴体とゲソを指でゆっくり離し、ワタを引き抜く」です。
まずは、ヤリイカをまな板の上に寝かせて置きます。
あなたが右利きなら「ヤリイカの頭が左向き」左利きなら「ヤリイカの頭が右向き」に置くと◎です。
ややこしくなるので、ここから先はあなたが「右利き」と仮定して内容をまとめていきます!
左利きの人は、左右を入れ替えてお読みください。
ヤリイカの頭を左向きにして、まな板に置けたら「胴体部分を左手で押さえる」「右手でゲソ(腕のような部分)を引っ張る」ステップに入ります。
具体的には、ヤリイカの胴体と足が繋がっている部分まで、右手の指を入れて引き剥がしてください。
胴体を左手で押さえ、ゲソを右手で水平にゆっくり引けたら「内臓(ワタ)」も一緒に引き抜けるはず。
内臓まで綺麗に引き抜く感覚は、大量のお芋を1度でゲットできた「芋掘り体験」のような感じです!笑
下処理②:軟骨を利き手で引き抜く!
下処理②は「軟骨を引き抜く」です。
軟骨があると、口当たりが良くありません。
ヤリイカを美味しく食べるなら、軟骨処理をお忘れなく!
ゲソと内臓を処理した、ヤリイカの胴体の内側を探っていると。
「なんか硬い?」といった感じで、手触りに違和感のある箇所があるはず。
違和感の正体が「透明な軟骨」で、まるでプラスチックのような感触をしています。
軟骨がある部分を把握したら、あとは利き手で引っ張るだけでOK。
しっかりと指で摘んで、抜き取りましょう!
下処理③:ゲソとワタを切り離し、目とくちばしを取ろう!
下処理③は「ゲソとワタを切り離し、目とくちばしを取ろう!」になります。
ゲソに付いているワタは「包丁」で切り取り、ゴミ箱に捨ててOKです。
ワタには苦味や濃厚な旨味があるのですが、今回の煮物料理では使用しません。
召し上がりたい方は、ぜひ「塩辛」「キモ焼き」など、お酒あてに最高な一品料理にしてお召し上がりください♪
また「くりばし」「目の部分」も取り除きます。
これらの部分は硬く「口当たりが悪い」ので、あらかじめ処理しておくと◎
目の切り落としは簡単なのですが..。
丸く硬いくちばしは、意外と見落としがち。
ヤリイカの足の付け根の真ん中あたりに、潜んでいるので要チェック!
目と目の中間に、包丁を入れて開くと「クチバシ」が出てくるので処理しやすいかと。
下処理④:皮をむいてよく洗う!
※煮物の場合はむかなくてもOK
下処理④「皮をむいてよく洗おう!」です。
あなたが煮物を作るなら、下処理④はスキップしてOK。
ヤリイカって小ぶりかつ身が柔らかいので、そのままでも美味しく食べれますよ♪
刺身でヤリイカを食べるなら、口当たりを良くするために「皮をむく」のをお忘れなく。
ぜひ、素材本来のコリコリ食感を堪能しましょう!
余談ですが、ヤリイカの皮にはコラーゲンが豊富に含まれているので「美容効果」を期待できるそうです♪
ヤリイカの皮のむき方は簡単。
キッチンペーパーで軽く擦り、こそげ落とす。
もしくは、すでに皮が破けた部分に指を入れてむくのが良いかと。
赤い皮を取り除き、白く美しい身が現れた時の快感はたまりません!笑
ヤリイカの皮は上手に取り除けましたか?
最後に、水でよく洗い「ヤリイカの下処理」が完了になります。
胴体中にある、ワタ残りも忘れずに処理してくださいね!
定番料理「ヤリイカの煮物」レシピを解説|染み出す煮汁が食欲をそそります〜!
ヤリイカの下処理は上手にできましたか?
ここからは「美味しいヤリイカの煮物レシピ」をご紹介です!
下記に「煮物に必要な材料(2人分)」をまとめたので、チェックしてください。
【煮物に必要な材料(2人分)】
- ヤリイカ:3杯
- お水:大さじ2杯(30ml)
- お酒:大さじ2杯(30ml)
- お醤油:大さじ2杯(30ml)
- みりん:大さじ2杯(30ml)
- お砂糖:大さじ2分の1
- 生姜の薄切り:5枚~6枚
※イカを数える時は「杯」が使われるので、知識として押さえると◎
続いて「ヤリイカの煮物作り方(4ステップ)」をまとめていきます。
【ヤリイカの煮物作り方(6ステップ)】
- ヤリイカの胴体を「幅2cm程」に切ります。
※ゲソが長い場合、半分にカットして◎ - ヤリイカ以外、全ての材料(お水、醤油、みりんなど)をお鍋に入れて、沸騰させます。
- ヤリイカをお鍋に入れて、落とし蓋をする。
- 再び沸騰させて、中火(弱め)で約3分間程煮る。
- 落とし蓋を取り除き、やや火を強めて煮る(コツは「煮汁をヤリイカによ〜く絡める」ことです♪)
- 2分程経ち、煮汁の量が3分の1程度になったら「ヤリイカの煮物」完成です。
上記の「ヤリイカの煮物作り方(6ステップ)」を読んでみて気になるポイントはありましたか?
書きれなかった、ヤリイカの煮物を美味しく作るコツをまとめていきます!
ヤリイカは煮込むと「身が縮む」ので、食べ応えに物足りなさを感じる場合も..。
食べ応えがある煮物に仕上げるなら「ステップ1」に工夫を加えてください。
今回は2cmにヤリイカの身を切ってますが、大きめに切るのがポイント。
ヤリイカを煮た後も、ちゃんと身が残るので食べ応え抜群!
ヤリイカの柔らかさも堪能し尽くせるので、ぜひあなた好みに調整してくださいね〜。
ほかにも、ヤリイカは火を通しすぎると「硬くなる」ので注意。
生で食べる時を除き「サッと火を通して、美味しく仕上げる」のがイカ料理の鉄則です。
ヤリイカの「柔らかい食感」を残して、煮物を仕上げるなら「ステップ3」に工夫を加えましょう。
具体的にあh、再沸騰させる間「ヤリイカを鍋から取り出す」だけでOKです。
ある程度、煮汁が煮詰まったタイミングで「ヤリイカ」を鍋に戻すと、味は染み染みなのに「食感が硬くない!」煮物が出来上がります!
ヤリイカの「保存方法」を解説!
ヤリイカの「保存方法」についてご紹介です。
基本的に、下処理済みのヤリイカは「冷蔵保存」「冷凍保存」のどちらで保存してもOK!
目安ですが「すぐに食べる予定がある=冷蔵保存」「すぐに食べない(3日以上食べる予定がない)=冷凍保存」がおすすめです。
ちなみに、ヤリイカの冷凍保存期間は「約1ヶ月」なので、お忘れなく!
調査したら、使いきれず余ったヤリイカを「冷凍保存」している人がいました。
冷凍保存の感想として「すぐ使えて便利」「下処理しているので、面倒な手間を省ける」ことが、嬉しかったそうです。
ここからは、具体的な「ヤリイカの冷凍保存方法」をまとめていきます。
まず、下処理が済んでいるヤリイカを「サランラップ」でピッタリ包んでください。
その後、保存袋(ジーパー付き)に入れるだけでOK。
すでに「〇〇料理で使うか〜」とヤリイカの用途が決定している場合。
あらかじめ輪切りや短冊切りを加え、料理で使いやすい形状に切り分けておくのがおすすめ。
解凍するだけで、すぐに調理に取りかかれ便利ですよ!
冷凍保存は、小ぶりなヤリイカに限りますが、解凍していない状態でも「使いたい形状にカット」できるのも魅力。
ヤリイカの「冷蔵保存方法」とは?
それでは、ヤリイカの「冷蔵保存方法」をご紹介です。
下記に「ヤリイカの冷蔵保存方法」についてまとめたので、チェックしてください。
【ヤリイカの冷蔵保存方法】
- 下処理が完了したヤリイカの水分をキッチンペーパーで拭き取る。
- 部位別、もしくは食べやすくカットしたヤリイカをサランラップで包む。
- フリーザーバックに入れて、冷蔵庫に保存する。
上記の「ヤリイカの冷蔵保存方法」を読んでみて気になるポイントはありましたか?
すぐにヤリイカを食べる予定がある人は、ぜひお試しください。
ヤリイカを冷蔵した時の「保存期間=2日~3日」が目安になります。
個人的には、お刺身でヤリイカを食べるなら「翌日」にいただくのがおすすめ。
少しでも鮮度の高いヤリイカを食べてもらえたら、嬉しいです♪
ヤリイカの「冷凍保存方法」とは?
それでは、ヤリイカの「冷凍保存方法」をご紹介です。
下記に「ヤリイカの冷凍保存方法」についてまとめたので、チェックしてください。
【ヤリイカの冷凍保存方法】
- 下処理が完了したヤリイカの水分をキッチンペーパーで拭き取る。
- 部位別、もしくは食べやすくカットしたヤリイカをサランラップで包む。
- フリーザーバックに入れて、袋内の空気をできるだけ抜く。
- その後、冷凍庫に入れて保存する。
上記の「ヤリイカの冷凍保存方法」を読んでみて気になるポイントはありましたか?
ヤリイカをすぐに食べる予定がない人は、ぜひお試しください。
ヤリイカを冷凍した時の「保存期間=約1ヶ月」が目安になります。
冷凍していても、完全に腐敗を防げるわけではないので注意。
念の為に、冷凍保存したヤリイカは「加熱処理」をしてから食べてください!
ヤリイカを解凍するタイミングは「調理で使用する前日」がおすすめ。
ゆっくり余裕を持って解凍できるので、調理前に慌てる心配がありません。
もちろん、調理直前に「流水解凍」するのも可能です。
解凍するときのコツは「完全に解凍せず、半解凍を目指す」ことになります。
これだけで「ヤリイカの生臭さ」を抑えられるんです!