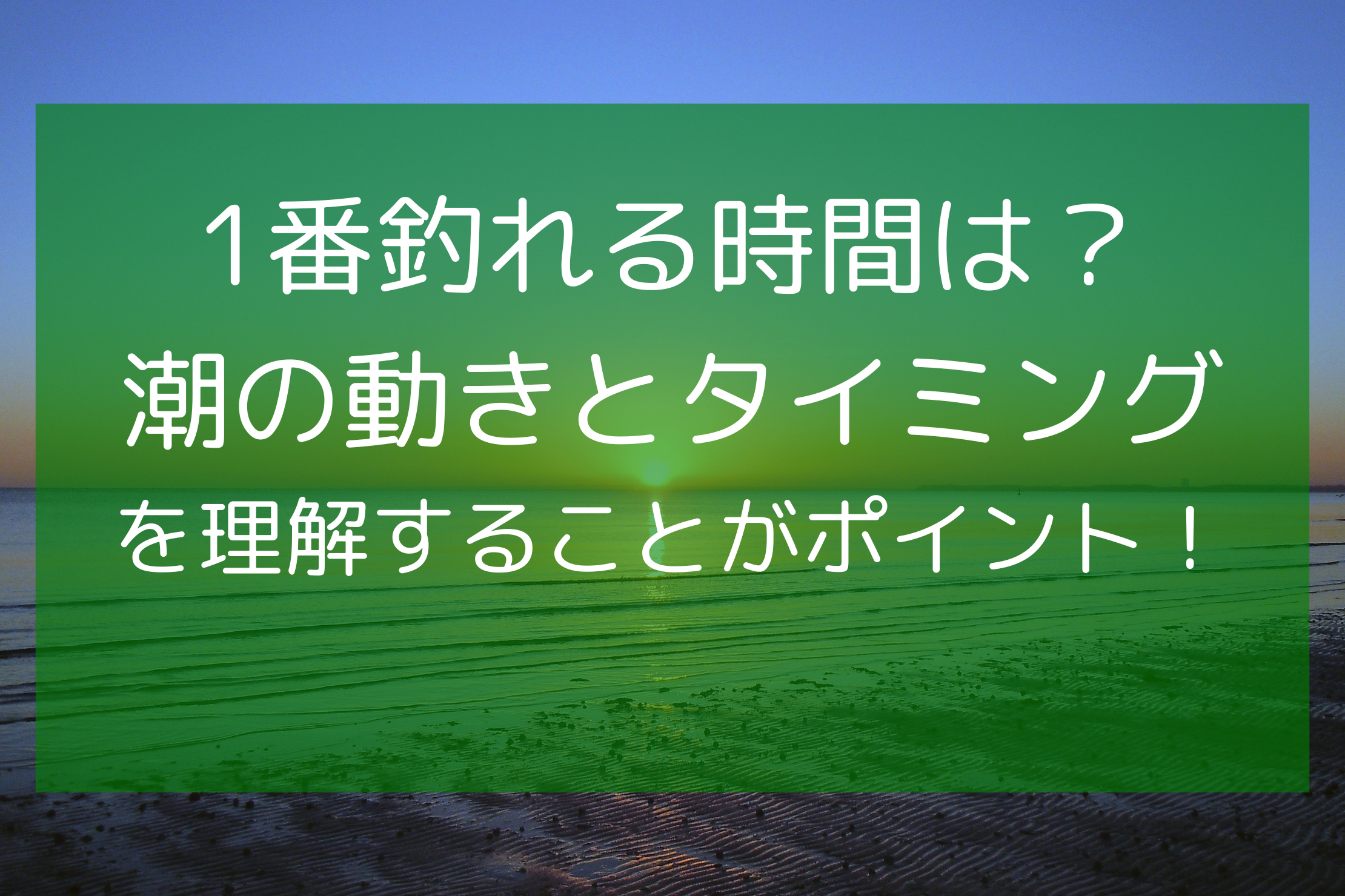Contents
魚の活性と潮の関係とは?
魚の活性と潮周りに密接な関係があることみなさんはご存知でしょうか?
潮周りとは、潮の満ち引きの大きさや状態を表しています。
魚の活性が高くなる原理を「潮の動き」と「食物連鎖」の観点からみていきましょう。
潮の動き(流れ)は酸素とプランクトン(魚の餌)を海に生息している魚に運んできます。
魚は水中から酸素を取り込むことで呼吸をしています。
潮が動ごき水中の酸素量が増えると魚は活発に動けるようになるんです。
また、潮が流れ込んでくると魚の餌となるプランクトンが運ばれ、そのプランクトンを捕食しようと小魚の活性が上がります。
続いて、活性の上がった小魚を捕食するフィッシュイーター(捕食魚)が、我こそはと小魚たちを捕食し始め活性が高まります。
「プランクトン→小魚→フィッシュイーター(捕食魚)」といった感じで「食物連鎖」が始まるのです。
潮の種類
海において潮の満ち引きは、太陽と月の引力が影響して発生します。
地球に対し、月と太陽が一直線上に重なると潮の動きが大きくなります。
このタイミングが「大潮(おおしお)」と呼び、魚の活性が1番高いです。
地球を中心に、月と太陽が互いに直角方向にずれている時は潮の動きは小さくなります。
このタイミングを「小潮(こしお)」と呼び、魚の活性は低めです。
潮汐(ちょうせき)と呼ばれる海面水位の動きを表す言葉があります。
上記にある「大潮(おおしお)」「小潮(こしお)」は、潮汐(ちょうせき)の一部です。
全部で5種類の潮汐(ちょうせき)が存在していて、それぞれ「潮の動き方が異なる」ので、違いをチェックしてください!
まずは、下記の「潮汐(ちょうせき)サイクル」に触れてみて、ざっくり全体把握をしましょう。
【潮汐(ちょうせき)サイクル】
大潮→中潮→小潮→長潮→若潮→中潮→大潮(15日間かけて1サイクルが終わる)
潮汐(ちょうせき)サイクルを把握できましたか?
あなたが釣行する日が潮汐(ちょうせき)5種類のうち、どれに当たるのか調べることがおすすめです。
釣果に大きく影響してきますよ!
それでは、潮汐(ちょうせき)の特徴をまとめていきます。
まずは「大潮」の特徴から追っていきましょう。
潮汐(ちょうせき)サイクル:大潮(おおしお)
まずは「大潮(おおしお)」からご紹介。
大潮(おおしお)は、満潮と干潮の潮位差が最も大きくなる日です。
地球に対して月と太陽が一直線上に重なったときに起こります。
大潮(おおしお)は、潮の動きや潮の流れが最も大きいです。
潮の流れがあるので魚の活性が高いと言えますね。
魚も動きやすいですし、水中にプランクトンや酸素が豊富に存在しています。
魚の活性が上がるので、魚を釣りやすい時間です。
満月や新月の当日や前後の日が「大潮(おおしお)」に該当するので、釣りをするならこのタイミングを狙いましょう!
潮汐(ちょうせき)のサイクル:中潮(なかしお)
続いて「中潮(なかしお)」についてご紹介。
大潮と小潮の間にある中潮(なかしお)は、満潮と干潮の差が中程度です。
潮の動きや流れがまずまず(極端に早くない)なので、快適に釣りを楽しめます。
大潮(おおしお)に次いで魚の活性が高いこともあり、最も釣りを楽しめる潮汐(ちょうせき)です。
中潮(なかしお)は、大潮(おおしお)の前後に2回発生します!
このタイミングを逃さないようにしてくださいね。
潮汐(ちょうせき)のサイクル:小潮(こしお)
続いて「小潮(こしお)」についてご紹介。
小潮(こしお)とは、潮の干満の差が最も小さくなる日や状態のことです。
地球を中心に、月と太陽が直角の方向にくる(上弦・下弦)時、それぞれの起潮力(きちょうりょく)を打ち消すので潮差が小さくなります。
潮差が少ない小潮(こしお)時は、潮がゆっくりとしか動かず、海水の流れが少ないです。
海中に酸素やプランクトンが流れ込まないので魚の活性が上がりません。
釣果も落ちやすく、ポツポツと魚が釣れることが多くなります。
潮汐(ちょうせき)のサイクル:長潮(ながしお)
続いて「長潮(ながしお)」についてご紹介。
長潮(ながしお)は、干満の差が最も小さく潮の動きが極端に少ない潮汐(ちょうせき)サイクル。
小潮が終わると起こり、上弦の月・下弦の月を2日ほど過ぎた頃のタイミングです。
長潮(ながしお)のタイミングは釣りを避けるのが良いと思います。
潮の動きや流れがほとんどなく、魚の活性が上がらないからです。
あらゆる方向にプランクトンや小魚が漂っていて、魚が餌を捕食することもできません。
遊泳力の弱い魚なんて、捕食スイッチが全く入らないこともあります。
1番釣果を上げにくい潮汐(ちょうせき)なので、釣りをするなら「腕試し気分」で向かいましょう。
潮汐(ちょうせき)のサイクル:若潮(わかしお)
続いて「若潮(わかしお)」についてご紹介。
若潮(わかしお)とは、中潮に変わる手前の潮周りです。
魚の活性が低い長潮の次の潮回りなので、魚の活性が徐々に回復してくるタイミング。
少しずつ潮の干満差が回復することで「潮が動き」「潮の流れ」が起こり、魚の活性が回復します。
魚を釣りやすい時間帯!潮の動き始めと潮が止まる手前をご紹介
それでは「魚を釣りやすい時間帯」についてご紹介します。
魚を釣りやすい時間帯として「潮の動き始め」「潮が止まる手前」があり、潮が動いて魚が釣れるタイミングです。
「潮の動き始めはいつ?」「潮が止まる手前はいつ?」と疑問を持った人が多いと思います。
ズバリ結論から言いますと「満潮(まんちょう)前後」「干潮(かんちょう)前後」が、潮が動くので魚を釣りやすいタイミングです。
このタイミングは潮の満ち引きの割合を表した釣り用語で「上げ3分下げ7分」「上げ7分下げ3分」と言われることもあります。
※干潮から満潮(満潮から干潮)までに掛かる時間を10等分した数値の割合です。
満潮とは、海面の高さが最大まで上昇したタイミング。
反対に干潮とは、海面の高さが最も下降したタイミングを指します。
勘違いしている人が多いのですが..満潮や干潮は潮の流れが少ないので魚はあまり釣れません!
そんな満潮と干潮は、ほぼ全ての釣り場で「1日2回ずつ」生じるので、満潮と干潮前後は「集中必須」です。
さあ、ここからが肝心です!
「潮の動き始め」「潮の動きが止まる手前」は、魚の活性が高くルアーや仕掛けを積極的に食いついてきます。
先ほどお伝えした「大潮」と「中潮」の満潮前後・干潮前後のタイミングは、潮が大きく動くので「プランクトン」や「酸素」が海中豊富に存在しています。
魚の活性が高まること間違い無しですね。
ぜひ、釣りをする「狙い目」として満潮前後・干潮前後のタイミングを把握しておきましょう。