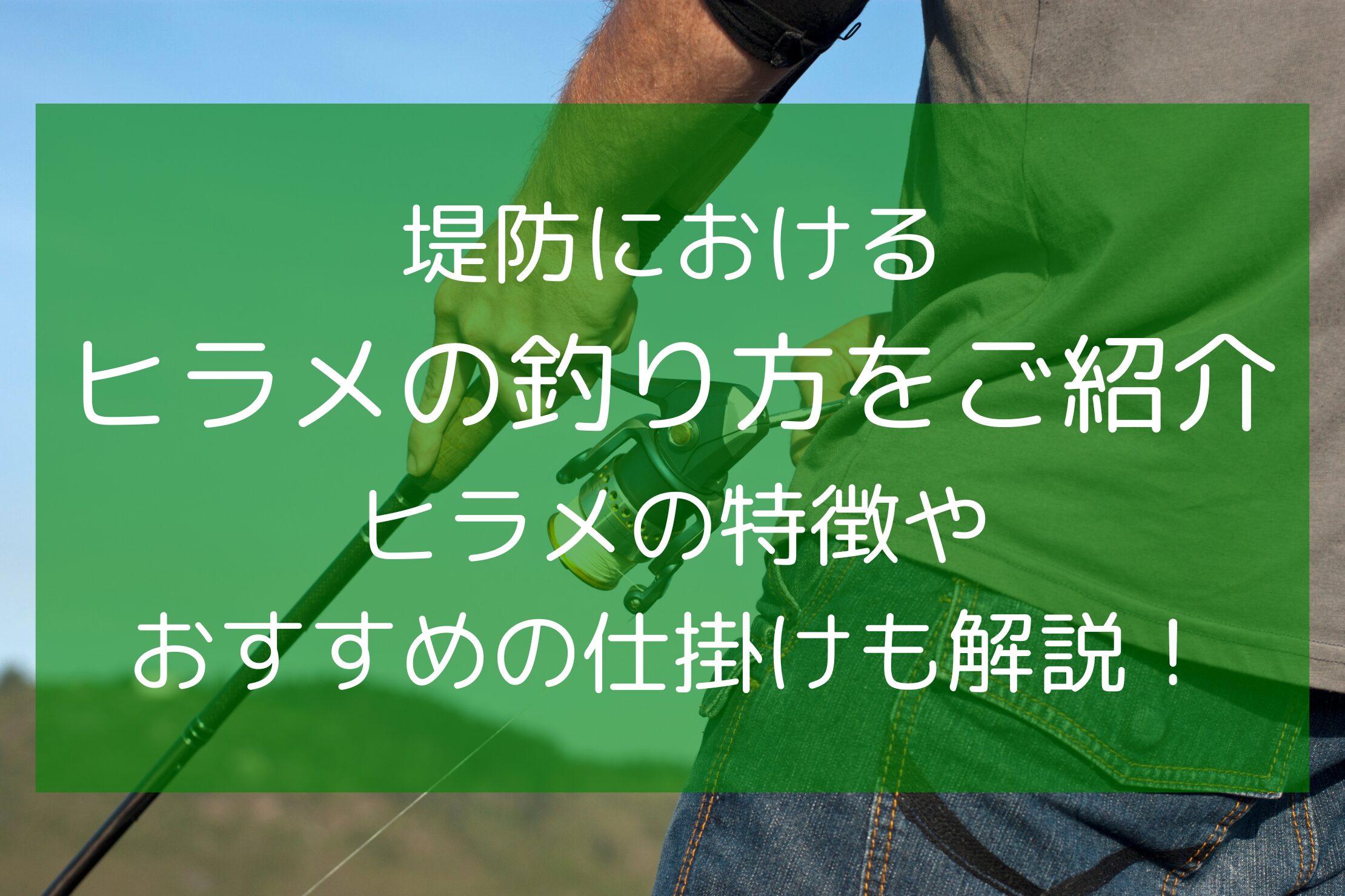今回のターゲットになる「ヒラメの特徴」について解説していきます。
ヒラメは水深20m〜200m程度の砂泥地(海底や湖底などで、砂と泥が混ざりあった場所)に生息している魚です。
ヒラメって「あまり動かなそう」といったイメージがありませんか?
実際のヒラメは捕食対象である小魚や甲殻類を狙う際には、全身を使い泳いで追いかけます!
水中で動き出したヒラメは非常に迫力があるので、ぜひYouTubやInstagramでチャックしてみてくださいね。
ヒラメ最大の特徴は「左右に扁平な体形」だと思います。
両目が体の左側に寄っているので、見た目のインパクトが強烈です。
そんなヒラメの魚体は最大で1m程の大きさに、その時の重さは約10kgとかなり大型にまで成長しますね。
これは余談ですが、お腹を手前に向けたとき「顔が左にくる=ヒラメ」「顔が右にくる=カレイ」になります。
カレイに比べてヒラメの方が、口が大きく歯が鋭いので注意が必要です。
堤防でヒラメが釣れた際には、ヒラメの口周りに手を近づけないよう注意してくださいね。
【ヒラメの特徴まとめ】
- 分類:カレイ目・カレイ亜目・ヒラメ科・ヒラメ属・ヒラメ種
- 別名:ソゲ(若魚)、オオクチ、カレ、ゾゲ、バカレイ、ヒダリグチ、ホンガレイなど
- 釣りやすい季節:春~初夏(4月~6月)・秋~冬(10月〜12月)
Contents
堤防からヒラメを狙うなら「泳がせ釣り」で釣ろう!
堤防でヒラメを狙うなら「泳がせ釣り」をおすすめします。
ルアー(擬似餌)を使用した釣りでもヒラメを釣ることはできますが、生きた餌(アジなど)を使用する「泳がせ釣り」の方がヒラメの反応が断然に良いことが多いです。
泳がせ釣りには生きた小魚(アジ、イワシなど)を餌として使用します。
アジ、イワシといった生き餌を釣り針に付け、これらを捕食する大型魚(ヒラメや青物など)を狙う釣り方です。
関西地域では泳がせ釣りのことを「ノマセ釣り」と言うことがあるので、釣り知識として押さえましょう!
泳がせ釣り(ノマセ釣り)は道具が比較的揃えやすいですし、難しいテクニックを必要としません。
初心者さんでもお手軽にチャレンジしやすい釣り方だと言えますね!
またお手軽に大物を狙えることも魅力的で、初心者さんも堤防で楽しむ「泳がせ釣り(ノマセ釣り)」にチャレンジしてみましょう。
ビギナーズラックだとしても大物のヒラメを釣り上げた感動体験は忘れられない記憶になること間違いなしです。
ヒラメの釣り方「泳がせ釣り」について
それでは、泳がせ釣りについてご紹介です。
泳がせ釣りの特徴や必要な道具についてまとめています。
泳がせ釣りとは?釣り場:堤防や磯など
泳がせ釣りは、堤防・波止・磯・イカダといったフィールドを釣り場として楽しむことができます。
フィールドを選ばないので堤防や波止といった身近な場所から、お手軽に始めることができるんです!
初心者さんでもチャレンジしやすい釣り方だと言えますね。
ヒラメは数釣りができる?
初心者さんの中には「ヒラメをたくさん釣りたい!」と数釣りを楽しみにしている人もいるかと思います。
実は、ヒラメの個体数ってさほど多くありません。
堤防でヒラメを狙った「数釣り」は難しいのが現状です。
泳がせ釣りの基本や初心者さんが釣果を伸ばすコツは?
泳がせ釣りでヒラメを狙う際には、釣果実績のあるポイントを探してから竿出し(釣りを開始するまでの一連の動作)をすることが基本となります。
少しでも「釣果」を伸ばしたいなら、ヒラメの餌である小魚が回遊しているタイミングを狙うと◎です。
日の出前後「朝マズメ」や日没前後の「夕マズメ」といったプランクトン(ヒラメの餌)の活性が高まる時間帯が釣果を期待できるでしょう!
泳がせ釣りで準備するアイテムは?
泳がせ釣りをストレスなく快適に行うなら「柔らかめの磯竿」を準備するのがおすすめ。
これは泳がせ釣りが「食い込み(魚がしっかり餌を捕食した状態)」を重要視するからです。
釣竿が柔らかいと、ヒラメが餌をくわえた際に「違和感」を感じないので、口の中に餌を入れている時間が長くなりますよ!
泳がせ釣りでは生き餌を使用します。
生き餌として使用される小魚(アジ、イワシなど)は現地で調達することが基本です。
現地で調達した生き餌(アジ、イワシなど)はクーラーボックスやバッカンに入れて生かしておきましょう。
生き餌が弱るのを防ぐために、釣り針に生き餌を付ける工程を素早く行うことを意識してください。
弱っている生き餌だとヒラメの興味を引くことが難しくなります。
活き活きと動き回りヒラメに猛烈にアピールする生き餌を準備できるかが「釣果」を大きく左右しますよ!
泳がせ釣りの釣り方は?
泳がせ釣りの釣り方をまとめていきます。
海に仕掛けを投入しオモリが着底したことを確認したら、釣竿を軽くあおったり、リールハンドルを少し巻いて「糸ふけ」を取ってください。
糸ふけが取れた後は、リールに付いているドラグを緩め「ヒラメの反応(アタリ)」を待つだけです。
ヒラメが生き餌に食いつくと、釣竿の先端(穂先)が大きく曲がり始めます。
※余談ですが釣竿の先端(穂先)が大きく曲がることを「お辞儀」と表現することもあるそうです。
釣竿の先端(穂先)が大きく曲がった瞬間に「アワせ」を入れてしまうと、素バリを引くことになる可能性が高いです。
ヒラメが生き餌を食べたにも関わらず、針が口に残らず手元に戻ってきてしまいます。
多くの人が「ヒラメが掛かったのに..」と落ち込んでしまうでしょう。
このようなトラブルを避ける為に、ヒラメの反応(アタリ)があったら「ゆっくり釣竿を立てる!」そして「手元に重みを感じたら大きくアワセを入れる!」といった2点を押さえましょう!
焦らずゆっくりと動作を行うだけでヒラメを手元に連れてこれる確率がぐ〜んと高まりますよ。
泳がせ釣りに「必要な道具」とは?
ここからは、泳がせ釣りに必要な道具について深ぼって解説していきます。
下記に「泳がせ釣りに必要な道具一覧」をまとめたので、まずは全体把握をしてみましょう。
【泳がせ釣りに必要な道具一覧】
- 磯竿:2号〜4号(4.5m〜5.3m)
- スピニングリール:3000番〜4000番
- 道糸:PEライン(1号〜2号)、ナイロンライン(3号〜4号)
- サルカン:道糸とサルカンはダブルクリンチノットで結ぶ、幹糸とサルカンはクリンチノットで結ぶ
- 幹糸(複数本のハリスを付ける元の糸のこと)
- サルカン(遊動式):幹糸とハリスはクリンチノットで結ぶ
- ハリス:フロロカーボンライン(3号)を70m〜80m程度準備
- チヌバリ:5号〜7号
- 捨て糸:フロロカーボンライン(2号)を50cm程度準備
- スナップサルカン:捨て糸と六角おもりはクリンチノットで結ぶ
- 六角おもり:5号〜10号
上記の「泳がせ釣りに必要な道具一覧」を準備して、泳がせ釣りにチャレンジしましょう!
まずは道糸について解説です。
準備する道糸には「PEライン」がおすすめ。
水の抵抗を受けにくく、感度が良いので「ヒラメの反応があった!」といった水中の情報を把握しやすいんです。
ですがお値段が高いですし、ライントラブルが多くなるといった懸念点も挙げられます。
お値段がお手頃で、ライントラブルが少ないナイロンライン(3号〜4号)を道糸として代用することが可能なので、釣具を準備する際の参考にしてくださね。
続いてチヌバリについて解説です。
チヌバリにはシングルフックやトリプルフックが使用されます。
トリプルフックを使用するとフッキング率が高くなるメリットがあるので、初心者さんは押さえておくと◎です。
ですが、海中で不自然な動きを演出してしまいヒラメに違和感を与えてしまうことも。
釣行日のヒラメの反応から使用するチヌバリを決定してください。
続いておもりについて解説です。
六角おもりは一般的に5号〜10号のものを準備しておきましょう。
使用するおもりの号数を決める際は「潮流」「水深」など釣り場の状況を参考にすることがポイントです。
最後に生き餌について解説です。
泳がせ釣りで使用する生き餌としてアジやイワシが挙げられます。
おすすめはアジをメインの生き餌にすることです。
イワシは餌持ちが良くないのでおすすめできません。
仕掛けを海から回収する際は、こまめに生き餌を交換するよう心がけてくださいね!
サビキ釣りを屈指してアジやイワシを現地で調達してください。
活きの良い生き餌を調達することが、泳がせ釣りで釣果を伸ばすポイントです。
また生き餌が弱らないように「素早く釣り針に付けること」も重要となります。
堤防からヒラメを狙おう!「ぶっこみの泳がせ釣り」がおすすめ!
泳がせ釣りにはさまざまな仕掛けが存在しているんです。
ウキ釣り仕掛け、エレベーター仕掛け、胴付き仕掛けなどが挙げられますね。
仕掛けの種類がこんなにあると「どの仕掛けがおすすめなの?」「堤防でヒラメを釣りやすい仕掛けは?」と迷ってしまう人もいるでしょう。
堤防でヒラメを狙うなら、胴突き仕掛けを使用した「ぶっこみの泳がせ釣り」をおすすめします。
ぶっこみとは、仕掛けに重めの錘を付け海底付近に沈める釣り方のことです。
ぶっこみの泳がせ釣りって海底付近に生息している魚を狙うことに特化しているので、ヒラメのように海底に潜んでいる魚と相性抜群!
初心者さんでも効率よくヒラメを狙えますよ。
基本的にヒラメの反応(アタリ)を待つだけなので「難しいテクニック」が必要ないことも嬉しいポイントです。
仕掛けの準備も非常に簡単です。
道糸の先に「三又サルカン」「ハリス」「釣り針」「捨て糸」「錘(おもり)」を付けるだけでOK!
それでは、ぶっこみの泳がせ釣りに必要なものをご紹介です。
堤防からヒラメを狙う「ぶっこみの泳がせ釣り」に必要なものは?
それでは、ヒラメを堤防で狙うのにおすすめな「ぶっこみの泳がせ釣り」に必要なものを解説します。
下記にこれから紹介する「ぶっこみの泳がせ釣りに必要なもの一覧」についてまとめたので、まずは全体把握をしてみてください。
【ぶっこみの泳がせ釣りに必要なもの一覧】
- 生き餌
- 竿
- リール
- 道糸
- 三又サルカン
- おもり
- 捨て糸
- 仕掛け
必要なもの①:生き餌
必要なもの①として「生き餌」をご紹介します。
ぶっこみの泳がせ釣りをする際は、生き餌として「アジ」「イワシ」といった小魚を用意することが必須です。
生き餌がないと泳がせ釣りを始めることができません。
釣り場に着いたら早速「アジ」「イワシ」を確保しましょう!
アジやイワシなどの小魚は「サビキ釣り」で狙って確保するのがおすすめです。
サビキ釣りはアジやイワシなどの回遊魚を狙うことに特化していて、初心者さんでも簡単に釣ることができます。
必要なもの②:釣竿
必要なもの②として「釣竿」をご紹介です。
堤防でヒラメを狙う際の釣竿は、ある程度「汎用性」があるものなら問題ありません。
ヒラメってそこまで引きが強いわけではないので、使用できる釣竿の自由度が高いんです。
初心者さんはお手持ちの「ショアジギングロッド」「エギングロッド」「磯竿(3号以上)」で、ぶっこみの泳がせ釣りを始めましょう!
これから釣竿を購入する方は「長さ:2.4m〜3m」「錘負荷:最大60号~80号」程度のスペック。
また、食い込みを重視した柔軟な磯竿があると便利です。
ヒラメを堤防で快適に狙うことができると思います。
必要なもの③:リール
必要なもの③として「リール」をご紹介です。
堤防でヒラメを狙う際のリールは、5号程度のナイロンラインが巻けるスピニングリールを用意しましょう。
用意するスピニングリールの目安としては「3000番台〜4000番台」のものが良いと思います。
短めの釣竿には「3000番スピニングリール」、長めの釣竿には「4000番スピニングリール」と使い分けるのが◎
これは余談ですが、釣り場所によって「ヒラメ」はちょい投げ釣りでも釣れることがあります。
ちょい投げ釣りに対応できるよう、釣り糸の量を調整しておいてくださいね。
必要なもの④:道糸
必要なもの④として「道糸」をご紹介です。
道糸とはリールに巻かれている釣り糸(ライン)のことを言います。
堤防でヒラメを狙う「ぶっこみの泳がせ釣り」で使用する道糸として「ナイロンライン(5号以上)」をおすすめします。
ナイロンラインは魚が暴れた時のショックを吸収してくれるので「ラインブレイク」「ライントラブル」を起こす心配が少ないんです。
お手頃価格なので費用対効果がよく、初心者さん入門としても最適な釣り糸(ライン)だと思います。
PEラインを使用しても堤防でヒラメを狙うことは可能です。
ですが価格が高いので、あなたのお財布事情に合わせた釣り糸(ライン)を選んでくださいね。
必要なもの⑤:三又サルカン
必要なもの⑤として「三又サルカン」をご紹介です。
三又サルカンは道糸にオモリや仕掛けなど複数のアイテムを付けたいときに活躍します。
仕掛けの準備や調整が楽になるので、初心者さんは必ず準備しておくと◎
釣具を準備する時間を短縮することができると思います。
また三又サルカンを使用することで釣り糸(ライン)のヨレが減り、仕掛けの動きがスムーズになることも嬉しいポイントです。
必要なもの⑥:おもり
必要なもの⑥として「おもり」をご紹介です。
おもりは仕掛けを海中に沈めるために必要不可欠。
堤防でヒラメを狙う「ぶっこみの泳がせ釣り」使用するおもりの目安として「10号~30号程度」がおすすめです。
おもりの重さは潮流や釣りをするポイントの状況に合わせて設定してください。
仕掛けが海に沈み込みやすく、引き波に流されない重さのオモリを選べたら◎です。
具体的には潮の流れが強いなら「重めのおもり」、浅い釣り場では「軽いおもり」を選ぶようにしましょう。
軽めのおもりは重いおもりに比べ「水流の中で自然に動く生き物」に近い動きを演出することが可能です。
このことは釣果に繋がる知識として押さえておくと良いと思います。
自然界においてヒラメは「水流の中で自然に動く生き物」を餌として捕食することが多い魚なんです。
「水流の中で自然に動く生き物」を演出できる軽めのおもりを屈指して、ヒラメに違和感を与えずに釣果を伸ばしましょう!
必要なもの⑦:捨て糸
必要なもの⑦として「捨て糸」をご紹介します。
捨て糸とは「根掛かり」した時に仕掛け全体を逃すことを目的におもりに結ぶ細い糸のことです。
ぶっこみ仕掛けは水底(ボトム)付近を狙うのに特化しているので「根掛かりがしやすい仕掛け」とも言えます。
捨て糸にこだわることで、根掛かりした際も「すべての仕掛けを失うトラブル」を避けることに繋がりますよ。
堤防でヒラメを狙う際には、捨て糸は三又サルカンとおもりを繋ぐために使用されます。
ポイントとして捨て糸は必ず「道糸(リールに巻かれている釣り糸)より細いものを使用する!」ことを念頭に入れておきましょう。
細い捨て糸を使用することで、根掛かりしたときロストする仕掛けをおもりだけにしてくれます。
道糸にナイロンライン5号を使用した際の捨て糸の目安として、ナイロンライン2号~3号程度のものを使用するのがおすすめです。
一般的に捨て糸には、ナイロンライン3号~4号が推奨されいることも押さえておくと◎
再び仕掛けを準備するのって時間と労力を使うので大変疲れるんです。
初心者さんなら尚更疲れてしまうかもしれません。
しっかりと捨て糸を用意することで、根掛かりが起きた際のリスクを減らしておくといいですね。
必要なもの⑧:仕掛け
必要なもの⑧として「仕掛け」をご紹介です。
生き餌を付けるため仕掛けには、ハリス(道糸と釣り針を結ぶ糸)と釣り針が付属しているものが必要となります。
堤防でヒラメを狙うなら釣り針が2本付いてる仕掛けを使用するのが望ましいです。
釣り針が2本付いてる仕掛けを使用すると釣り針と釣り糸が絡まるといったライントラブルが起こりやくなります。
初心者さんは「釣り針が1本付いている仕掛けを使用してOK」ということを知っておきましょう。
もちろん、釣り針が1本付いている仕掛けを使用してもヒラメを釣ることは可能です。
仕掛けは自作することも可能ですが、制作に時間がかかりますし、出費も多くなることがあります。
これから「ぶっこみの泳がせ釣り」を始める初心者さんは、市販で購入できる仕掛けを使用するのがおすすめです。
釣具店はもちろん、ネット通販でも購入することが可能。
市販で購入できる仕掛けにはおもりと三又サルカンがセットで付いてきます。
これが本当に便利で、仕掛けを買ったらすぐにぶっこみ釣りを始められるんです。
釣具の準備をスムーズにおこない、ストレスを減らし快適に釣りを楽しみましょう!