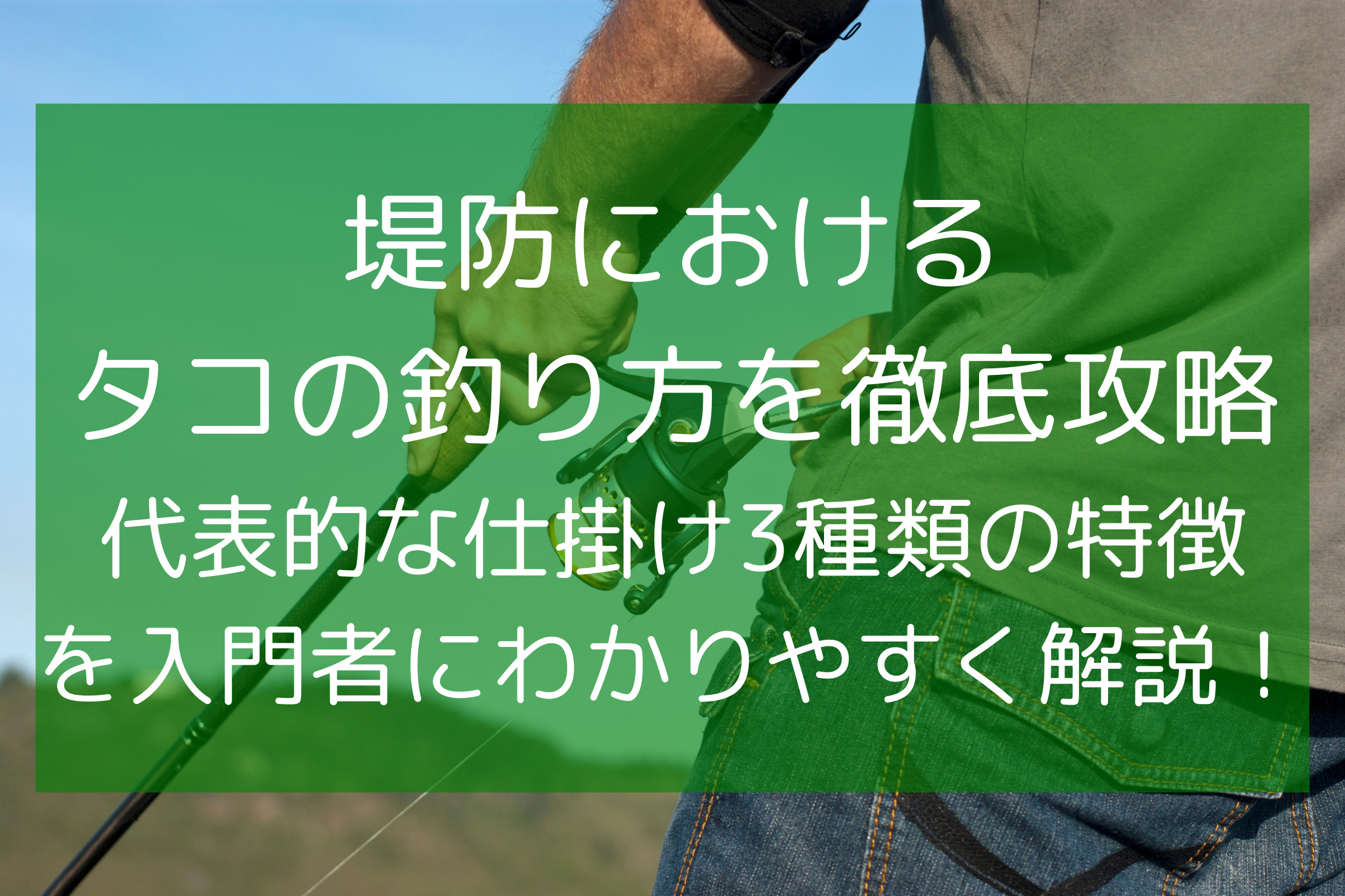Contents
- 1 堤防で楽しむ「タコ釣り」が面白いことをご存知ですか?
- 2 マダコの生態について!
- 3 タコ(マダコ)釣りを楽しむ「時期」について!
- 4 タコ(マダコ)が「釣れる時期」「釣れる時間帯」は?
- 5 タコ(マダコ)が釣れるポイントや場所は?
- 6 タコの釣り方①:タコエギについて解説!仕掛けやタックルなども
- 7 タコの釣り方②:テンヤについて解説!仕掛けやタックルなども
- 8 タコの釣り方③: タコジグについて解説!仕掛けやタックルなども
- 9 タコの釣り方「コツ3選」とは?
- 10 タコの「持ち帰り方」「下処理」について!
- 11 タコ釣りをする上で、大切な「注意点」を把握しよう! あらかじめ「漁業権」を調べたら◎
- 12 大切なことは「シンプル」な考え方! タコ釣りにチャレンジしよう!
堤防で楽しむ「タコ釣り」が面白いことをご存知ですか?
堤防で楽しむ「タコ釣り」が面白いことをご存知ですか?
近年は、関西地方を中心に大盛り上がりしてますね!
「初心者さんでも、簡単に釣れる!」「釣り方が難しくない!」ので、タコ釣りは盛り上がるのでしょう。
「堤防からタコを釣る方法は複数存在している」ので注意も必要です。
タコ釣り初心者さんは「どの釣り方が良いかな?」と迷ってしまうかもしれません。
それぞれの釣り方で「必要な釣り道具(タックル・ルアーなど)」も違うので、慣れるまで結構大変..。
今回の記事では、堤防からタコを狙える「タコエギ」「テンヤ」「タゴジグ」を使用した釣り方を深掘ります。
ほかにも「タコ釣りに必要な知識」を詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください♪
タコは身近な堤防にも潜んでいます。
誰でもお気軽に「タコ釣り」にチャレンジできるのです!
マダコの生態について!
堤防から狙うメインターゲットは「マダコ」になります。
今回の記事における「タコ=マダコ」と考えてもらってOK。
大型個体だと「3kg以上」になる場合も!
たこ焼き1個には「約5g」のタコが使用されるので、なんと「たこ焼き=600個分」の重さになります。笑
マダコの生息域は?
マダコは日本の広い地域に分布しています。
ですが、低水温に弱いので「北海道」「本州の北部」の沿岸には生息していません。
北限で言うと青森までマダコが生息しているのです。
マダコは膝下くらいの浅瀬にも潜んでいますし。
水深40m程度の深い場所まで生息しているので、見つけるのが大変。
マダコの活動について
活動する時間帯も「夜行性」なので、日中は活動を控え「岩礁の隙間」に隠れて生活します。
夜になると主食である「甲殻類(カニなど)「二枚貝」「小魚」を捕食するため、活動的に動き出しますよ。
マダコは頭が良い生き物!
タコは知能指数が高い生き物。
体表が色素細胞で覆われているので「周囲の環境に溶け込む」ことが特技になります。
カメレオンのように擬態化して、外敵から身を守るのです。
マダコは高価食材!
余談ですが、国産のマダコは流通が少ないので「市場価格=高価」であることがイメージしやすいかと。
そんな漁獲量が少ない、マダコが堤防から釣れるのですよ?
今すぐ「堤防で楽しむタコ釣り」を始めないと損です!
ぜひ、国産マダコでしか味わえない「歯応え」「弾力」「甘み」「強い旨味」を堪能してください♪
タコ(マダコ)釣りを楽しむ「時期」について!
それでは「マダコが釣れる時期」を解説です。
「春」「夏」「秋」「冬」と四季ごとに、それぞれの特徴を見ていきましょう!
春は「活性が低い」時期
春のマダコは活性が低いです。
これは「水温が低い」ことが原因になります。
活性が低いので「アタリ(反応)が少ない」と考えてくれてOK。
春に初心者さんが、タコ釣りに入門するのはおすすめできません。
タコ釣りハイシーズンである「夏」に入るまで辛抱しましょう!
ここで、押さえてもらいたいポイントがあります。
それは「春もマダコは釣れる」ということ!
タコが潜んでいそうな「岩礁帯」「岸壁」を丁寧探り、狙うと◎です。
夏は「ハイシーズン」で釣りやすい時期
夏はタコ釣りのハイシーズンです。
「水温が上昇するので、タコの活性が高まる」ことが理由になります。
「6月から8月」にかけてマダコが1番釣れるので、初心者入門におすすめ!
産卵期を終え、生まれたばかりのマダコ(新子サイズ)を数釣りできちゃいますよ♪
大型のタコは卵を守っていたり、体力が落ちるので活動的ではありません。
全く釣れないことはありませんが..。
「夏=大型のタコは釣れにくい!」と考えてくれてOKです。
秋は「引き続きマダコが狙える」時期
秋もマダコを狙うことが可能です。
夏に生まれた新子も「200g→400g」程度まで成長するので、まだまだタコ釣りを楽しめます♪
ですが、秋口になると少しずつ水温が下がるのも事実。
水温が下がると、タコは深場に移動するので..。
夏に比べると「アタリが少ない?」と感じるかもしれません。
冬は「マダコが狙いづらい」時期
冬はマダコを狙うのが難しい時期です!
基本的に「冬=タコ釣りをする人が少ない」と考えてくれてOK。
初心者さんが、冬からタコ釣りを始めることはおすすめできません。
一方「大物狙い」を期待するなら、この季節がおすすめ。
タコの寿命は1年〜2年程度なので「冬を乗り越える(越冬)マダコ=大型」になるケースが多くあります。
具体的に「大きさ=60cm程度(腕含め)」「重さ=2kg~3kg」まで、成長するのです。
大型のタコを狙うなら「水深が深い場所」を狙うと◎
タコは水温が下がると、水温が安定している「深場」移動するためです。
ハイシーズンには「地域差」が存在する!
タコ釣りのハイシーズンには「地域差」が存在します。
ハイシーズンは「産卵後」と考えてくれてOKです。
産卵後は新子サイズ(小型〜中型)を数釣りできるチャンス♪
初心者さんがタコ釣りデビューするなら、このタイミングが良いかと。
基本的にタコの産卵ピークは、水温が高くなる「夏の時期」になります。
「産卵期には地域差がある」ことに注意しましょう!
地域により産卵期が異なるため、タコ釣りハイシーズンに「地域差」が生まれるのです..。
温暖な場所(九州など)や黒潮の影響を受ける海域(南岸沿い)では、春から産卵ピークに入るケースも。
早い段階で産卵ピークになるので、初夏からマダコが釣れ続け始めますよ!
一方、寒い地域(日本海や瀬戸内海など)・雪解け水が流れ込む海域だと、海の温度が低下しますね。
産卵ピークが遅くズレてしまい、秋ごろがタコ釣りハイシーズンになるのです。
あなたが住んでいる地域の特徴を把握するのも「タコ釣りを楽しむ」ために重要です。
インターネットで「お住まいの地域名 タコ釣り ハイシーズン」と検索しておくと◎
タコ(マダコ)が「釣れる時期」「釣れる時間帯」は?
タコは基本的に「1日」「1年」を通して狙えます。
いつでも釣れるチャンスがあるのは嬉しいですが..。
釣り人なら「少しでも釣果を伸ばしたい!」と考えてしまいませんか?
この見出しではタコが「よく釣れる時期」「よく釣れる時間帯」をご紹介です。
上記のタイミングを押さえるだけで、タコが釣れる確率を高められるでしょう!
基本的にマダコは夜行性。
つまり「暗い時間帯」がよく釣れるのです。
初心者さんがタコ釣りをするなら「朝マヅメ」「夕マヅメ」時がおすすめ!
タコを釣りやすいですし、真っ暗な夜に比べて安全性が高いのです。
夜は転落や落水が怖いので、釣りに慣れるまでは「朝マヅメ」「夕マヅメ」を狙ってタコ釣りを楽しみましょう♪
よくタコ(マダコ)が「釣れる時期」は?
タコがよく釣れる時期は「5月〜9月頃」です。
水温が上がり、タコの活性が高まることが理由。
水温が安定している場所なら「真冬(1月〜2月)」でもタコは釣れますが..。
初心者さんがタコ釣りを始めるなら、初夏が最適だと思います。
なかでも「6月〜8月頃」がおすすめです。
この時期は産卵後に生まれた「子タコ」が多く生息していて、最もよく釣れるシーズン!
タコの数自体が多いので、誰でも釣果を期待できるでしょう。
よくタコ(マダコ)が「釣れる時間帯」は?
タコがよく釣れる時間は「夜」です。
タコは夜行性が強い生き物なので、暗いほど釣果を期待できます。
シンプルに「夜>薄暗い時間帯(朝・夕)>日中」に釣れやすいと押さえてOK。
上記にもありますがタコは「夜」に1番釣れる傾向があります。
ほかにも「朝マズメ」「夕マズメ」など、薄暗い時間帯も活動的です。
効率よくタコを狙うなら、これらのタイミングがベストかと♪
日中もタコは釣れますが..。
活性が低かったり、物陰に潜んでいるケースが多いので、釣果を出すのは難しい場合も..。
ですが「日中しか釣りに行けない」人もいるでしょう。
そんな時はタコが好み潜むような障害物周りを丁寧に探ると◎
タコの目の前に餌を持っていければ、本能を刺激できタコがヒットしてきます!
「雨」が降ったら注意!
タコ釣りをする上で「雨」には注意。
タコには「真水を嫌う」という性質があるので、雨の日や雨が降った後は「釣果」が伸びにくいです。
特に水量が少ない「河口付近」「浅瀬」などのポイントは、雨の影響を強烈に受けます。
なぜ、雨が降るとタコが釣れなくなるのでしょうか?
これは、タコが真水(雨)の影響が少ない「深場に移動する」ことが理由になります。
あらかじめ「釣行日の天気」を把握しておくと◎です。
「また別日にするか〜」と言った感じで、対策ができますね!
夜行性のタコ(マダコ)は「日中(昼間など)」も釣れる?
タコは「夜行性」です。
暗くなってから捕食活動を開始します。
ここで押さえたいのが「タコは日中も捕食する」ということ。
実は、障害物に身を隠しながら「小魚」「甲殻類」を捕食しているのです。
捕食活動をするなら、日中でもタコが釣れるチャンスはあります。
釣り方に工夫を加えると良いのです!
タコの活性が高い「暗い時間帯(マズメ・夜)」は「広範囲を探る釣り方」が最適ですが..。
タコの活性が低い「日中」に同じ釣り方をしても、効率が悪すぎますね。
このことを踏まえ、日中にタコを狙うなら「障害物近くを細かく・丁寧に探る」釣り方をすると◎です。
タコが身を隠しやすいポイントを見つけ出せたら、確実に釣果が上がりますよ!
タコ(マダコ)が釣れるポイントや場所は?
タコ(マダコ)が釣れる場所をご紹介していきます。
堤防で行うタコ釣りで釣果を伸ばすなら「タコの隠れ家」を見つけるのが、1番効率的です。
この見出しでは、身近にある「タコが釣れる1級ポイント(障害物・エサが豊富な場所など)」をピックアップしていきます。
あなたの環境に最適な場所を見つけてください♪
釣れるポイント①:壁際(防波堤など)
釣れるポイント①として「壁際」をご紹介です。
定番中の定番ポイントなので、タコ釣りビギナーは押さえましょう!
壁際はタコの餌が豊富に生息しています。
貝類や甲殻類(カニなど)、小魚が多いんです。
これらの餌を捕食するため「壁際=エサ場」になる確率が大!
意外と見落としがちですが「壁際から少し離れた海底付近」も狙い目です。
具体的には2m〜3m前後離れたポイントが◎
堤防の底には敷石などが積み上げられているので、タコが身を潜めやすくなります。
他のアングラーと差を付けるなら堤防の「繋ぎ目」「割れ目」「スリット部分」もチェック!
これらの場所は「エサが集まりやすい」かつ「身を隠すのに最高」なので、タコにとって格好の住処になります。
見逃さず、確実に探りたいものです。
釣れるポイント②:沖の沈み根
釣れるポイント②として「沖の沈み根」をご紹介です。
タコ釣りをするなら沖もチェックすると◎
見落としがちですが、沖にもタコが身を潜めやすい「障害物(岩や捨て石など)」が形成されています。
目視で見つけるのは難しいので、結構レベルが高いお話です。
ですが、他のアングラーさんと確実に差を付けられるはず!
海中にある目立たない障害物を少しずつ把握していくのです。
具体的には、仕掛けを用いて海底を引いてきましょう。
根掛かりに注意してくださいね。
仕掛けを引いていて、手元に「何か引っかかる」「違和感がある」なら、それは障害物です!
高確率で「タコの住処」になるので、忘れず探りを入れてください。
釣れるポイント③:石畳
釣れるポイント③として「石畳」をご紹介です。
石畳は、タコ釣りをする上で超1級ポイントになります。
「身を隠せる隙間が豊富」「エサが豊富に生息している」など、石畳が超1級ポイントである理由を挙げたらキリがありません。
タコが潜みたくなる「条件」が多く揃っている反面。
石畳を狙う時は「根掛かりが多い」のが難点になります。
タコエギなどの仕掛けをロストするトラブルが増えるので、気を付けてくださいね。
まだ道具が少ない初心者さんが、石畳を狙うにはハードルが高いかもしれません。
やや上級者向けの釣り場と言えますね..。
釣れるポイント④:沈み瀬や岩礁
釣れるポイント④として「沈み瀬」「岩礁」をご紹介します。
身を隠しやすい「沈み瀬」「岩礁」は、タコが潜んでいる確率が非常に高いです。
目視できないので、初心者さんにとってハードルは高いですが..。
沖に形成されている「沈み瀬」「岩礁」を把握しておくと、他のアングラーに差を付けられます。
個人的に「沈み瀬」をマップアプリで見つけておくのがおすすめ。
航空写真を見るとわかりやすいので、釣り場に行く前にチェックしましょう!
余談ですが、地磯が隣接している「堤防」も積極的に狙いたい、好ポイントになります。
タコの釣り方①:タコエギについて解説!仕掛けやタックルなども
堤防といった陸からタコを狙う釣り方には、主に「タコエギ」「テンヤ」「タコジグ」を使用する3種類の仕掛けが使われることが多いです。
今回の記事では、これら3種類の特徴や釣り方について解説していきます。
まずは堤防における「タコエギ」を使用した釣り方からご紹介です。
タコエギとは?
タコエギとはタコ釣りのために開発された専用のエギ(擬似餌)のことを言います。
そんなタコエギを使用した釣り方はエサを使用しません。
タコエギをルアーのように誘いながらタコを釣り上げていきますよ!
小さいタコから大きいタコまでよくアタリ、よく釣れることが魅力的です。
初心者さんやルアーマンの方でもお手軽に始めやすく、堤防からタコを狙う釣り方として最も人気のある釣り方だと思います。
イカ用のエギとタコ用のエギの違いは?
形状が似ているのでパッと見た感じ「イカ用のエギ」「タコ用のエギ」の違いはわかりません。
下記に「イカ用のエギ」「タコ用のエギ」の違いをまとめてみたので、釣り知識として押さえておくと良いかもしれません。
【イカ用のエギ・タコ用のエギの違い】
- タコエギは根掛かり防止のため上向きの掛け針が付いている。
※イカ用のエギは全方向に向いた細いカンナ状(傘のように広がった形状)の釣り針が付いている。 - タコエギはブレードのような装飾が付いているのでキラキラしている。
- タコエギには音でタコを寄せるためラトルが内蔵されていることが多い。
- タコエギはイカエギに比べ重いので沈みやすい。
タコエギを使用した釣り方は?
タコエギを使用した釣り方では、堤防の基礎部分(堤防直下、周辺地盤のこと)や石畳(いしだたみ)を狙うことが多いです。
また堤防から沖にある障害物に向かい遠投することでもタコを狙うことが可能になります。
タコエギは投げてから水底(ボトム)を引きずるような使い方にも向いていますよ。
基本的に水底(ボトム)付近を狙う釣り方なので、タコエギが浮き上がってこないよう注意しましょう!
タコエギが浮き上がってしまう時は?
潮の流れが速い場所では、意識してもタコエギが浮き上がってきてしまうことも考えられます。
そんな時はスナップにタコエギとオモリを一緒に付けてみてください。
オモリを付けることで沈下速度が早くなり、潮の流れが早くても浮き上がりにくいので使いやすいですよ!
タコエギにアピールを加えたい時は?
タコは派手なルアーに興味を示しやすい傾向があります。
釣果を伸ばすためスイベル(複数のルアーを付けられる)を使用しタコエギを2つ~3つ同時に泳がせるテクニックも存在していますよ。
初心者さんは、ぜひタコエギのアピール力を高めるため「ブレードを使用する」テクニックを押さえておくと◎です。
下記に「タコエギで使用するタックル一例」についてまとめたので、チェックしてみてください。
【タコエギで使用するタックル一例】
- タコエギ専用ロッド
- スピニングリール4000万
- 道糸:PE2号〜3号
- リーダー:フロロカーボンライン8号〜12号
- タコエギorテンヤ
タコエギの仕掛けは?
仕掛けとしてタコ専用のエギを用意するのが良いですよ。
堤防でタコを狙う時は基本的に「水底(ボトム付近)」を狙います。
イカ用(アオリイカなど)のエギは沈むのが遅いので、手返しが悪くなってしまうんです。
またカンナが小さいのでタコ釣りには適していません!
もしかしたら「タコ用のエギを購入しよう」「どのタコ用のエギがいいのかな?」と迷う方もいるかと思います。
タコエギ選びで迷ったらデュエル(duel)から販売されている「タコやん」の購入を検討してみても良いかもしれません。
ルアーボディに浮力があるので根掛かりしにくいといった魅力があります。
初めてのタコエギとして初心者さんでも「使いやすさ」を実感できるでしょう。
タコエギのタックルは?
続いて「タコエギのタックル」についてご紹介します。
これから堤防でタコ釣りを始める人は必見の内容です!
ロッドについて
準備するべき釣竿として「タコエギ専用ロッド」がおすすめです。
長さは7ft程度あると十分だと思います。
タコって堤防や岸壁に吸盤で張り付くことが多いんです。
結構強い力でタコは障害物は張り付くので、力負けしないような(引き剥がせる)バットパワーや強度を兼ね備えた釣竿を準備しましょう!
ロッドに高い負荷が加わっても安心して釣りを楽しめると思います。
タコエギ専用ロッドの購入に対して「出費が厳しい..」と感じる人もいるかと思います。
タコエギでタコを狙う場合、ある程度硬いルアーロッドなら代用することも可能です。
代用可能なルアーロッドとして、エギングロッド(硬め)、シーバスロッド、ショアジギングロッドが挙げられます。
すでにお手持ちの方は、ぜひタコエギを使用して「堤防からのタコ釣り」を楽しみ尽くしましょう!
リールについて
スピニングリール・ベイトリールどちらのリールでもタコエギを使用することは可能です。
タコ釣りビギナーの方は、ぜひタコエギを投げやすいスピニングリールを選んでみてください。
選ぶべきスピニングリールのサイズ(番手)は3000番〜4000番を目安にすると良いですよ!
リールにパワーやドラグ力が欲しい方は4000番以上のスピニングリールを選んでも問題ありません。
あなたの選んだスピニングリールに1号〜3号程度のPEラインを基準として100mほど巻いておきましょう。
PEラインは根ズレに弱く、すぐにラインブレイクしてしまいます。
ラインブレイクを防止するためにリーダーとして、フロロカーボンライン(8号~12号程度)を用意しておくのが良いですね。
タコエギの釣り方は?
タコエギの釣り方は基本的に海底(ボトム)を狙います。
まずはタコエギを狙ったポイントにキャストしてください。
キャスト後、タコエギが着底したことを確認できたら、海底(ボトム)の変化を感る程度のリーリングスピードで引いてきます。
タコエギを引いてくる時は「ズル引き」をしながら「シェイク」を加えるアクションが効果的です。
またタコが潜んでいそうなポイント付近でタコエギを止めてシェイクするのも◎
海底(ボトム)からタコエギが離れてしまうとタコの反応(アタリ)がほとんど無くなってしまうので注意しましょう。
初心者さんは「タコエギは海底(ボトム)付近を泳がせること」に意識を集中しながら誘いを加えてくださいね。
タコが好んで住み着く好ポイントとして、海底に障害物や石が多い場所が挙げられます。
竿先に「異物感」「不規則な揺れ」「引っ張られ感」といった変化が感じられた場合、海底に障害物や石が多いと判断して問題ありません。
海底に障害物や石が多い場所ではあまりタコエギを移動させないこともテクニックになります。
タコエギを動かさず、その場で竿先を小さい幅(10cm程度)でチョンチョンと操作してアクションを加えてみてください。
タコを効果的に誘い出せますよ!
誘いを繰り返していて「穂先が戻らない」「竿先に重さや違和感を感じる」「引っ掛かったような感覚」があったら、タコのアタリである可能性が高いです。
タコエギにタコが抱いていると確信できたら、糸フケを取り大きくアワセを行いましょう!
糸フケを取る時は、釣り糸が緩まないように「ラインテンション」をかけたまま一定のリズムでリールハンドを巻き取ります。
また、アワセの動作は釣竿を大きく上げて行うと◎
しっかりとタコに釣り針を貫通させて、フッキングを成立させてくださいね。
タコをタモ網に取り込むときは臨機応変な対応が必要となります。
タコは堤防、岸壁、岩などに吸盤で引っ付くことがあるので「根掛かりしたかな?」と不安になることもあるんです。
そんなときは「タコは障害物に引っ付くから根掛かりじゃない!」「ちゃんとタコがヒットしたんだ!」とワクワクドキドキしながら、タコとのファイトを存分に味わい尽くしましょう。
タコの釣り方②:テンヤについて解説!仕掛けやタックルなども
テンヤは板のような部分(餌を固定する台座)に大きな針を取り付けた仕掛けになります。
この板のような部分(餌を固定する台座)にカニやイワシなどのエサを巻き付けることでタコを狙うんです。
商品によってはカニなどを模したルアーが付いているテンヤが販売されていることもあります。
餌を巻きつける手間がかからないのが嬉しいですね。
餌を固定する以外に、板のような部分自体にはオモリの役目が兼ね備えられています。
仕掛け自体がシンプルなこともあり、自作する釣り人が多い印象です。
テンヤの使い方は?
重さのあるテンヤの使い方はタコエギと同じです。
海底(ボトム)を引きずってタコを狙っていきますよ!
タコエギに比べるとテンヤは「根掛かり」に強い構造をしているので、安心して海底(ボトム)を引いてこれると思います。
テンヤにはエサを付けるのでタコの嗅覚に直接刺激を与えることが可能です。
タコエギとは違った本能に訴えかけるので、タコの食いつきや良かったり、長い時間アタリが続くこともあります。
ですが、タコを狙う釣り方って必ずしも「生餌だから釣れる!」といった保証はありません。
ルアー(擬似餌)を屈指してタコを狙う方が有利な状況も数多く存在しているのが事実です。
ぜひ、タコ釣りを始める際の参考にしてみてくださいね。
テンヤで釣れるタコのサイズ感は?
テンヤはタコエギよりも仕掛けが大きいです。
仕掛け自体が大きいので、小さいタコは釣れにくい傾向にあります。
大型のタコを狙えることもテンヤの魅力ですね!
あなたが「大物狙いを楽しみたい!」と考えているなら、ぜひテンヤを屈指したタコ釣りを始めましょう。
忘れられない1匹に出会えるかもしれませんよ!
テンヤの仕掛けは?
仕掛けとして「タコ専用のテンヤ」を準備しておきましょう。
一般的に堤防でタコを狙う際に使用するテンヤの重さは「10号〜20号程度」がおすすめです。
板のような部分(餌を固定する台座)に巻きつける生エサとしてアジ、カニ、手羽先、豚の脂身などがあります。
多種多様な生エサが存在していますが、最強の生エサは「カニ」です。
タコは自然界においてカニを捕食することがほとんど。
手や足が付いているカニを使用するとタコに対して猛烈にアピールすることができますよ!
生エサに苦手意識がある方はカニのオモチャ(ビニール製)をテンヤに巻きつけることも可能です。
ですが、生エサに比べるとタコに対するアピール力は少なく、食いつきがあまりよろしくありません。
テンヤのタックルは?
釣竿を使ってテンヤを使用する際は、タコエギでご紹介したタックルと同じものを使用して問題ありません。
ですが、釣竿を使わず手で釣り糸を操作してタコを狙う「手釣り」を行うなら話は別です。
手釣りで堤防からタコを狙うなら「ボビン(糸巻き器)」を用意すると◎
ボビン(糸巻き器)に25号程度の太い糸を巻き付けておくと、安心してタコとのファイトを楽しめるでしょう。
また根掛かり対策に「リーダー」付けるようにしてください。
根掛かりが起こった際のロストを最小限にすることが可能となります。
ロッドについて
長さは7ft程度のタコエギ専用ロッドを準備しておけば十分です。
問題なくテンヤを使用して堤防からタコを狙うことができるでしょう。
タコエギ専用ロッド以外のルアーロッドで流用することも可能です。
具体的には硬めのバスロッドやショアジギングロッドがおすすめ。
ですが、重いテンヤ(15号以上)を使用してタコを狙う際は、ベイトロッドを準備してもらいたいです。
ベイトロッドはパワーがあるので、重いテンヤを初心者さんでも快適に扱えると思います。
リールについて
準備するべきリールとして「ベイトリール」をおすすめします。
糸巻き量が多く、ドラグ力もあるので「タコの強い引き」にも負けません!
ベイトリールにはPEライン(2号〜3号程度)を100mほど巻いておくと、根掛かりなど「ライントラブル」があっても安心です。
堤防でのタコ釣りを中断ぜず、継続して楽しむことができますよ。
テンヤを使用した釣り方は仕掛けを投げる必要があります。
仕掛けを投げる際にブレーキ機能が付いたベイトリールを使用していると「飛距離」が出せないことも!
ブレーキ機能の調整って難しいんです..。
なかなか上手にキャストを行えないと「タコ釣りにストレスを感じる」人もいるかと思います。
飛距離を出したい方は、ぜひベイトリールを選ぶときの参考にしてくださいね。
テンヤの釣り方は?
堤防からタコを狙うテンヤ釣りには「釣竿を用いる釣り方」と「ボビン(糸巻き器)を利用した手釣り」の2パターンが存在しています。
それぞれの釣り方についてみていきましょう!
釣竿を用いるテンヤ釣りについて
まずは「釣竿を用いる釣り方」について解説です。
実は「釣竿を用いたテンヤ釣り」と「タコエギを使用した釣り」ってほとんど釣り方に差がないんです。
ですが、タコエギを使用した釣り方のおさらいだと思って読むことで「釣り知識」が深まるはず。
堤防で釣竿を用いたテンヤ釣りをおこなうなら、タコエギと同じように「海底(ボトム)」を狙いましょう。
テンヤが着底したことを確認したら、あとは海底(ボトム)をゆっくり引きずりながら、リールハンドルを巻くだけです。
この時テンヤが浮き上がらないように注意を払うことが重要ですよ!
タコがテンヤに抱きつき押さえつけてくるので、釣竿に重みが増したり、ググッと引っ張られるような感覚が手元に伝わります。
あとは「タコがテンヤに抱きついた!」と確信でき次第、糸フケを取り、大きくアワセましょう!
大きく合わせることで、しっかりとタコに釣り針を貫通させることができますよ。
ボビン(糸巻き器)を利用した手釣りについて
続いて「ボビン(糸巻き器)を利用した手釣り」について解説です。
手釣りをおこなう時は、仕掛けを防波堤の岸壁やテトラの穴などに沿って落とします。
着底を感じ取れたら「チョンチョン」とアクションをテンヤに加えてタコにアピールをして釣果を狙ってくださいね。
堤防際を移動しながら「タコがいないかな?」と探る際には、テンヤが浮いてこないよう注意です。
テンヤを浮き上がられないコツとして「潮の流れに沿って移動する」ことが挙げられるので、手釣り初心者さんは押さえておくと◎
しっかりと海底(ボトム)を取ることで、効率よくタコにアピールし続けましょう!
タコの釣り方③: タコジグについて解説!仕掛けやタックルなども
タコジグとはオモリが仕込まれている擬似餌で、タコのような形をしています。
そんなタコジグを使用した釣り方は、タコエギやテンヤを使用した釣り方とは全く異なるんです!
タコジグを使用した釣り方は?
タコジグを使用した釣り方は堤防の岸壁といった壁際を垂直方向(縦方向)に狙うことに特化しています。
基本的に仕掛けを投げることはしません。
ひたすら足元に潜む(堤防の岸壁に付いている)タコを縦に探り狙って行くんです!
タコジグの効果的な使い方は?
タコは目立つものに惹かれる傾向がありましたね。
1個のタコジグを使用するのでなく、2個~3個と複数のタコジグを連結させてタコを狙うことでアピール力を高めると効果的な場合がありますよ!
タコジグを使用した釣り方では、一応「タコベイトを海に投げ入れる→海底(ボトム)にいるタコを誘う」ことも可能なのですが..。
タコジグに付いている釣り針は全方位に向いているので「根掛かり」が起こりやすくなります。
あなたが「堤防の岸壁でなく海底(ボトム)を狙いたい!」と考えているなら、先ほどご紹介した「タコエギ」「テンヤ」にルアーを変えるのが無難かもしれません。
【タコジグタックル一例】
- 胴がしっかりしていてパワーのある釣竿
- 小型で軽量なリール
- PEライン6号以上orフロロカーボンライン10号〜12号
- タコジグ(2個、3個と連結させてOK)
タコジグの仕掛けは?
タコジグには単体のもの、2つ以上のタコジグが連結されたものが販売されています。
2つ以上のタコジグが連結されたタゴジグは1度に広い水層(レンジ)を探れますし、アピールも強いので効率よくタコを狙えますよ!
ですが根がかりするリスクが高かまるので、その点は注意しましょうね。
タコジグで使用されるカラーは赤、ピンク、オレンジなど派手目なものが主流。
タコジグの購入を検討している方は「基本的どんなカラーでも釣れる!」ということを知っておくと◎
カラー選びで迷うことが少なくなります。
あなたが「釣れそう!」と思えたカラーをチョイスしてから堤防に向かいましょう!
タコジグのタックルは?
続いて「タコジグのタックル」についてご紹介します。
これから堤防でタコ釣りを始める人は「必見の内容」です!
ロッドについて
タコジグを使用した釣り方を快適に楽しむなら、強く硬い釣竿を選びましょう!
バットパワーがあると岸壁についたタコを引き剥がしやすいですよ。
またタコジグを使用した釣り方って遠投する必要がありません。
基本的に足元を狙うことが多いので、初心者さんは短い釣竿のほうが扱いやすいかと思います。
何度もお伝えしていますが、岸壁にタコが張り付くと「非常に大きな負荷」が釣竿にかかるんです。
タコの強い負荷に負けないよう安価でも良いのでバットパワーがあり、折れにくい「タコ竿」を用意しておくことをおすすめします。
「お金的にタコ竿を準備できない..」「新しい釣竿を買うのはちょっと..」といった感じで、釣具の新調に抵抗がある人もいるかと思います。
その場合は、すでに手持ちのビッグベイトロッド(バス用)、ジギングロッド(青物用)、船のタコ釣り用ロッド、船竿なら流用することが可能です。
タコの誇る強烈なパワーに負けずに、堤防でタコを狙うことができますよ。
リールについて
タコジグを使用した釣り方はスピニングリール・ベイトリールどちらのリールを使用しても問題なく楽しめます。
ですが基本的にタコジグは投げる必要がなく、縦の動き(水面に対して垂直な動き)を中心に堤防からタコを釣ることが多いです。
上記のことを考慮するなら、釣り糸の出し入れがしやすく手返しの良い「ベイトリール」をおすすめします。
スピニングリールよりも巻上げ力が強いので、岸壁についたタコに力負けすることも減らせますね。
※巻上げ力とは、リールハンドルを回した時に釣り糸を「どれだけ強く?」「どれだけ早く巻き取れる?」のか表す指標。
お手元にベイトリールが準備できたら、PEライン(太さ:3号〜5号程)を50mほど巻いておきましょう。
タコジグを使用した釣り方は足元にいるタコを狙うので、あらかじめ巻いておく釣り糸の量は少なくても問題ありません。
注意点として「釣り糸(ライン)が岸壁に擦れるシーンが多いこと」が挙げられます。
擦れに弱いPEライン単体でタコジグを使用した釣り方に望むと「ラインブレイク」が多発してしまうでしょう。
ラインブレイクを避けるためにPEラインには、必ずリーダーとしてフロロカーボンライン10号~12号を結ぶようにしてくださいね。
リーダーを準備することに抵抗がある方は、思い切って太めのPEライン(太さ:6号)をベイトリールに巻いておくことをおすすめします。
これからタコジグ専用リールの購入を検討している方は、「強度の高いジギングリール」を選ぶのが良いかと思います。
ジギングリールには大型魚の引きに対抗する「耐久性」が備えられているので、大型のタコが岸壁に付いた時も安心です!
岸壁から大型のタコを引き剥がすときに生じる「大きな負荷」にも耐えられるでしょう。
またドラグ力があり堅牢なこともおすすめしたい理由です。
タコジグの釣り方は?
タコジグを使用した釣り方は、堤防の壁際や岸壁スレスレに沿ってタコジグを落としていくのが基本です。
丁寧にゆっくりと「堤防の壁際や岸壁付近にタコがいないか?」探ぐりましょう。
タコジグを使用した釣り方で意識するべきポイントは?
釣果を伸ばすには「同じ釣り場所で釣り続けないこと」を意識するのが大切です。
少しでも「タコの反応(アタリ)がないな〜」と感じたら岸壁沿いを歩いて移動しましょう。
移動を繰り返しタコの反応(アタリ)を出すことで「釣果」に繋がりますよ!
タコジグにアクションは?
タコジグに加えるアクションとして竿先を小刻み動かし操作するか、数cm刻みで落下させて止める動作を繰り返すのがおすすめです。
基本的にタコジグはどんどん下(海面→海底)に向かって潜らせてOKです。
丁寧に「タコがいないか?」探っていきましょう!
タコジグにアクションを加える際は「スカート(水中で揺れる部品)を踊らせること」を意識してみてください。
スカートが水中でヒラヒラ踊ることでタコに猛烈にアピールすることが可能です。
海底に障害物があるような場所には、タコが潜んでいることが多くあります。
「海底に障害物が多いな〜」と感じたら、海底付近でタコジグを踊らせアピールを試みましょう。
エサを求めて移動してきたタコがヒットするかもしれません。
根掛かりに注意!
海底付近でタコジグを踊らせアピールするときは「根掛かり」に注意してくださいね。
万が一、タコジグが海底に寝てしまうと高確率で根掛かりを起こしてしまいます。
初心者さんは着底するかしないかギリギリの位置でタコを誘いましょう!
タコがタコジグや仕掛けに反応(アタリ)したり抱きつくと、釣り糸や竿先に変化や違和感を感じます。
ラインテンションが抜けたり、何かに引っ掛かったような重さを感じるんです。
このような違和感を感じたらタコが反応している可能性が高いので、糸フケを取り、力強くアワセを入れてくださいね。
アワセ方のコツは?
アワセを入れるときには釣竿の操作がとても重要です。
釣竿の操作として、まずは沖側に竿を向けます。
沖側に竿を向けたら、堤防の壁際や岸壁からタコジグを離すように引き上げましょう!
上記のように操作することで空アワセだったとしても堤防の壁際や岸壁に付いているイガイ(二枚貝の1種)に引っ掛かりません。
イガイ(二枚貝の1種)によるラインブレイクを避けることが可能なんです。
堤防の壁際や岸壁にタコが引っ付いて離れない時も、引き離して浮き上がらせることができます。
ほかにも、タコジグを回収するときの根掛かり防止や同じタナ(水層)でタコを誘いたいときにも有効なので、徹底してこの動作を行なうと◎です。
タコの釣り方「コツ3選」とは?
それでは、タコ釣りのコツ3選を解説です。
「タコエギ」「テンヤ」「タコジグ」全ての釣りにおいて、共通しているポイントになります。
あなたが「少しでもタコ釣りを上達したい!」と考えているなら、必見の内容です♪
タコ釣りのコツ①:3つの仕掛けを使い分けよう!
タコ釣りのコツ①は「3種類の仕掛け(タコエギ・テンヤ・タコジグ)を使い分ける」ことになります。
事実として「〇〇仕掛けを使えば、絶対にタコが釣れる!」という保証はありません。
ここで伝えたいのは「タコが潜む場所」「タコの活性」に合わせて、仕掛けを選定するのが大切ということ。
あなたが海底にストラクチャー(岩礁、沈み根など)が多い場所で、タコ釣りをするとします。
タコはストラクチャーに潜んでいるので「積極的に海底付近を狙う!」と判断できそうです。
以上を踏まえ、海底にアプローチしやすい「タコエギ」「テンヤ」を選ぶのが効果的でしょう!
あなたが岸壁やテトラの間に潜んでいるタコを狙うとします。
岸壁やテトラの間を狙うなら、基本的に「縦方向」に攻められる仕掛けが有効です。
つまり、海底に沈めてタコにアプローチする「タコジグ」を選ぶと釣果が上がりますね♪
タコ釣りのコツ②:根掛かりを回避する方法を把握!
タコ釣りのコツ②は「根掛かり回避方法を把握する」ことです。
堤防でタコを狙うなら、ある程度「根掛かり」は覚悟しておく必要があります。
タコが身を潜めている「障害物」をピンポイントで狙うため、気を付けていても「根掛かり」は起こり得るのです。
ですが「根掛かりしたらどうしよう..」「ルアーロストしたくないな..」と怖がっていたら「釣果」が出ません。
タコは賢いので、障害物付近をタイトに攻めないとヒットしないんです。
では「タコエギ」「テンヤ」「タコジグ」を使用する際にできる「根掛かり回避方法」をまとめていきます。
いくつか具体的な場面を例に挙げていくので、ぜひ参考にしてください!
あなたが「タコエギ」「テンヤ」を使用して、障害物が多い海底付近を探っているとします。
工夫として、釣竿を上下に動かしながら「リフト&フォール」の要領で「タコエギ」「テンヤ」を移動させるのがおすすめ。
ただ海底を巻いてくる「ズル引き」に比べ、格段に根掛かりを回避できるでしょう。
タコを誘いたい時は、障害物がありそうな定点で「竿先をシェイク」するのも効果的。
捕食スイッチを刺激できたら「がつん!」とタコが食いついてくるはずです♪
ほかにもタコエギを使用するなら仕掛けに工夫を加えても◎
具体的に「スナップにオモリを付ける=海底に接触する部分を減らせる」「短いハリスを使用する(捨てオモリ式)=根掛かりしてもルアーロストしない」などがあります。
続いて、あなたが「タコジグ」を使用して壁際や岸壁スレスレを探っているとします。
タコジグを使用した釣り方は、海底から仕掛けを回収している時に「根掛かり」が起こります。
イガイになどの突起に引っ掛かるんです..。
根掛かりを回避するため「仕掛けを壁際や岸壁から離す」ことを心がけましょう。
釣竿を沖に向かい突き出すのです!
自然とタコジグが壁際や岸壁から離れるので、根掛かりを回避できます。
また、タコジグを使用して海底を攻める時は「着底姿勢」に注意。
タコジグが寝ていると、海底との接触面積が増えて根掛かりが起こりやすいんです。
釣竿を立てる、ラインテンションを張るなど、工夫すると◎
根掛かりトラブルに遭遇した時に備え「根掛かり回収機」を用意しておくと良いですね。
基本的、堤防でタコを狙うなら「近距離」を攻めるので、回収機が活躍する場面は多くあります。
海底にルアー・仕掛け・オモリ・釣り糸など「ゴミ」を残さないので、環境保護に繋がる工夫とも言えますね!
タコ釣りのコツ③:しっかりアワセを行う!
タコ釣りのコツ③は「しっかりアワセ」をすることです。
強いアワセができないと、海底や岸壁に張り付いているタコを引き離せません。
タコにパワー負けしないよう「ドラグ=フルロック」にしておくと◎です。
アワセが問題なくできても、やり取りを上手に行えなければ、タコが再び「海底」「岸壁」に張り付いてしまいます。
このようなトラブルを回避するためにも、ラインテンションを掛けたまま「ファイト」を行いましょう!
タコが再び張り付かないよう、あなたがタコの動きをコントロールするイメージでOKです。
タコの「持ち帰り方」「下処理」について!
それでは、タコの「持ち帰り方」「下処理」についてご紹介です。
まずは「タコの持ち帰り方」からまとめていきます。
結論から言いますと「釣れたタコは1匹ずつ袋に入れる」「クーラーボックスに入れる」の2点を押さえましょう。
生命力が強いタコを袋に入れず、直接クーラーボックスに入れてしまうと大変。
クーラーボックス内の壁を這いずり回ったり、外に逃げ出すのです。
帰宅した時に車内がべとべとしてたら、最悪な気分になるかもしれません..。
上記のようなトラブルを回避するために「タコを袋に入れる」ことを忘れずに!
クーラーボックスの隙間から、タコが脱走する恐れがなくなり、安心して帰宅できるでしょう♪
ご自宅に帰宅したらタコを美味しく食べてください。
生・蒸し・茹でなど、さかざまな調理法で召し上がれることも「タコ釣りの魅力」だと思います。
それでは、美味しい状態でタコを持ち帰るための知識3選をご紹介です。
あなたが「タコを美味しく食べたい!」と考えているなら、覚えておくと便利!
タコの「キープ方法」とは?
タコの「キープ方法」をまとめていきます。
タコはバケツから脱走するので注意。
吸盤があるので、バケツの壁を這い上がるのです。
タコの脱走を防止するために、釣れた後は「すぐ締めて、クーラーボックスに収納」すると◎
鮮度を保つことにも繋がるので、一石二鳥ですよ♪
タコをクーラーボックスに収納する時のコツがあります。
先ほどもお伝えしましたが「ビニール袋に入れる」と良いですよ。
脱走も防止できますし、クーラーボックス内にある氷に直接触れるのを回避できます。
食味が落ちにくくなるので、帰宅してから美味しくいただけるでしょう♪
タコを生きた状態で持ち帰りたい人は「洗濯ネット」「専用ネット」を用意しておくと便利です。
「TAKO入れ網 DX(マルシン)」などがあると、タコの持ち帰りが快適になりおすすめ。
タコの「締め方」とは?
タコの「締め方」をまとめていきます。
締め方は、目と目の間を「ナイフで刺す」「ハサミを入れてカット」するのがおすすめ。
タコの締めがちゃんと成立すると、体が白くなります。
また、動きが鈍くなるので抵抗してきません。
タコを締める時の注意点があります。
スバリ「タコに噛まれる」可能性があるのです
意外ですが、タコはクチバシのような口を持っています。
毒はありませんが、強力に噛んでくるそう。
結構痛いので、注意してくださいね!
タコの「下処理」とは?
最後にタコの「下処理」をまとめていきます。
タコの表面に「塩」を振りかけて、もみほぐしましょう。
こうだけで「ヌメリ」「汚れ」「臭み」が落ち、抜けるので美味しく調理できるんです。
1回の食事でタコを食べきれない場合もあるかと思います。
そんな時は手段として「1匹ずつ袋に入れて、冷凍する」のがおすすめ。
冷凍しておくと鮮度を保てますし、解凍後にヌメリを取りやすいメリットがあるのです!
タコ釣りをする上で、大切な「注意点」を把握しよう!
あらかじめ「漁業権」を調べたら◎
タコ釣りをする上で注意しておくべきポイントがあります。
必ず押さえてもらいたいのが「漁業権」です。
タコに関して漁業権が設定されていることは、サザエ・アワビ・ウニに比べると認識されていません。
エリアや地域によりますが、マダコが漁業権の対象にされている場合。
むやみに捕獲するのは「違法行為」にあたります。
違反者には厳しい「罰則」があるので、注意する必要がありますね!
あなたがタコ釣りをする場所の漁業権を事前に下調べしておくと◎です。
タコには「サイズ」による規制もあります。
タコで有名な兵庫県南部にある明石市の場合「体重100g以下のタコを採捕=密漁」です。
ほかにも、北九州市に広がる関門海峡では「体重400g未満のマダコの採捕=密漁」になります。
禁止されているタコのサイズが地域で違うのですね.。
違法行為にあたるので「知らなかった!」では済みません。
調査したら100万円以下の罰金を支払うケースもありました..。
あらかじめ、あなたが釣りをする場所で「採捕してよいタコのサイズに指定がないか?」調査しておきましょう。
注意点①:漁業権
繰り返しますが、注意点①として「漁業権」をおさらいです。
釣り場によってタコには「漁業権」が設定されている場合があるので注意。
漁業権を侵害する行為(密漁など)を行うと「罰則」を受けます。
違反行為の内容や対象生物によって違いますが「100万円以下の罰金が科せられる」可能性も..。
安心してタコ釣りを楽しむなら、あらかじめ「漁業権に違反していないか?」を確認した上で釣行に向かいましょう!
自然環境を保護するためにも、小さすぎるタコはリリースすると◎
これは漁業権に関わらずです。
生態系を守ることも、釣り人としてのマナーだと思います。
注意点②:どのように漁業権を調べる?
注意点②として「漁業権が適応されている地域の調べ方」をまとめていきます。
一番手っ取り早い方法は「海洋状況表示システム(URL)」を利用することです。
海洋状況表示システムは「さまざまな海洋情報」が載っている情報サービスになります。
地図上で重ね合わせて、確認できるので初心者さんでも使いやすいかと♪
細かく漁業権の対象魚を確認するには「各都道府県のHP」をチェックするのがおすすめ。
あなたが静岡県に在住している場合。
検索窓に「静岡 タコ釣り 漁業権」と打ち込むと◎
罰則を受けることなく、タコ釣りを楽しめますね♪
もしかしたら「漁業権を調査するのめんどくさい..」と感じる人もいるでしょう。
海の資源を守ること、漁師さんの生活を守ることは「釣り人のルール&マナー」だと思います。
多少手間かもしれませんが、釣りを楽しむ上で怠ってはなりません。
注意点③:「ヒョウモンダコ」に注意!
注意点③は「ヒョウモンダコ」です。
稀にですが、タコ釣りをしていると「小型のタコ」が釣れることがあります。
ヒョウモンダコの唾液には「猛毒」が含まれているので注意。
噛まれると呼吸困難になり、最悪の場合「死に至る」場合も..。
ヒョウ柄模様の体表をしていて、見た目がとても派手です。
少しでも「違和感があるタコ」が釣れたなら、気を引き締めましょう!
タコ釣り前に、ヒョウモンダコの見た目を確認しておくと◎です。
ヒョウモンダコが釣れた際も、落ち着いて対応できると思います。
繰り返しますが、ヒョウモンダコが釣れたら「絶対に手で触れない」ようにしてください!
大切なことは「シンプル」な考え方!
タコ釣りにチャレンジしよう!
タコ釣りをする上で「必要な道具」「3種類の釣り方」の知識は、とても重要です。
たくさん解説してきましたが、「タコエギ」「テンヤ」「タコジグ」全てに共通している考え方があります。
どの釣り方でも「タコが潜んでいる場所を丁寧に狙う」だけで釣果を出せるのです。
難しいことは考えず、シンプルに「海底」「岸壁」など、限られたポイントを狙いましょう!
上記の考え方を押さえるだけで、初心者さんでもタコが簡単に釣れる可能性が高まります。
あなたも、ぜひ近年盛り上がってきている「タコ釣り」にチャレンジしてください♪