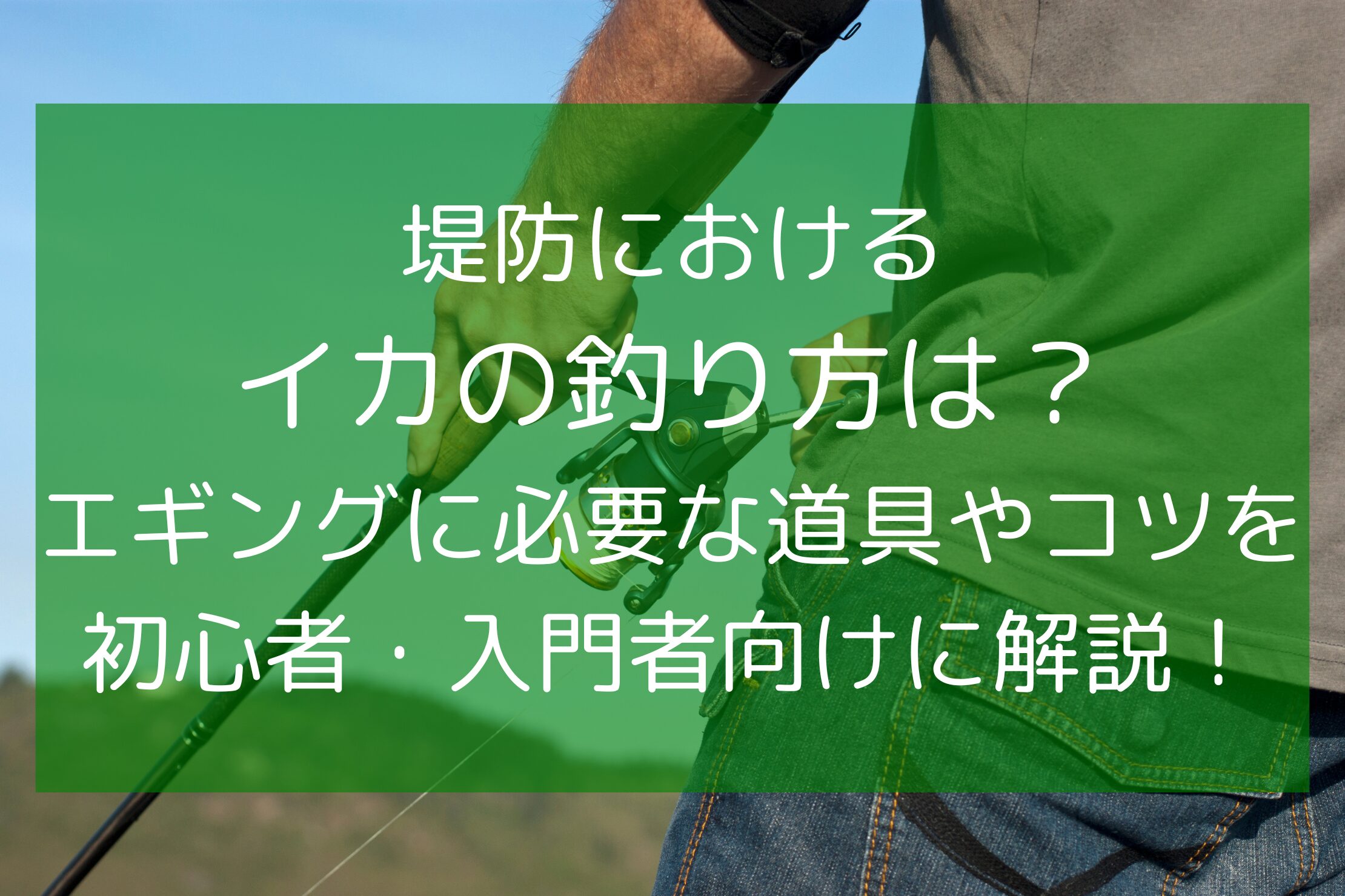堤防からイカを狙う時には「エギング」と呼ばれる釣り方で狙うことがほとんどです。
エギングとはエギと呼ばれる擬似餌を使用してイカ類を狙う釣り方の総称になります。
一般的なメインターゲットはアオリイカですが、釣り場によってはコウイカやヤリイカなども釣ることが可能です。
アオリイカが釣れる時期は春〜初夏・秋〜初冬の2シーズンに分けられます。
春にエギングを始めるなら4月〜6月頃。
秋にエギングを始めるなら8月〜11月頃がおすすめです。
春のイカは産卵期を迎えます。
産卵期を迎えるため「親イカ(1kg〜3kg前後)」と呼ばれる、大型の個体をエギングで狙えますよ!
一方、秋は生まれたばかりのイカを狙えます。
成長段階の「子イカ(500g前後)」は食欲旺盛なので小型のエギに対する反応が素晴らしく、数釣りを期待することができるんです。
ルアーフィッシングの中でも「エギング」は高い人気を誇ります。
ロッド、リール、ライン、エギといった「シンプルなタックル」で楽しめること。
また釣り場に軽装で足を運べることが、初心者さんからベテランまで、多くの釣り人を魅了している要因でしょう。
今回の記事では「春のイカ釣り(エギング)」の釣り方やタックルについてご紹介していきます。
あなたが「堤防でエギングを始めたい!」「身近な釣り場でイカを釣りたい!」と考えているなら必見の内容です!
【エギング概要】
- ターゲット:アオリイカ、コウイカ、ヤリイカなど
- 釣り場:堤防、磯など
- 釣れる時期:春〜初夏(4月〜6月頃)・秋〜初冬(8月〜11月頃)
Contents
エギングで釣れる魚介類は?代表的なイカをご紹介!
エギングにおけるメインターゲットは「アオリイカ」です。
アオリイカとの駆け引きや独特な引き味が多くの釣り人を魅了しています。
食べて美味しいことも嬉しいポイントです。
アオリイカ以外にも海底に砂地や海藻が点在する場所なら「コウイカ」「モンゴウイカ」「シリヤケイカ」などがヒットすることも!
コウイカは驚くと「墨を吐き出す習性」があるので注意が必要です。
あなた自身や釣り場を汚してしまうかもしれません。
コウイカが釣れた際は、怒らせないよう丁寧に取り込みをしてくださいね。
上記に挙げたイカ類以外にもエリアによっては「スルメイカ」「ケンサキイカ」「ヤリイカ」を狙うことが可能です。
エギングができる場所をご紹介!
アオリイカは海藻が多い場所を好む習性があります。
海藻が豊富な藻場には「産卵場所」「エサが豊富に生息」しているからです。
※海藻を好むアオリイカを地域によっては「モイカ」と呼ぶこともあります。
春のアオリイカは産卵を行います。
産卵場所として海藻(アマモやホンダワラなど)は最適なんです。
春にエギングを行うなら藻場のある堤防、磯、砂浜(サーフ)から「アオリイカ」を狙ってくださいね。
アオリイカのエサ(小魚や甲殻類など)が多く生息している場所も狙い目です。
小魚(イワシ、アジ、キビナゴ、ネンブツダイなど)が多く生息している場所にアオリイカは回遊してきます。
また、捕食を目的とした高活性なアオリイカが潜んでいるので、比較的釣果を伸ばしやすいです。
エサ(小魚や甲殻類など)が多く生息している場所として「潮通しが良い堤防」や「岩礁帯」などが挙げられます。
初心者さんは積極的に地形変化や潮流に変化があるポイントを狙うと「釣果」を出せますよ!
秋シーズンは産卵時じゃないので、藻場にこだわらなくてもOKです。
基本的にアオリイカが藻場にいる確率は高いのですが、あなたが釣りをする場所に藻場がないことも考えられます。
そんな時は「シモリや隠れ根(水中に隠れている岩礁や根のこと)」「消波ブロック・コンクリートブロック」などの障害物周りを狙うことで「釣果」を伸ばせるでしょう。
足元にある障害物を丁寧に探り「アオリイカ(小型)」を中心に釣り上げてくださいね。
秋のアオリイカは身が柔らかく、とっても美味しいですよ!
エギングに「必要な道具」をご紹介!
それでは、エギングに必要な道具をご紹介です。
まずはおすすめの「タックル一例」からまとめていきます。
おすすめのタックル一例
下記に「おすすめのタックル一例」をまとめました。
これからエギングを始める人は、ぜひ参考にしてくださいね。
【おすすめのタックル一例】
- 釣竿:エギング用ロッド(8ft〜8.6ft)
- リール:スピニングリール(3000番)
- ライン:PEライン(0.6号〜0.8号)
- ショックリーダー:フロロカーボンライン(2.5号〜3号)を約1.5m使用
- スナップ
- エギ(3号〜3.8号)
エギングに必要な道具:釣竿(ロッド)
春にヒットするアオリイカの平均的なサイズは1kg前後で、最大で3kgを超える良型が釣れることもあります。
なんと胴の長さが30cm~40cm程度にまで成長しているで、手のひらよりも大きいんです。
大型のアオリイカを狙う際は、基本的に3.5号のエギを使用することをおすすめします。
3.5号のエギを軽快に操作するために「エギング専用モデル」の釣竿を準備しましょう。
エギング専用モデルの釣竿には、重いエギ(3.5号)をストレスなく使用できるくらいのパワーを備えていますよ!
ほかにも軽量さ、シャープな操作性、高い感度、エギのアクションに合わせた設計を兼ね備えているので、長時間「エギング」をしていても疲れません。
エギング専用モデルの釣竿の長さは「8.6ft(2.59m)」を基準にするのが◎です。
「足場が高いな〜」と感じるようなら「9ft(2.74m)前後」の釣竿を選ぶと、エギにアクションを加えやすいでしょう。
また「足場が低いな〜」感じるなら「8ft(2.43m)クラス」の釣竿を準備すると◎
取り回しが快適なので扱いやすいと感じられます。
あなたが実際に釣行に向かう釣り場に最適な「エギング専用モデルの釣竿」を選ぶ時の参考にしてくださいね。
エギングに必要な道具:リール
春に行うエギングでは「スピニングリール3000番(番手)」をメインに使用します。
スピニングリール3000番って糸巻き量(スプールに巻ける糸の量)とパワーのバランスが素晴らしいんです。
遠投時や強風が吹く中でもストレスを少なく有利にエギングを楽しめるため、多くのエギンガーに選ばれています。
堤防でエギングをする際は、広範囲を探る必要があります。
糸巻き量が少ないと遠くにいるアオリイカにアピールすることができませんよね。
春に釣れるアオリイカは大型であることが多いです。
大型のアオリイカにパワー負けしないためにも「スピニングリール3000番」のパワークラスが必要になります。
スピニングリールには「エギング専用機種」も販売されているので、これからエギングを始める人はチェックしてみましょう!
おすすめのスピニングリールとして、大手釣具メーカー「シマノ(SHIMANO)」から販売されている「セドナ」「セフィアBB」などが◎です。
初心者さんは、ぜひ参考にしてみてください。
エギングに必要な道具:釣り糸(ライン)
釣り糸(ライン)には「PEライン(0.6号〜0.8号)」がおすすめです。
感度と飛距離を重要視するなら「0.6号」、パワーや耐久性を意識するなら「0.8号」をスピニングリールに巻いておくと良いですね。
PEラインはスレや熱に弱く「ラインブレイク」することが多々起こります。
PEラインを使用する時は、弱点を補うためショックリーダーを結びましょう!
ショックリーダーには「フロロカーボンライン(2.5〜3号)を1ヒロ(約1.5m)くらい準備しておくと◎です。
ショックリーダーとは道糸(リールに巻かれている釣り糸)であるPEラインに結束して使用する釣り糸(ライン)のことを良います。
PEラインとショックリーダーを高い強度で結べる「FGノット」という結束方法がおすすめです。
結束部分が切れるトラブルが少ないので、効率よく安心してエギングを楽しめるでしょう。
エギングに必要な道具:エギ
初心者さんは「春のエギングでメインに使用するエギ=3.5号」だと押さえておきましょう。
3.5号のエギを基準にして状況に合わせ「サイズ」「タイプ」「カラー」を使い分けることで効果を発揮します。
アオリイカの活性が上がる「マズメ時」「夜間」にエギングを行う際は、アピール力を重視して3.5号以上のエギで攻めるのがおすすめ。
一方、アオリイカの活性が下がる「低水温」「潮止まり」「海が荒れている」時は、シルエットの小さい3号のエギを使用すると効率よくエギングを楽しめます。
春はアオリイカの産卵時期です。
アオリイカは産卵を藻場で行います。
ということもあり、春のエギングでは「シャローエリア(浅い水域)の藻場」を狙うことが多いです。
シャローエリア(浅い水域)の藻場を狙う際は、シャロータイプのエギを準備すると◎です。
軽重量で沈下速度が遅いのでシャローエリア(浅い水域)に潜むアオリイカを快適に狙うことができますよ。
藻場でノーマルモデルのエギを使用していると「藻掛かり」が多発するので注意が必要です。
シャロータイプのエギは「藻掛かり」が起こりにくいので、準備しておくことをおすすめします。
これは余談ですがアオリイカがヒットした時には「ランディングツール(陸に引き上げる道具)」が必須になります。
堤防で行うエギングではタモやギャフを持参しておくと良いですね。
快適にアオリイカを取り込むことができますよ!
エギングに必要な道具:スナップ
エギングをする際は、金属製の金具である「スナップ」を準備しましょう。
あらかじめスナップをリーダーに結ぶことで「ルアーの着脱を簡単かつ素早く行うこと」が可能です。
使用しているエギを素早く着脱できるので、ルアー交換の時間ロスを抑えられます。
ルアーを交換するたびに釣り糸を切ったり、結び直す必要性がないので本当に便利なんです。
定期的にスナップとリーダーの結束部分を確認すると◎
結束部分に傷がある場合、結び直すことで「ラインブレイク」を回避できますよ!
エギングの釣り方についてご紹介!
エギングの釣り方についてご紹介です。
まずは「4つの手順」についてまとめていきます。
エギングの釣り方:「4つの手順」について
エギングの釣り方には4つの手順があると思います。
下記に「エギング手順まとめ」を記載したので、まずは全体把握をしてみましょう。
【エギング手順まとめ】
- キャスト
- フリーフォール
- シャクリ
- カーブフォール
上記の「エギング手順まとめ」を足元まで繰り返すことで「アオリイカ」が潜む居場所を探っていきましょう。
それでは、各手順について詳しくみていきます。
まずはエギを狙った場所にキャストしましょう。
エギを上手にキャストできたら「フリーフォール」でエギを「海底or任意の水層(タナ)」まで沈めます。
※フリーフォールとは、リールから釣り糸(ライン)を放出し続けながら自由沈下させるテクニックです。
あなたが「藻場」を狙っている場合「藻の上までフリーフォール」させることがコツ。
藻掛かりを回避することができます!
エギを沈める時は「釣り糸(ライン)」の動きから状況判断すると◎です。
釣り糸(ライン)が海に引き込まれている時は、エギが沈下している状況になります。
釣り糸(ライン)の動きが止まったら、エギが着底した証拠なのでアクションを加え始めましょう!
初心者さんがいきなり釣り糸(ライン)の動きを把握することは難しいと思います。
特に波や風があると尚更分かりにくいでしょう。
波が穏やかな日・無風の日に釣り場に足を運び練習することをおすすめします。
少しずつ釣り糸(ライン)の動きから水中の状況を把握する感覚が掴めるはずです。
エギが着底または任意の水層(タナ)に到達したら、釣竿を「シャクリ」エギにアピールを加えましょう。
シャクルときは釣竿を上下動かしてくださいね。
この時「大きく」「力強く」「素早く」動かすことでアオリイカに効果的なアピールをすることができますよ。
シャクリが終わり次第、釣り糸(ライン)を張った状態でエギを沈める「カーブフォール」を行います。
カーブフォール中にアオリイカがエギに抱きつくことがほどんどです。
エギが不自然な動きや沈み方をしていると、アオリイカが警戒してしまい「釣果」を出せません。
初心者さんは「竿先を下げた状態にする」「釣竿(ロッド)を動かさない」「リールハンドルを巻かない」の3点を意識してください。
この3点を意識することでエギがスーッと自然な状態でカーブフォールしながら沈みます。
微妙な差で釣果が大きく変わるので、次回の釣行時からチャレンジしてくださいね。
最後にワンアドバスをご紹介です。
朝夕のマズメ時や夜間はアオリイカが水面まで浮きやすくなります。
「アオリイカが浮いている!」と感じたら、ぜひエギを屈指して中層付近を探ってみましょう。
海底までエギを沈める手間を省略できるので、効率よくアオリイカを釣ることが可能です。
この手は小型のアオリイカを狙う「秋シーズン」にも効果的で大活躍してくれますよ!
エギングの釣り方:各手順の「意識するべきこと」について
シャクリ方に正解や決まりはありません。
釣果を伸ばすには「しっかりと水中でエギを動かすこと」を意識しましょう。
まずはアオリイカに興味を持ってもらえるようなアピールをすることが重要なんです。
アオリイカにアピールをした後は「フォールをしっかりさせること」がとても大切。
ほとんどの場合アオリイカのアタリが出るのは「フォール中」で、いきなりエギにが沈んでいる最中に抱きついてきます。
アオリイカがヒットした際には釣り糸(ライン)が引っ張られたり、沈降途中でエギが止まるパターンが多いです。
エギング始めたての頃は「アオリイカのアタリ」に驚くかもしれませんが、このようなアタリが出たら丁寧に「アワセ」を行いましょう!
アワセとは魚やイカ類の口に釣り針を掛ける動作のことを言います。
釣竿やラインテンションを上手に活用した「アワセ」を行いフッキングに持ち込んでくださいね。
アオリイカのアタリかどうか判断ができず、シャクリ中にアオリイカがヒットしていたことも多く起こります。
何が起こるか予測できないこともエギングの醍醐味なんです。
エギにヒットした直後のアオリイカは、猛烈に抵抗を繰り返します。
ジェット噴射・ジェット推進を繰り返し遠くに逃げる習性があるんです。
アオリイカが抵抗している際は、釣り糸(ライン)を巻かないでください。
釣り糸(ライン)に負荷がかかり「ラインブレイク」する原因になるので、ドラグを調整して身切れを防ぎましょう!
また釣竿(ロッド)をしっかり曲げたり、ラインテンションを保つことで、徐々にアオリイカはがおとなしくなり始めます。
おとなしくなったアオリイカは、水面に浮き上げることが可能です。
「アオリイカの抵抗が少ない!」「アオリイカの引きが弱まった!」と感じたら、釣り糸(ライン)を丁寧に回収してOK。
あとは足元までアオリイカを寄せ、玉網を使って丁寧に取り込んでくださいね。
ここがエギングのポイント!
最後に、エギングのポイントについてご紹介です。
まずは「アオリイカの取り込み方について」まとめていきます。
ポイント①:アオリイカの取り込み方について
エギングのポイントとして「アオリイカの取り込み方」が挙げられます。
小型のアオリイカ(200〜300g前後)なら、水中から素早く抜き上げることが可能です。
タモや玉網を使用しなくても簡単に取り込むことができると思います。
大型のアオリイカ(500g以上の個体)がヒットした際は、身切れやライン切れが起こることが多いので注意しましょう。
最悪の場合、釣竿(ロッド)が折れたり破損することも!
大型のアオリイカをバラし(逃し)たり、大切な釣具が破損したらテンションが落ちてしまいますね..。
このようなトラブルを避けるために、大型のアオリイカがヒットした際の取り込みには「玉網(たまあみ)」を上手に活用してください。
玉網(たまあみ)の使い方はシンプルです。
アオリイカを足元まで寄せたら、あらかじめ玉網(たまあみ)を伸ばし海中に浸けておくと◎
素早くアオリイカを取り込みことができますね!
あとは、上手に玉網(たまあみ)の近くまで誘導し、胴体側から取り込んでくださいね。
胴体側から取り込むことで、アオリイカを傷つけません。
ポイント②:アオリイカの産卵行動について
エギングのポイントとして「アオリイカの産卵行動」が挙げられます。
産卵行動時のアオリイカのオスとメスはペア状態に入ります。
この状態のアオリイカはルアーやエサに見向きもしません。
自然環境を守るためにも、ペアリングしているアオリイカを狙うことは避けましょう。
産卵期のアオリイカを優しく見守り、釣り場環境を守ることも重要です。