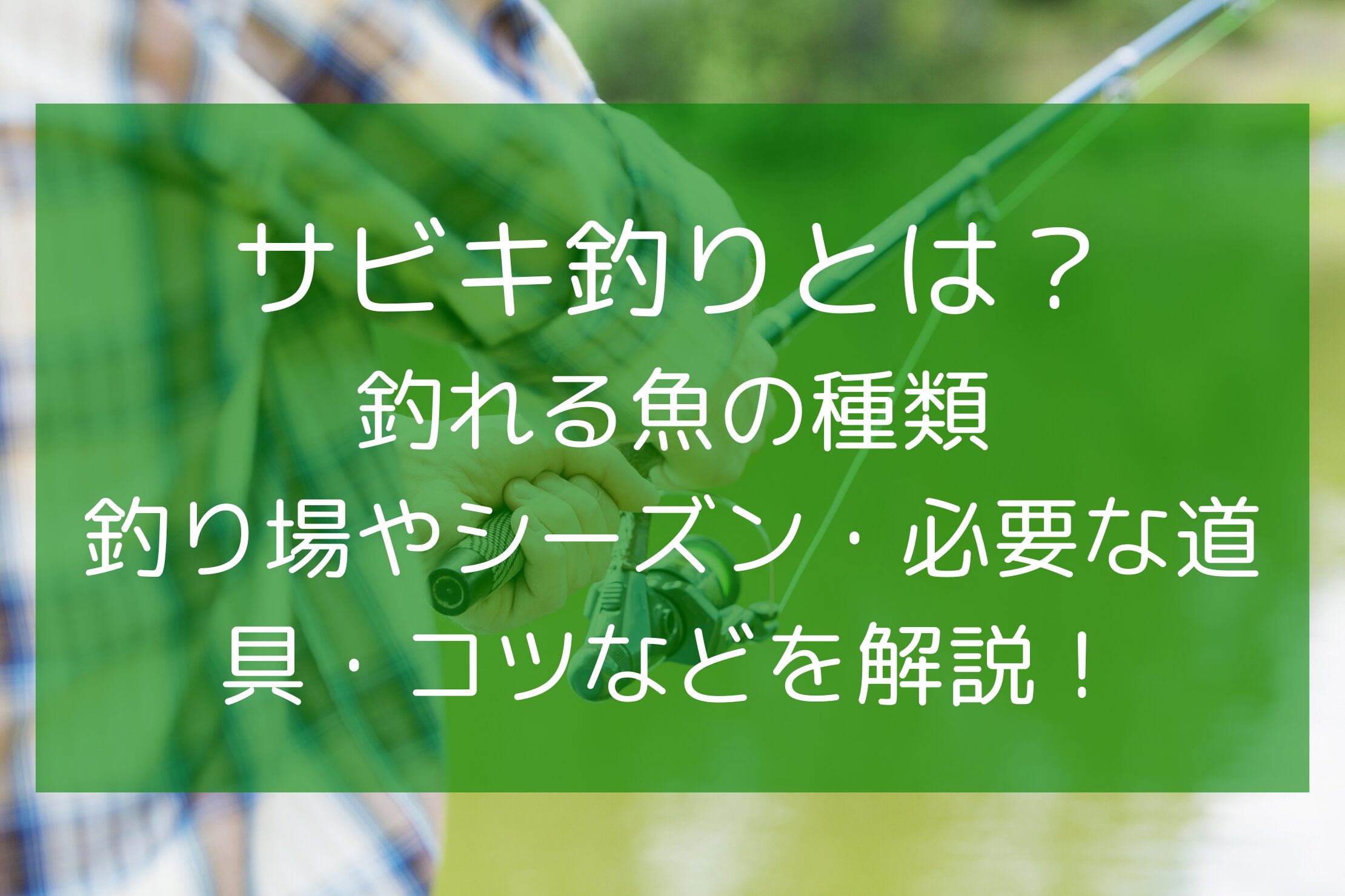マキエを使った釣り方は「ウキフカセ釣り」「カゴ釣り」「ダンゴ釣り(紀州釣り)」など数種類ありますが、これから海釣りに入門する人には「サビキ釣り」がおすすめです。
サビキ釣りとは、プランクトンのオキアミをマキエ(撒き餌)に使用し、足元に「アジ」「サバ」「イワシ」などの魚を寄せます。
その後、サビキバリ(擬似バリ)が複数個付いた「サビキ仕掛け」を海に投入し、これら小型回遊魚を狙う釣り方です。
詳しくは「サビキ釣りとは?」の見出しで詳しく解説していきます。
この記事では「サビキ釣りとは?」という基本的な知識をはじめ「サビキ釣りで釣れる魚の種類」「サビキ釣りができる『釣り場』や『シーズン』」「必要な道具・仕掛け・餌」「サビキ釣りの方法」などを詳しく解説!
さらには「サビキ釣りで釣れないときのコツ」や「サビキ釣りで釣れた魚の持ち帰り方」にも触れています。
今回は釣り初心者向けに記事を作成しましたが、サビキ釣りに興味がある方全般にも役立つかと思います。
ぜひ参考にどうぞ!
Contents
サビキ釣りとは?
サビキ釣りとは、プランクトンの「オキアミ」「アミエビ」をマキエとして海に撒き、足元に寄ってきた小型回遊魚を狙う海釣りの王道。
堤防釣りの中で、最もポピュラーな釣り方のひとつですが、難しいテクニックは一切必要ありません。
「初めて釣りに挑戦する方」「釣りの経験はあるけど、海釣りは初めての方」など、幅広い釣り初心者や入門者が楽しむのに最適です。
基本的な知識もわかりやすく、理解しやすいので、ぜひチャレンジしてみてください!
サビキ釣りの名前の由来でもある「サビキ仕掛け」には、ビニール・薄いゴム・魚の皮が付いた「サビキバリ(擬似バリ)」が複数個セットされています。
このサビキ仕掛けを海中に投入し、マキエでおびき寄せた、群れで泳いでいる小型回遊魚を狙いましょう。
回遊魚の群れが足元に来ると、1度のキャストで「アジ」「サバ」「イワシ」といった魚が2匹〜3匹と立て続けにヒットすることが多々起こります。
女性や子供、誰でも短かい時間でたくさんの魚が釣れる(数釣り)「ビギナーズラック」に遭遇することも!
サビキ釣りは主に「堤防」「岸壁」などでの釣りにおすすめで、季節としては水温が高い時期である「春」「夏」「秋」まで楽しめます。
この時期はメインターゲットになる「アジ」「イワシ」「サバ」「コノシロ」「サッパ」など、回遊魚が群れで活発的に行動しているのです。
サビキ釣りでは「アジ」「イワシ」「サバ」など、いろいろな種類の魚が釣れる!
サビキ釣りは周囲にマキエとして魚を引き寄せる力(集魚力)が高い「アミエビ」を撒くので、足元にさまざまな種類の魚が集まります。
足元を泳ぐ魚をエサや複数の擬似バリが付いた「サビキ仕掛け」を海に落とし狙うだけなので、釣り初心者でも簡単にさまざまな種類の魚に出会える(魚を釣れる)のです。
釣りをする場所や釣りをする時期(シーズン)によりますが、メインターゲットは小型回遊魚である「アジ」「イワシ」「サバ」「コノシロ」「サッパ」などが中心に釣れます。
他にも、強烈な引きを楽しめる「真鯛」「グレ」、美味しく食べれる「カマス」「カサゴ」「サヨリ」「カワハギ」など魅力的な魚たちがヒットすることも。
サビキ釣りでは毒ドゲを持つ魚である「ハオコゼ」「アイゴ」が釣れてしまう場合があります。
毒トゲが身体の一部に刺さると「激痛が走る」「腫れや痺れ」を引き起こすため、これらの魚が釣れたら素手で触ることは避け、海に放してあげてください。
魚体を挟んで持てる「フィッシュグリップ」や「プライヤー」があると、毒ドゲを持つ魚に直接触れずに、口元に掛かかっているハリを外せて便利です。
ここからは、サビキ釣りでよく釣れる魚をご紹介していきます。
サビキ釣りでよく釣れる魚は、主に下記の8種類です。
【サビキ釣りでよく釣れる魚|8種類】
- アジ
- イワシ
- サバ
- カワハギ
- マダイ
- スズメダイ
- メジナ(グレ)
- アイゴ
それでは、各魚たちの情報を詳しくみていきましょう。
サビキ釣りで釣れる魚①:アジ
サビキ釣りで釣れる魚①は「アジ」です。
サビキ釣りのメインターゲットである「アジ」は、潮通し(潮流れ)が良い釣り場所に回遊していることが多い魚になります。
潮通しが良い釣り場として「堤防の先端」や「堤防コーナー部」が挙げられ、足元を見ると群れで泳ぐアジがいることも!
マキエを海に撒きアジをおびき寄せるサビキ釣りなら、釣り初心者でも簡単に美味しい魚「アジ」を釣り上げることができます。
アジはお刺身や揚げ物など、いろいろな調理法でおいしく食べられることも魅力です。
食卓に並んでいると嬉しいお魚ランキング1位と言っても過言ではありません。
釣れるシーズンは「春」「夏」「秋」です。
サビキ釣りで釣れる魚②:イワシ
サビキ釣りで釣れる魚②は「イワシ」です。
イワシには捕食されないよう群れで泳ぐ習性があり、この習性を利用することでサビキ釣りでは「大量釣果」が狙えます。
群れの中の1匹が釣れた途端に、周囲で泳いでいるイワシの活性が連鎖的に上がるため、2匹3匹と釣れ続き始めるのです。
ウロコが取りやすいイワシは、下処理の手間が少ないので、調理の手間を省略できるも嬉しいポイント。
家事に割く時間や疲労を軽減できると、のんびりとお子さんや家族と過ごす時間や心の余裕を作れます。
釣れるシーズンは「春」「夏」「秋」で、特に6月〜7月頃のイワシは「入梅いわし」と呼ばれていて、口いっぱいに脂の旨みが広がりとても美味しいんです♪
サビキ釣りで釣れる魚③:サバ
サビキ釣りで釣れる魚③は「サバ」です。
近年、水産資源の減少のため高級魚になりつつある「サバ」も回遊魚なので、アジやイワシと同じようにサビキ釣りなら釣り初心者でも簡単に釣り上げられます。
サビキ釣りでサバを釣るコツは「マキエ(撒き餌)を上手に使う」ことです。
「狙ったポイントに投げ込む」「継続的に少しずつ海に撒き続ける」の2点を意識すると、サバを足元に集めれるのでヒットしやすくなります。
サバの脂(オメガ3系脂肪酸)は中性脂肪をや悪玉コレステロールを下げますが、数時間経つと痛み始めるため「食中毒」に注意してください。
鮮度を保つように「サバ」が釣れたらすぐに締め、氷を入れたクーラーボックスに入れて保存しておくと◎
自宅に帰り次第、熱々でホクホクな「竜田揚げ」、絶妙な甘さがたまらない「サバ味噌」、サバ本来の旨みを味わえる「塩焼き」など美味しく調理して食べられますよ。
釣れるシーズンは「春」「夏」「秋」です。
サビキ釣りで釣れる魚④:カワハギ
サビキ釣りで釣れる魚④は「カワハギ」です。
カワハギの口は小さく硬いたいうえに、クチバシのような形をしているため、釣り針(鈎)がなかなか掛かりません。
比較的、サビキ釣りで狙える魚の中では難易度が高い「カワハギ」ですが、サビキ釣りで釣り上げた時の喜びは最高です。
餌だけを上手に捕食することから「エサ取り名人」と呼ばれているので、カワハギが釣れた日には「釣り初心者」を卒業しても良いかもしれません。
食べてみると淡白な白身や上品な旨みが「抜群に美味しい!」と評判なので、興味がある方はぜひご賞味あれ!
釣れるシーズンは「春〜夏」にかけてです。
サビキ釣りで釣れる魚⑤:マダイ
サビキ釣りで釣れる魚⑤は「マダイ」です。
武士の鎧を思わせる見た目の美しさ、縁起物(めでたいという語呂合わせ)など、さまざまな要因が重なり、マダイは「魚の王様」として多くの釣り人に親しまれています。
マキエを海に撒き広範囲に潜む魚にアピールするサビキ釣りなら、魚の王様を「堤防」「岸壁」といった身近な釣り場で狙えるのです。
釣りをする場所や時期によって大型のマダイ(50cm以上)が釣れるサビキ釣りですが、一般的には「20cm以下の小さいマダイ(幼魚)」が釣れるケースが多いです。
そのような小さいマダイを関西地方では「チャリコ(少年という意味)」という愛称で呼びます。
釣れるシーズンは「春」「秋」で、大物狙いをしたい方は「乗っ込みの時期(3月下旬〜6月上旬)」にサビキ釣りに挑戦してください。
サビキ釣りで釣れる魚⑥:スズメダイ
サビキ釣りで釣れる魚⑥は「スズメダイ」です。
マダイと同じく、左右に平たい(側扁)の魚体をしている、スズメダイですが「見た目」や「大きさ」は全く違います。
マダイの体色は光沢がありピンク色に対し、スズメダイは黒みがかった体色をしていることが特徴的です。
スズメダイは群れで泳ぎ行動しているため、複数の擬似バリ(サビキバリ)が付いた仕掛けで魚を狙う「サビキ釣り」との相性抜群。
1度ヒットし始めると「数釣り」を楽しるので、釣り初心者でも高確率で「たくさん釣れた〜」と達成感を味わえますよ!
釣れるシーズンは「夏から秋」にかけて釣れるため、「子供に魚を釣りあげた経験を積ませたい親御さん」におすすめしたいターゲットです。
サビキ釣りで釣れる魚⑦:メジナ(グレ)
サビキ釣りで釣れる魚⑦は「メジナ(グレ)」になります。
非常にパワフルな引き味を楽しめるメジナ(グレ)は「磯の王者」と呼ばれており、数多くのアングラーから高い人気を誇るターゲット。
一般的にメジナ(グレ)は、釣り初心者には難易度の高い「フカセ釣り」を屈指して、アクセスの厳しい「磯場」で狙うことが多いです。
ですが、マキエを上手に活用したり、潮流れの良いポイントを選べれば、釣り初心者でも簡単に「サビキ釣り」で釣り上げられます。
本格的な夏場(6月~8月)になると、身近な「堤防」「港湾部」「釣り公園」でメジナ(グレ)が釣れ始めるので、ぜひ挑戦してくださいね。
サビキ釣りで釣れる魚⑧:アイゴ
サビキ釣りで釣れる魚⑧「アイゴ」です。
アイゴは毒トゲを持つ危険な魚なので、直接手で触れないよう慎重に釣りバリ(鈎)を外してリリースしましょう。
手で触れずに魚を摘める「フィッシュグリップ」や「ワニグリップ」を釣り場に持参すると便利ですが、手持ちにない場合「釣り糸を切って逃す」ことも視野に入れておくと◎
釣れるシーズンは「春」「夏」「秋」です。
サビキ釣りができる「釣り場」や「シーズン」とは?
ここでは、サビキ釣りができる「釣り場」や「シーズン」について解説していきたいと思います。
サビキ釣りができる釣り場には、常に新鮮な海水が流れ込む(潮通しが良い)場所に面した「漁港」「堤防」「岸壁」などがおすすめ。
整備された施設が多く、安全性の高い「海釣り公園」もおすすめで、「子供に釣りの経験を積ませたい」「ファミリーフィッシングに挑戦したい」と考えている親御さんから人気を誇ります。
さらに、水深が深い(3m〜5m以上)場所だと「魚の警戒心が弱まり、サビキ仕掛けにヒットする」「回遊ルートなので、足元に群れが泳いでいる」ことが多いので、釣り場に到着したら足元全体を見渡しましょう!
(潮流れがゆるやかでも、水深が深く規模が大きい「港内」なら、豊富な魚種や大型個体に出会えることも)
釣り場が広すぎる場合、魚が回遊しているポイントに偏りが生じることも考えられます。
そんな時は、サビキ釣りをしている釣り人に挨拶を交わしながら「どこで魚が釣れましたか?」「どんなタックルや仕掛けを使いましたか?」と尋ね、ヒントを探ると良いかと。
釣れているアングラーの真似をするのが、サビキ釣りで「アジ」「サバ」「イワシ」を釣り上げるまでの近道です。
サビキ釣りを楽しめる釣り場をGoogleマップなど、地図だけで探すのは難しいため、釣行前にインターネットで調べておきましょう。
Google検索窓に「地名+サビキ釣り+釣り場」「地名+サビキ釣り+おすすめ」といった感じで探しておくと◎
「足元の水深が深い場所」「潮位の高い『満潮』『大潮』といった時間帯」など、いくら条件が良くても魚が回遊してこなければ「釣果」は期待できません。
最悪の場合「1日釣りをして釣れた魚が0匹だった..」というシーンに遭遇してしまうことも。
このような状況を回避するため、釣り場ごとに最新の「最新の釣果情報」や「回遊魚の状態」を入手しておくと良いです。
(これらの情報も「釣具店」「ネット」を利用すると入手しやすい)
サビキ釣りは、主に「春」「夏」「秋」の季節(シーズン)に楽しめ、「冬」はオフシーズンです。
釣りをする地域にもよりますが「7月〜9月」が釣果を期待できます。
水温が低下する冬は、海が荒れることが多く、岸付近まで魚が回遊してきません。
足元に泳いでいる魚を狙うサビキ釣りでは、どうしても魚を釣り上げるのは難しいのです。
ただ冬が終わり春に入ると、サビキ釣りで中型〜大型の回遊魚が釣れるので「タックル(釣竿やリール、釣り糸、仕掛けなど)の準備」や「リーダーの結び方を練習」して過ごすといいかと思います。
暖かい時期である春と秋は、サビキ釣りで「中型〜大型狙い」を楽しめます。
産卵期を迎える春には「尺アジ(30cm以上)」や「ギガアジ(40cm超)」を狙えますし、秋は夏の間に成長した「中型アジ」「コノシロ」がヒットするのです。
釣れる魚のサイズが大きいため、使用するサビキバリのサイズも「5号~8号」と大きめに調整すると、ヒットした魚を逃がしません。
浅瀬まで魚が接近する夏は、年間を通しサビキ釣りで数釣りを1番楽しめるシーズン。
マキエやコマセにおびき寄せられた「小型回遊魚(アジ、サバ、イワシなど)」を目視で確認でき、他のシーズンと比べて簡単に魚が釣れます。
春に生まれたばかりの小魚を相手にすることが多いため、使用するサビキバリを「3号〜4号」と小さめにしておくと、魚の口にハリが掛かりやすいです。
(夏場の釣りは熱中症や日焼けに注意し、「帽子」「サングラス」「長袖」の着用を忘れずに)
釣りをする時期(シーズン)に伴い、サビキ釣りにおける「釣り方」「釣れる魚」の傾向が変わることがわかりました。
ただ、年間を通して共通しているポイントもあり、それは「日の出や日の入り前後1時間は魚がヒットしやすい」ということ。
まだ薄暗い「朝マズメ」「夕マズメ」とも呼ばれる、このタイミングはエサであるプランクトンが豊富に泳いでいるため、サビキ釣りのメインターゲットである小型回遊魚の活性が高まるのです。
サビキ釣りができる釣り場①:岸壁
サビキ釣りができる釣り場①は「岸壁」です。
足元に深い水深のある岸壁は「回遊魚(アジやイワシ)」や「根魚(カサゴやメバル)」など、さまざまな魚が集まる絶好のスポット。
船の係留施設ということもあり足場の安全性が高いので、小さいお子さんや高齢者が「転倒」「落水」するトラブルが起こりにくく安心です。
サビキ釣りができる釣り場②:堤防
サビキ釣りができる釣り場②は「堤防」です。
堤防の中でも、潮流れが良い・水深が深い「コーナー部(内向き・外向き)」「先端部」は、足元まで魚が回遊してくる1級スポット。
海にマキエを撒き魚を寄せ、複数の擬似バリで魚を狙うサビキ釣りでなら、釣り初心者でもたくさん魚が釣れるため、堤防で釣りデビューする方も多いんです!
サビキ釣りができる釣り場③:波返し(なみがえし)
サビキ釣りができる釣り場③は「波返し(なみがえし)」です。
防波堤や岸壁の最上部にある「波返し」は、波が陸地まで超えてこないように防ぐ壁状の構造物。
足場が高い波返しでは、糸絡みが起こりやすく、サビキ釣りを快適に楽しめないかもしれません。
これはサビキ釣りで使用する仕掛けが、全長1.5mと結構長いことが理由です。
(風や波に邪魔されて、魚とのやりとりがスムーズにいかないことも多い)
釣り初心者が波返しでサビキ釣りに挑戦するなら、できるだけ足場が低いポイントを選ぶのがおすすめ。
仕掛けを狙い通りに操作できますし、風や波の影響を受けにくいので、あなたの思い通りにサビキ釣りを楽しめます。
サビキ釣りができる釣り場④:藻場
サビキ釣りができる釣り場④は「藻場」です。
回遊魚が多く生息している藻場は、サビキ釣りをするなら絶好のスポット。
その反面、サビキ仕掛け(複数のハリが付いた仕掛け)が根掛かりしたり、海底や中層に生える藻に絡まるリスクが高いです。
ハリと藻が絡まると、海中でサビキ仕掛けが不自然な動きをするため、魚が違和感を感じてしまい、魚が釣れない時間が長くなることも。
藻場をサビキ仕掛けで狙うなら、狙う水層を上目に調整することで「根掛かり」「藻と絡まる」トラブルを回避できるでしょう。
サビキ釣りができる釣り場⑤:イカダ
サビキ釣りができる釣り場⑤として、海上にロープで固定された「イカダ(釣り専用)」が挙げられます。
イカダの下に回遊魚が泳いでいることは多いので、イカダを利用してサビキ釣りを楽しむ釣り人は大勢いらっしゃいます。
「アジ」「イワシ」「サバ」「メジナ」「カマス」「カサゴ」など、多彩な魚種が連続でヒットする数釣りが楽しめるケースも!
イカダは波が穏やかな場所にあることが多く「船酔い」の心配が少ないです。
初めて釣りに挑戦する女性や高齢者、家族連れの方など、幅広い釣り初心者が安心して釣りを楽しめるスポットともいえますね。
サビキ釣りに「必要な道具」「仕掛け」をご紹介!
サビキ釣りをする際に必要な道具や仕掛けを下記にまとめました。
- 【サビキ釣りに必要な道具や仕掛け】
- 万能竿:磯竿(約3m〜5m)
- スピニングリール(2500番〜3000番)
- 道糸:ナイロンライン(2号〜3号)
- サビキ仕掛けセット
- サルカン
- ハリ(3号〜7号)
- ハリス(0.6号〜1.5号)
- 幹糸(1.5号〜3号)
- オモリ付きマキエカゴ(中または12号)
「サビキ釣りに必要な道具や仕掛け」を読んでみて気になるポイントはありましたか?
サビキ釣りは、釣り初心者でも操作しやすい「短いルアーロッド(2m〜3m程度)」を使用して楽しめます。
ですが、短いルアーロッドだと「長いサビキ仕掛け(特に6本バリ仕様)」を思い通りに扱えず「ライントラブル」が起こりやすいです。
ライントラブルを減らすために、短いルアーロッドに合わせてサビキ仕掛けの長さを調整しましょう。
「サビキ仕掛け(6本バリ仕様)は半分にカット」「ショートサビキ仕掛け(3本バリ)を準備する」の2点を押さえておくと良いと思います。
釣り糸や仕掛けを結び直す手間や時間を減らせるので、釣り初心者でもストレスなくサビキ釣りを楽しめます。
釣具準備の手間を省きたい方には、サビキ釣りで必要なアイテム一式が揃う「セット仕掛け(市販品)」がおすすめです。
セット仕掛けには、道糸と仕掛けを接続するために必要な「サルカン」や「スナップ付きサルカン」が付属してきます。
(サルカンには糸ヨリを防ぐ機能もあるため「ヨリモドシ」と呼ばれることもある)
このサルカンに「道糸」や「マキエカゴ(オモリ付き)」をセットしたら、すぐにサビキ釣りを始められますよ!
ここからは、サビキ釣りに必要な道具や仕掛けについて、詳しく紹介していきたいと思います。
サビキ釣りにおすすめの「釣竿(ロッド)」とは?
サビキ釣りにおすすめの釣竿は、「万能竿(長さ:3m〜5m程度)」「磯竿(号数:2号~3号)」です。
釣り初心者には、1本でさまざまな魚種や釣り方に対応してくれる「万能竿(長さ:3m〜5m程度)」が特におすすめ。
足場と海面の距離が近い堤防や港でなら、少し短い「ルアーロッド(約2.4m~2.7m)」でもサビキ釣りに挑戦できます。
細かく分類されているルアーロッドの中でも、長さと硬さのバランスがちょうど良い「エギング用」「シーバス用」が最適です。
釣竿の長さを選ぶ際は、釣り場所の高さを考慮するのが良いです。
基本的なセオリーとして「足場が高い場所=長い釣竿」「足場が低い場所=短い釣竿」を選べば間違いありません。
ただ、長すぎる釣竿は「重くて扱いにくい」「狙い通りに操作できない」といったトラブルが起こるため、基本的には3m程度の釣竿を準備しましょう。
堤防や海釣り公園でサビキ釣りを楽しむ方には、シマノから販売されている万能振出ロッド「マルチマリン」がおすすめ。
マルチマリンには豊富なラインナップがありますが、サビキ釣りには「M300」「M350」「M400」「M450」の4機種がマッチしています。
沖目に泳ぐ回遊魚をウキやサビキ仕掛けキャストして狙う場合、釣竿の反発を利用しやすい硬くパワーのある「MHクラス」のモデルを選びましょう。
サビキ釣りにおすすめの「リール」とは?
サビキ釣りにおすすめなリールは「2500番〜3000番のスピニングリール」です。
汎用性が高いため小型回遊魚・大型魚どちらが釣れても対応できますし、釣り初心者でも扱いやすいサイズ感ということがおすすめな理由になります。
リール番手の選び方として「使用する釣竿に適したサイズ(号数)」を意識しておくと良いです。
たとえば、万能竿(長さ:3m〜5m程度)でサビキ釣りに挑戦するなら「2000番〜4000番のスピニングリール」が最適。
また、磯竿(号数:2号~3号)を使用するなら「3000番スピニングリール」をセットすると、釣竿とリールのバランスが取れるのです。
バランスの取れている釣竿とリールを組み合わせると、サビキ仕掛けが扱いやすくなり、さらに疲労も感じにくくなるので、サビキ釣りを快適に楽しめます。
道糸には、比較的安価で購入できてライントラブルが少ない「ナイロンライン(2号〜3号)」がおすすめ。
目安ですがリールに約100m~150m程度の長さのナイロンラインを巻いておくと、釣り糸が切れたり絡まっても安心です。
サビキ釣りにおすすめの「サビキ仕掛けセット」とは?
サビキ釣りでは「サビキ仕掛けセット(堤防用)」を準備する必要があります。
サビキ仕掛けとは、撒き餌を詰めて魚を寄せる「サビキカゴ」と、複数の擬似バリ「サビキバリ」が連結した仕掛けのこと。
各メーカーから販売されている「サビキ仕掛け」には、「アジ専用」「サバ専用」「ママカリ専用」など、ターゲットに応じたラインナップがあります。
あなたが狙う「魚の種類」や「魚のサイズ」に合わせて、最適なサビキバリの「大きさ」「色(カラー)」を選択するのが良いです。
小型回遊魚を狙うなら「号数が小さい(サイズが小さい)」、大型回遊魚を狙うなら「号数の大きい(サイズが大きい)」サビキバリが必要になります。
「豆アジ(5cm程度)やカタクチイワシ=2号以下」「小型アジ(10cm程度)=4号〜5号」「良型アジ(20cm以上)=6号以上」を目安として押さえましょう。
サビキバリのスキン素材には魚を騙すため「擬餌(魚の皮、薄いゴム、薄いビニール)」が使われており、豊富なカラーバリエーションが存在します。
釣り初心者は、サビキバリとしてコマセ(アミエビ)と同じ色である「ピンク色」のを選ぶのがおすすめ。
海中に漂う「コマセ(アミエビ)」と勘違いした回遊魚がヒットしてきますよ。
サビキ釣りにおすすめの「マキエカゴ(オモリ付き)/エサカゴ」とは?
マキエカゴとは、マキエ(エサ)である、プランクトンの「アミエビ」「オキアミ」を詰めるカゴのこと。
網目や穴があるマキエカゴを海に沈めると、この穴からマキエが放出され、ターゲットの小型回遊魚が足元にたくさん寄ってくるのです。
マキエカゴには錆びにくく視認性に優れる「プラスチック製」と、形を変えられ速く沈む「スチール製」の2タイプが存在しています。
釣り初心者には主流であり安価で入手できる「プラスチック製」を使用して、サビキ釣りに挑戦してもらえたらなと!
本体が軽量なので体力を大幅に消費せず、小さいお子さんや女性、体力や筋力に自信がない人でも扱いやすいです。
サビキ仕掛けの最上部にマキエカゴを取り付ける「上カゴ式」、最下部にマキエカゴを取り付ける「下カゴ式」と、マキエカゴを取り付ける位置で呼び名が変わります。
釣り初心者は、仕掛けがシンプルで扱いやすい「下カゴ式」がおすすめで、サビキ釣り中の糸絡み(ライントラブル)を減らせますよ!
一般的な使い分けは「浅いタナ(表層)に回遊魚が泳いでいる=上カゴ式」「深場に魚が潜んでいる=下カゴ式」になります。
サビキ釣りにおすすめの「エサ(撒き餌)」とは?
サビキ釣りでは「エサ(撒き餌)」を海に撒いて、足元に魚を寄せる必要がありました。
エサ(撒き餌)として「アミエビ」と呼ばれるプランクトンが使用されることが多く、釣具店や通販サイトで購入できます。
小型回遊魚(アジやサバなど)はプランクトンが主食なので、アミエビに警戒することなく食いつくのです。
サビキ釣りを2人で4時間くらい楽しむなら、事前にアミエビを「2kg~4kg」くらい用意し、冷凍庫に保存しておくと良いです。
釣行前夜〜数時間前に冷凍庫から取り出し自然解凍させておけば、すぐにサビキ釣りに挑戦できますよ。
強い臭いはしませんが、若干潮の香りがするため、苦手な方はラップや保存袋(ジップ付き)で密閉するのがおすすめ。
アミエビには「ブロック状態」「チューブタイプ」「常温」「冷凍」など、いろいろな商品が販売されています。
お手軽にサビキ釣りを楽しみたい方には、「チューブタイプ」かつ「常温保存」ができる商品をおすすめします。
解凍する手間を省けますし、そのままマキエカゴにアミエビを詰められるため、手や服が汚れる心配も少ないです。
マキエ用にバケツを準備する必要もありません。
釣り場には、使用したエサや仕掛けなど、ゴミを放置せず、忘れずに持ち帰りましょう。
自然環境を大切に守っていくことは、釣り人としてのマナーです。
エサを扱う上で便利なアイテム①:吸い込みバケツ(蓋付き)
エサを扱う上で便利なアイテムとして「吸い込みバケツ(蓋付き)」があります。
吸い込みバケツとは、手を汚さずにマキエカゴに「アミエビ」を詰められる便利なサビキ釣り専用バケツです。
簡単にエサ付けできる仕組みをしていて、バケツ中央部でマキエカゴを上下に動かすと、アミエビが勝手にマキエカゴの中へ吸い込まれます。
手を汚さずに素早くエサを補充できるため、釣り初心者でも仕掛けの準備を快適に行えますよ!
(アミエビを保管するだけなら「普通のバケツ」や「水汲みバケツ」で代用できますが、自分でアミエビをカゴに詰める手間がかかります)
エサを扱う上で便利なアイテム②:マキエ用スプーン
エサを扱う上で便利なアイテムとして「マキエ用スプーン」があります。
(マキエ用スプーン以外に「コマセスプーン」や「マキエスコップ」と呼ばれることもある)
マキエ用スプーンとは、手を汚さずにマキエカゴに「アミエビ」を詰めるために使用するスプーンのことです。
冷凍状態のアミエビを砕く役割もあり、サビキ釣り以外にも船釣りやフカセ釣りなど、エサを使い魚を狙う様々な釣りで大活躍します。
サビキ釣りに必要な道具:すいこみバケツとは?
必須ではありませんが「すいこみバケツ」があると非常に便利です。
すいこみバケツとは、エサ(撒き餌)を簡単にマキエカゴに入れることができる専用のバケツ。
手を汚さずにサビキ釣りを楽しめますし、素早くエサを詰めれるため、釣具準備をスムーズに行えますよ!
すいこみバケツが無くても、割り箸やスプーンがあると代用することが可能です。
サビキ釣りに必要な道具:割り箸とは?
撒き餌が凍っている場合、「削る」「ほぐす」ことで解凍を促したり、ほかにも海水と「混ぜる」必要があります。
割り箸があると、上記の動作を全て行えて便利です。
(手が汚れる可能性があるため注意)
コンビニやスーパーでもらうこともできるため、釣行前に立ち寄るなら、ぜひ!
サビキ釣りに必要な道具:スプーンとは?
すいこみバケツが無い場合、スプーンがあるとエサ(撒き餌)をすくい、マキエカゴに詰めるときに役立ちます。
専用のコマセスプーンがあると便利ですが、コンビニでもらえるような「プラスチック製スプーン」でも代用可能です。
基本的なサビキ釣りの方法とは?
基本的なサビキ釣りの方法をご紹介していきます。
基本的なサビキ釣りの方法は、主に以下の手順です。
【基本的なサビキ釣りの方法|手順】
- サビキ釣りの手順①:エサを詰めたマキエカゴを海に投入する
- サビキ釣りの手順②:魚が食いついたら、ゆっくり抜き上げる
ここでは、基本的なサビキ釣りの方法として「手順①:エサを詰めたマキエカゴを海に投入する」「手順②:魚が食いついたら、ゆっくり抜き上げる」を詳しくご紹介していきます。
ほかにも「魚を取り込むときのポイント」を解説するので、気になる方はチェックしてみてくださいね!
サビキ釣りの手順①:エサを詰めたマキエカゴを海に投入
釣り場に到着したら「タックル一式(釣竿、リール、釣り糸、サビキ仕掛けなど)」の準備を整え、サビキ釣りスタート。
サビキ釣りの手順①は「アミエビ(エサ)を詰めたマキエカゴを海に投入する」になります。
アミエビを詰める際は「マキエカゴにふわっと詰める(目安は8割)」ことがコツで、アミエビが水中に綺麗に放出されるため、魚の群れが集まりやすくなるのです。
サビキ仕掛けを海に投げ入れたら、海底までマキエカゴが沈むまで(竿先にコツンと小さい衝撃が伝わるまで)放置します。
海底までマキエカゴが沈んだら、リールハンドルを数回巻き(1回転〜2回転)、海底からマキエカゴを「50cm~1m程度」浮かせてください。
このときマキエカゴからアミエビが放出されるため「回遊魚(アジやサバなど)」が足元に集まるのです。
回遊魚に違和感を与えずサビキバリ(擬似バリ)に食いつかせるためには「誘いのテクニック」も大切。
釣竿を大きく持ち上げて、ゆっくりな速度で竿先を元の位置に戻す(道糸をピシッと張ったまま)と、サビキ仕掛けが自然に落下している状態を演出できます。
すると、回遊魚の警戒心が薄れ、マキエ(アミエビ)と勘違いを起こしサビキバリに食いつくのです。
サビキ仕掛けを海に投入したら「底取り(仕掛けが海底に着いたか確認すること)」をする!
海底までサビキ仕掛けを沈める際は、リールに付属する「ベイル(釣り糸の放出をコントロールする役割)」を操作する必要があります。
ベイルを起こすと釣り糸が勝手に放出され続けるので、道糸(リールに巻かれている糸)に人差し指をかけ、ライントラブルを防ぎましょう。
ベイルから人差し指を離した途端、マキエカゴが海底まで沈み始めるので、あとはマキエカゴが海底に着くまで放置してOK。
手元や竿先に伝わる感触(軽くなるような感触)で底取りを行う釣り人も多いですが..。
釣り初心者は「釣り糸の変化」で底取りをするのがおすすめで、目視でわかりやすいですよ。
サビキ仕掛けの落下中や海底から離れている状態なら「道糸がピシッと張る」、海底に着いている状態なら「道糸はダラ〜と緩む」ことを押さえておきましょう。
底取りを確認できたら、ベイルを元の位置に戻します。
サビキ釣りの手順②:魚が食いついたら、ゆっくり抜き上げる
魚がサビキバリに食いつくと、竿先が「ビビビ」と動いたり、手元に「ブルブル」「グン」と振動や重みが伝わります。
魚のアタリ(反応)を察知できたら、竿を立て(竿先を上に向ける)、その後リールハンドルを一定スピードで巻いてきてください。
サビキバリに掛かっている魚を海中から回収できるので、ゆっくり抜き上げて取り込むことができます。
サビキ仕掛けを海に投入し、しばらく待っても(5分程度)「魚のアタリ(反応)がない」場合、足元に魚が回遊していない証拠です。
魚を寄せるためにも、1度サビキ仕掛けの回収を行い「アミエビ(マキエ)」を詰め直した後に、サビキ仕掛けを再び海に投入してください。
これを繰り返していると、足元に美味しい魚「アジ」「サバ」「イワシ」が集まるため、気付いたら魚がヒットし始めるのです。
詳しくは「サビキ釣りで魚が釣れない時のコツ」で紹介しますが、狙う水層を変えたり、使用する針の号数を変えると、いきなり魚がヒットすることも!
魚を取り込むときのポイントをご紹介!
魚を取り込むときに「竿先を地面に置かない」ことを意識するだけで、釣竿の破損や劣化を防止できます。
細く繊細な部分である竿先は地面に置いただけで「硬い砂」「砂利」が原因になり傷ついてしまうのです。
(最悪の場合、わずかな衝撃で竿先が折れる可能性も!)
また、ゴミが付着した状態が続くと、釣竿の劣化が早まるので、釣行後は「水洗い」を行うのが良いかと。
海面から魚を抜き上げたら、まず後ろに下がるか釣竿を左右に回し「マキエカゴ」を地面付けてください。
サビキ仕掛けが自由に動かないようにすることで、糸絡みを減らせますよ。
その後「竿先を地面に置かない」を意識しつつ、釣竿を安全な場所に立て掛けることができたら、魚の取り込みをトラブルなく行えるでしょう。
釣りに慣れるまでは、釣竿とサビキ仕掛けの間に身体を入れて、魚の口からハリを外すのがおすすめ。
釣竿とサビキ仕掛けの間隔を保てるので、サビキ釣りで起こりやすいライントラブル(仕掛けが絡まる)を減らせます。
複数匹の魚が掛かっても安心してハリから取り外せるため、魚が暴れても身体に針が刺さる事故も起こりにくいです。
サビキ釣りで魚が釣れない時のコツ4選をご紹介!
サビキ釣りで魚が釣れない時のコツは、主に以下の4つです。
【サビキ釣りで魚が釣れない時のコツ4選】
- 魚が泳いでいる水層(タナ)を早く見つける
- 追い食いを誘う
- 魚の口に合うハリの大きさ(号数)を選ぶ
- 沖を狙う(足元に魚が寄らない場合)
ここでは、サビキ釣りで魚が釣れない時のコツ4選「魚が泳いでいる水層(タナ)を早く見つける」「追い食いを誘う」「魚の口に合うハリの大きさ(号数)を選ぶ」「沖を狙う」について、詳しく紹介していきたいと思います。
サビキ釣りで魚が釣れない時のコツ①:「魚が泳いでいる水層(タナ)」を早く見つけること
サビキ釣りで魚が釣れない時は「魚が泳いでいる水層(タナ)を早く見つける」のがコツです。
魚には特定の水層を泳ぎながらエサを探す習性があるため、その水層にサビキ仕掛けを漂わせることが「釣果」を出す秘訣になります。
サビキ釣りのメインターゲットである「アジ」は海底付近から中層で活動することが多いです。
また「イワシ」「サバ」などは、比較的浅い水層を回遊していることが多いので、魚種ごとに大まかな行動パターンを把握するのがおすすめ。
効率的なアプローチができるだけで、釣り初心者でも1日を通して釣れる魚の数が大幅にアップしますよ。
(釣り場や天候状態などで「魚が泳いでいる水層」は変化するので、毎回同じパターンで釣れるとは限りません)
魚が泳いでいる水層(タナ)は、見落としをなくすために「海底→中層→上層」と順番を守り探るのが大切です。
海底までサビキ仕掛けを落としたら、まず海底付近を中心に「魚のアタリ(反応)」を確認してみましょう。
(魚の反応は「竿先の動き」や「ラインの張り具合」や「手元の感覚」を頼りに探ります)
反応がない場合、リールハンドルを巻き、サビキ仕掛けを回収しながら魚の居場所を見つけてくださいね。
サビキ釣りで魚が釣れない時のコツ②:「追い食い」を誘い、釣れた数を稼ごう
サビキ釣りで魚が釣れない時は「追い食い」を誘うのもコツです。
追い食いとは、1度のサビキ仕掛け投入で「複数匹の釣果を狙うテクニック」になります
群れで泳ぐ「小型回遊魚(アジやイワシなど)」が、1匹でもサビキバリに掛かり暴れ出すと、後を追うように2匹3匹目とヒットし始めるんです。
これは仕掛けの動きや魚が暴れる様子が引き金となり、連鎖的に周囲にいる魚の「捕食スイッチ」が刺激されることが理由。
「追い食い」を発生させるには、「魚のヒット(竿先が小刻みに揺れたり、釣り糸がピンと張るなど)」を確認しても、すぐに仕掛けを回収してはいけません。
魚がヒットしてから「10秒数える」「引きの重さが増す」まで、リールを巻き始める(サビキ仕掛けを回収する)のを我慢しましょう。
サビキ釣りで魚が釣れない時のコツ③:魚の口に合うハリの大きさ(号数)を選ぼう
サビキ釣りで魚が釣れない時は「魚の口のサイズに合わせてハリの大きさ(号数)を選ぶ」ことも大切です。
デメリットである「口に掛からない」「掛かっても外れる(バレる)」「ハリが伸びる!」を回避できるので「釣果(釣れる魚の数)」が大幅に変わりますよ!
小魚を釣るなら「ハリが小さい(2号〜4号)」のサビキ仕掛けを、大物狙いに挑戦するなら「ハリが大きい(6号以上)」を準備しておけば安心です。
サビキバリの素材は「スキン(合成素材)」「魚の皮(サバ皮)」「ハゲ皮」と3種類に分けられます。
釣り初心者には最も万能でオードドックスな「スキン素材」がおすすめで、リアルな小魚の皮を模しているので魚を騙しやすいです。
代表的なスキンカラーとして「ピンク」「白」「グリーン」が挙げられ、釣行日の状況に応じて色を選びましょう。
迷ったらマキエ(アミエビ)にそっくりな「ピンク色」を選ぶのが王道で、魚の視線を猛烈に惹きつけてくれます。
サビキ釣りで魚が釣れない時のコツ④:足元に魚が寄らないときは「沖」を狙おう
足元狙いのサビキ釣りで魚が釣れないときは「沖を狙う」のもコツ。
岸から離れている沖目には、警戒心が薄く誰でも釣りやすい魚が多く、さらに「魚が集まるポイント」が存在しているケースもあります。
サビキ仕掛けに「ウキ(魚のアタリを視覚的に捉える釣り道具)」を追加したら、海面に変化がある沖目に投げ込みましょう!
高活性の魚が集まる「敷石の沖側」「魚が跳ねた場所」「潮ヨレ」「潮目」を中心に狙えれば、メインターゲットである「アジ」「サバ」「イワシ」が簡単に釣れますよ。
ほかにも「コノシロ」「カマス」「カサゴ」「カワハギ」「グレ」「サヨリ」がヒットすることも!
海面に変化が見つけられない場合、同じ箇所にサビキ仕掛けを投げ入れることを意識すると良いです。
いろいろな箇所に「マキエ」をばら撒いてしまうと、あちこちに魚が散り散りになることが理由。
サビキ釣りで沖目を狙う際の釣り方は、基本的に足元を狙うサビキ釣りと同じです。
まずはアミエビを詰めた「マキエカゴ」を狙うポイントより、やや沖目に投げ入れます。
ウキの位置を確認しつつ、サビキ仕掛けの着水場所を把握したら、大きく釣竿をあおり海中にマキエ(アミエビ)を放出。
(狙い通りに仕掛けを投げ入れられなかったら、リールを巻いて仕掛けの場所を移動させればOK)
サビキ仕掛けとウキ止めまでの長さを短くし「浅い水層(タナ)に魚が潜んでいないか?」を探るのがおすすめで、見落としを最小限にできます。
魚の反応がないなら、ウキ止めの位置を上にずらし、少しずつ探る水層を深く下げていくと良いかと。
沖目にいる「魚のアタリ」を手元の感覚で察知するのは、経験が必要になるため釣り初心者には難しいかもしれません。
慣れるまでは「ウキの動き(海に沈む、左右に動くなど)」で、魚のアタリを判断するとわかりやすくおすすめです!
不自然にウキが動き「魚が反応している!」と判断できたら、落ち着いて釣竿を立て「フッキング」を成立させてください。
(ラインを弛ませないようにすると、針先にパワーが伝わるためフッキング成功率が格段にアップ)
あとは、一定のスピードでリールハンドルを巻き、魚を取り込むだけです。
魚を取り込むときに「竿先を地面に置かない」ことを意識すると、釣竿の破損や劣化を防止できましたね。
サビキ釣りで沖を狙う際に使用する、タックルの一例を下記にまとめました。
【サビキ釣り用タックル(ウキを追加したver)】
- 万能竿:磯竿(約3m〜5m)
- スピニングリール(2500番〜3000番)
- 道糸:ナイロンライン(2号〜3号)
- ウキ止め
- サビキ専用ウキ(中または12号)
- シモリ玉
- ウキストッパー
- サルカン
- ハリ(3号〜7号)
- ハリス(0.6号〜1.5号)
- 幹糸(1.5号〜3号)
- オモリ付きマキエカゴ(中または12号)
※市販のアジサビキ仕掛けだと「ハリ・ハリス・幹糸の3点セット」で入手可能です。
サビキ釣りで釣れた魚の鮮度を保つ「持ち帰り方」とは?
釣りの醍醐味として「自分で釣った魚を食べる」ことが挙げられ、釣行後の大きな楽しみです。
サビキ釣りでは「アジ」「イワシ」「サバ」といった、お刺身や焼き物・揚げ物など、いろいろな料理で美味しくいただける魚が釣れます。
この見出しでは、食卓に並ぶ魚の鮮度を大幅に保てる持ち帰り方として「氷締め」をご紹介します。
そもそも氷締めとは、釣った魚を「塩水(海水+氷)」の中に入れ、瞬間的に冷やす、最もシンプルで簡単な締め方です。
釣行前は釣具店やスーパーに立ち寄り、氷を購入し「クーラーボックス」に入れて保管しましょう。
釣り場に到着したら、「塩氷(氷に少し海水を混ぜるだけでOK)」を魚全体がたっぷり浸かるくらい作ります。
塩氷は海水で作るのがコツで、浸透圧の影響で「魚の身が引き締まり(水っぽくない)」「魚の旨みが逃げない」のです。
(サビキ釣りでは、すぐに魚が釣れる可能性があるため「釣りを始める前」に塩氷を作るのがおすすめ)
サビキ釣りで釣れた魚は、キンキンに冷えた「クーラーボックス(塩氷入り)」の中に、急いで保管してください。
約1時間ほど経過し完全に魚が冷えたら「保存袋(ビニールやジップロックなど)」に移し、再びクーラーボックスに浸けます。
魚を保存袋に移動させず、長い時間塩氷に浸けておくと、魚の体内に水が入り込むため注意。
海水の入っているクーラーボックスはとても重いです。
持ち帰る(釣りを終える)タイミングで、水を捨てるだけでも「軽量化」に繋がりおすすめ。
車内が海水まみれにならないので、ファミリーカーを守ることにも繋がります。
サビキ釣りの仕掛けについて
サビキ釣りを楽しむ上で「サビキ仕掛け」は欠かせないアイテムで、魚にアプローチする役割を担います。
釣果(釣れた魚の数)に大きく影響するため、サビキ仕掛けの正しい知識を把握することが上達への近道です!
サビキ仕掛けとは「複数の擬似バリ(魚の皮やビニールが付いた鈎)」が、1本の糸から枝分かれした仕掛けのこと。
「マキエカゴ(エサカゴ)」と呼ばれる、海にエサを撒き魚を集める釣具と組み合わせて使用します。
サビキ釣りの仕組みはシンプル、足元に「マキエカゴ」で魚を寄せ、足元に群がる小魚を「サビキ仕掛け」を屈指して釣り上げるのです。
サビキ仕掛けとマキエカゴ(エサカゴ)の組み合わせ方には、2つのタイプが存在しています。
サビキ仕掛けの1番上にマキエカゴ(エサカゴ)を付けると「上カゴ式」と呼びます。
また、サビキ仕掛けの1番下にマキエカゴ(エサカゴ)を付けると「下カゴ式」となり、サビキ釣りに慣れていない方には「下カゴ式」がおすすめ。
仕掛けが安定しているため扱いやすく、釣り糸が絡まる(ライントラブル)が起こりにくいです。
市販されているサビキ仕掛けの中では、Hayabusaから販売されている「サビキ釣りセット(堤防用) ピンクスキン 5本鈎」がおすすめの商品。
サビキ仕掛けとマキエカゴがセット手に入るため、別途で準備しなくて済みます。
「程よいハリ数(5本)」「短い長さ(全長1.2m)」と釣り初心者でも扱いやすい設計を採用していているのも魅力です。
疑似バリにも工夫が施されていて、マキエとして使用される「アミエビ」をイメージしたピンクスキンを採用。
海中で擬似バリがアミエビが見事に同化するため、初心者向けのサビキセットですが「アジ」「サバ」「イワシ」といった回遊魚が手軽に釣れます。
サビキ仕掛けの準備について
サビキ仕掛けの準備について解説していきます。
まずは釣竿のガイド部分にリールから伸びている釣り糸を通すことからスタートです。
順番を守りガイドに釣り糸を通せたら、サビキ仕掛けが準備できる状態になります。
(ガイドに釣り糸を通す時は、持ち手側から竿先(トップガイド)に向かい釣り糸を通すこと)
サビキ仕掛け(市販がおすすめ)の先端に付いている「スナップ(小さい金属製の留め具)」だけを取り出します。
スナップにトップガイド(竿先)から出ている釣り糸を結ぶと、サビキ仕掛けと釣り糸の接続は完了です。
糸が絡まないよう、サビキ仕掛けをパッケージから全て取り出してください。
サビキ仕掛けの最後に付いている「サルカン(金属製連結アイテム)」が糸と糸を結ぶ役割を担うため、そこにマキエカゴ(エサカゴ)を取り付けます。
振り出し竿でサビキ釣りに臨む場合、最後に釣竿を伸ばして、サビキ仕掛けの準備完了です。
マキエカゴ(エサカゴ)にプランクトンである「アミエビ」を詰めたら、いつでもサビキ釣りを始められます。
続いては「エサの準備について」見ていきましょう。
エサの準備について
サビキ仕掛けの準備が完了したら、「マキエカゴ(エサカゴ)」にエサであるアミエビを詰めていきます。
特別な道具を準備しなくても、手でマキエカゴを持ち、スプーンや割り箸を用いれば、マキエカゴにエサを入れることができます。
ですが、手が汚れたり強烈な臭い(人によっては)が付くため、アミエビを手で触れたあとは手洗いをする手間がかかります。
(手を汚したくない方には、チューブタイプのアミエビを準備するのがおすすめ)
アミエビをマキエカゴに簡単かつ素早く入れることができる便利アイテム「すい込みバケツ」を準備して、サビキ釣りにチャレンジする釣り初心者もいらっしゃいます。
手で直接アミエビを触れずにアミエビをマキエカゴ入れられるため、手や服装が汚れる心配がありません。
釣り場に着いたら、水汲みバケツで海水を汲み、すい込みバケツの中で「海水」と「撒き餌(アミエビ)」を混ぜます。
撒き餌(アミエビ)がしゃぶしゃぶになる程度海水を入れ、柔らかいコマセを作るのがコツで、魚に効果的にアプローチすることができます。
それでは、いよいよサビキ釣りの実釣スタートです!
サビキ釣りで魚が釣れない人が、今すぐチェックすべきポイント3つ!
自然や生き物を相手にするサビキ釣りでは、なかなか思い通りに魚が釣れないこともあります。
「魚が釣れないタイミングなのかも..」と感じたら、これから紹介する「サビキ釣りのコツ3選」を実践してみてください。
サビキ釣りで簡単に魚を釣る人々が揃って行っているコツなので、魚がヒットし始めるきっかけになること間違いなしです。
【サビキ釣りのコツ3選】
- 最初はエサをたくさん撒く(マキエをケチらない)
- マキエカゴにアミエビがあるかを確認する(エサが無くなっていないか?)
- サビキ仕掛けは魚の泳いでいる水層にを漂わせて使用する
上記の「サビキ釣りのコツ3選」を読んでみて気になるポイントはありましたか?
それでは、詳しく「最初はエサをたくさん撒く(マキエをケチらない)」をご紹介していきます。
サビキ釣りのコツ①:最初はエサをたくさん撒く
サビキ釣りのコツ①は「最初はエサをたくさん撒く」ことです。
サビキ釣り開始直後は魚が撒き餌に気付かない、もしくは警戒心が高くエサに食いついてこない可能性があります。
釣りを始めたばかりの時間帯は、撒き餌を2回〜3回ほど海に入れ直し、周囲に散らすことを意識しましょう。
食いっ気のある魚が足元まで回遊してきたり、魚の警戒心を解くことに繋がります。
1度に大量の撒き餌を使用する方が効果的に思えますが、実は逆効果なことも。
魚が満腹になり、釣れなくなる場合があるので撒き餌の撒き過ぎ注意です!
理想は少量ずつ、複数回に分けてエサを撒くことがポイントです。
1回に撒くエサの量の目安はマキエカゴ1/3〜半分程度なので覚えておくと便利ですよ。
釣竿を2回〜3回ほどしゃくり、海中にエサを撒いたら仕掛けを回収しましょう!
エサを詰め直し、再び海中に入れます。
これを釣れるまで繰り返しましょう!
サビキ釣りのコツ②:マキエカゴにアミエビがあるかを確認する
サビキ釣りのコツ②は「マキエカゴにアミエビがあるかを確認する」ことです。
ひとつ前の見出しでもお伝えしましたが、海中で2回〜3回ほどエサを撒くと、マキエカゴは空になります。
マキエカゴにエサが無いと、周囲にエサを散らせないため、魚を寄せられません。
(すると、サビキ釣りで魚を釣り上げるのが難しくなってしまいます..)
「海に仕掛けを投入してから5分程度」を目安にエサの有無を確認してみてください。
釣り初心者は「魚のアタリ(反応)がないな〜」と感じたら、すぐにマキエカゴの中にエサがあるか確認しても良いですね。
サビキ釣りのコツ③:サビキ仕掛けは魚の泳いでいる水層にを漂わせて使用する
サビキ釣りのコツ③は「魚の泳いでいる水層に、サビキ仕掛けを合わせて(漂わせて)使用する」ことです。
エサの種類やテクニックも大切ですが、海釣りでは「魚の泳ぐ水層で釣果(釣れる魚の数)が7割決まる!」と言われくらい重要になります。
魚の泳ぐ水層(タナ)と仕掛けの位置が合わないと、魚の視界(目の前)に仕掛けが入らないので、「魚のアタリ(反応)」が激減するのです。
釣り初心者は、まず海底付近から探り始め、魚が釣れなければ「中層→海面付近」と、どんどん探る水層を上げていきましょう。
サビキ釣りの注意点について
サビキ釣りでトラブルを起こさないために、意識するべき「注意点」をまとめました。
釣り初心者が意識するべき注意点は、主に以下の3つです。
【釣り初心者が意識するべき注意点3選】
- 釣り糸を巻きすぎないこと
- 陸に仕掛けを上げる時は周囲に注意すること
- 隣の人と仕掛けが絡まないこと
ここでは、釣り初心者が意識するべき注意点3選「釣り糸を巻きすぎない」「陸に仕掛けを上げる時は周囲に注意」「隣の人と仕掛けが絡まない」について、詳しく紹介していきたいと思います。
釣り初心者が意識するべき注意点①:釣り糸を巻き取りすぎない
釣り初心者が意識するべき注意点①は「釣り糸を巻き取りすぎない」ことです。
サビキ仕掛け上部にあるサルカンが竿先にある状態で、さらに釣り糸を巻き取る(リールハンドルを回すと)「竿先が折れる危険(負荷が集中するため)」があります。
魚がヒットしている際は、竿先まで意識できずに「釣り糸を巻き取りすぎる」ことが多いので注意。
足元までサビキ仕掛けが回収できたと感じたら、リールを巻くのをストップしてくれてOKです。
釣り初心者が意識するべき注意点②:周囲に注意する(陸に仕掛けを上げる時など)
釣り初心者が意識するべき注意点②は「周囲に注意する(陸に仕掛けを上げる時など)」ことです。
海から引き上げたサビキ仕掛けが、隣の人に当たると「針が危ないよ!」「釣りを邪魔しないで!」と勘違いで注意されることがあります。
魚が掛かっていると興奮して周りが見えなくなりがちですが、できるだけ慌てず周りに気を配れるように気を付けてくださいね。
風が強い日だと、仕掛けが勝手に流されてしまいます。
あまりにも仕掛けのコントロールができない際は、釣り場を移動することも視野に入れましょう。
釣り初心者が意識するべき注意点③:隣の人と仕掛けが絡まないこと
釣り初心者が意識するべき注意点③:「隣の人と仕掛けが絡まない」ことです。
陸上では仕掛けが風に流されることがありますが、海に沈めたサビキ仕掛けは潮が原因となり「横に流される」ケースも!
そうなると、自分の仕掛けと隣で釣りをしている人の仕掛けが絡まるトラブルが起こるのです。
このようなトラブルを回避するためにも「隣の人と距離を取る」「仕掛けが流されたら回収し、あらためて沈め直す」の2点を意識すると◎